「どうせ資格試験のためだけのIT知識でしょ?」
そう思っている方にこそ読んでほしい内容です。
中小企業診断士の情報システムは、単なる試験対策にとどまりません。
実務補習や現場でのヒアリング時にも、“ITがわかる診断士”の価値は高まっています。
本記事では、50代からでも習得できる情報システムの基本を、資格学習と実務活用の両面からやさしく解説します。
中小企業診断士試験に出る「情報」の正体
中小企業診断士の一次試験科目のひとつ、「経営情報システム」は、その名のとおり“情報”に関する知識が問われる分野です。
ITに苦手意識を持つ50代の受験者にとっては、「専門外だ」「実務に関係ない」と感じて敬遠されがちですが、実はこの科目こそ“実務に活きる知識の宝庫”なのです。
診断士試験が求める“情報”とは?
まず前提として、中小企業診断士試験で問われる「情報」は、プログラミングやシステム構築といった“技術職向け”の内容ではありません。
主に出題されるのは以下のような領域です。
• 情報システムの構成(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク)
• 業務システムの種類と導入効果(販売管理、生産管理、会計システムなど)
• データベースの仕組みと活用
• セキュリティ対策とリスク管理
• 最新のITトレンド(クラウド、IoT、AI など)
これらはすべて、「ITを活用して経営課題をどう解決するか」という観点から出題されています。
つまり、ITそのものよりも、“経営とITの接点”に焦点を当てた内容になっているのです。
実務補習や顧問業でも使える基礎知識
実はこの「経営情報システム」で学ぶ内容は、資格を取得した後にもさまざまな場面で役立ちます。
たとえば、実務補習の中で「現場の業務フローを可視化する」「IT導入の課題をヒアリングする」といった場面では、基本的なITの理解が欠かせません。
また、経営者との面談時に「販売管理ソフトは何を使っていますか?」と聞かれたときに、まったく知識がなければ、信頼を損ねることもあります。
つまりこの科目は、「試験のためにだけ勉強する知識」ではなく、「診断士として最低限身につけておくべきリテラシー」だと言えるのです。
「わからないまま」進まないための第一歩
ここで大事なのは、“全部を完璧に覚える必要はない”ということです。
むしろ、苦手意識を持つ50代の方こそ、「図解」や「たとえ話」を使って、“ざっくりと全体像をつかむ”ところから始めるのが有効です。
次のパートでは、出題傾向を踏まえた「学習の順番」と「つまずかないコツ」について、具体的に解説していきます。

50代からでも理解できる!学習の順番
「ITに苦手意識がある」「何から手をつけていいか分からない」──そんな50代の方でも、中小企業診断士試験の「経営情報システム」は、正しい順番で学べば着実に得点できる科目です。
ここでは、苦手意識を抱える方にこそおすすめしたい、“図解と実感”を軸にした学習ステップをご紹介します。
ステップ①|用語に触れるより、まず「全体像」をつかむ
まず最初にやるべきは、専門用語の暗記ではなく「情報システムって何のためにあるのか?」という全体のイメージをつかむことです。
たとえば、「販売管理システム」と聞くと難しく感じますが、要するに「誰に何を売ったかを記録する道具」。
このように、まずは “システム=業務の効率化を助ける道具” という発想で、実生活に置き換えながら学ぶことが第一歩です。
特におすすめなのが、「企業の業務フロー図(販売→在庫→会計など)」をざっくり俯瞰して見ること。
それだけでも、「どこでITが使われているか」が見えてきます。
ステップ②|出題頻度が高いテーマから優先して学ぶ
診断士試験では出題傾向がある程度パターン化されています。
まずは「よく出る分野」から重点的に押さえることで、効率よく得点に結びつけましょう。
具体的には、以下の3分野が頻出です:
• ネットワークの基礎(LAN・WAN・クラウド)
→ 例:「クラウド導入のメリットとして適切なものはどれか?」
• データベースと正規化
→ 例:「第3正規形の特徴として正しいものはどれか?」
• 業務システムの活用と導入効果
→ 例:「ERP導入により期待される経営効果として適切なものは?」
最初からすべての分野を完璧に理解しようとする必要はありません。
「出題頻度が高く、実務でも関わる可能性がある領域」から、徐々に学びを積み重ねていきましょう。
ステップ③|実例・図解・動画を活用し、感覚で理解する
50代の方にとって、情報の流れや仕組みを“文章だけで”理解するのはハードルが高いかもしれません。
その際に有効なのが、「図解」や「たとえ話」を多用した教材です。
たとえば:
• サーバーは「図書館」、クライアントは「利用者」
• データベースは「整理された倉庫」
• VPNは「鍵付きの地下通路」
こうした感覚的な理解は、暗記ではなく“腹落ちする”学習につながります。
最近では、図解中心のテキストやYouTubeの講義動画も充実しており、1日15分でも習慣化すれば知識が定着していきます。
まずは“理解できそう”と思えることから始めよう
苦手意識があると「最初から完璧を目指してしまいがち」ですが、それは逆効果です。
むしろ、「わかるところ」「身近に感じられるところ」から入るのが、長続きのコツです。
次のパートでは、実際にITが苦手な50代の方にもやさしい参考書・講座・動画など、理解促進に役立つ具体的なツールをご紹介します。
IT苦手層にやさしい参考書&講座
50代でITに苦手意識がある方は、「専門用語が難しい」「イメージが湧かない」と感じることが多いでしょう。そこで重要なのが、「図解中心」「例え話が多い」「短時間で学べる」といった特徴を持つ教材を選ぶことです。ここでは、学習効率を高めるために役立つ書籍や講座、動画コンテンツを紹介します。
おすすめ書籍
1. 『いちばんやさしいITパスポート 絶対合格の教科書』
・初心者向けの図解が多く、試験に出やすい用語をやさしく解説。
・ITパスポート試験対策として有名ですが、診断士試験の基礎理解にも有効です。
2. 『経営情報システム入門(第2版)』柴直樹/水上祐治 著(日科技連出版社)
・中小企業診断士一次試験の「経営情報システム」に対応する初学者向け教科書。
・図解が豊富で用語の意味から全体像まで丁寧に解説されています 。
3. 『中小企業診断士 第1次試験 過去問題集 経営情報システム』(TAC出版)
・過去問を解くことで「出題パターン」を実感でき、学習の定着が早まります。
・図解や用語解説も丁寧で、復習用としても活用できます。
動画・オンライン講座(Udemy)
• 『よくわかるシステム運用管理 シンプルな図で解説』(日本語/講師:MICHI ANNAI)
システム運用の流れや概念を図で学べる講座。情報システムの基礎理解に役立ちます。更新は2025年6月で最新版です 。
• Udemyの「情報システム入門(情報システム・クラウド・DB)」など図解中心の講座
「情報システムのスキルを伸ばしたい」をコンセプトにしたコースがあり、初学者向けに分かりやすく学べます 。
便利な学習サポートツール
• 単語カードアプリ(Quizletなど)
→ 「VPNとは?」など、用語をカード化して隙間時間に復習可能。
ポイントは、“いきなり過去問を解かない”こと。
まずは上記のような図解中心の教材で感覚をつかみ、基礎が固まったら問題演習に移ると効率が良いです。
次のパートでは、「資格取得が実務にどう活きるか」という観点から、IT知識を武器にする理由を解説します。

資格取得が「使えるITスキル」につながる理由
中小企業診断士の試験で学ぶ「経営情報システム」は、単なる筆記試験対策にとどまりません。
この科目で得たIT知識は、再就職・副業・実務補習・顧問業務など、実際のビジネス現場で役立つ“武器”になります。
ここでは、診断士資格とともにITスキルがどのように活かされるのか、その理由を具体的に解説します。
現場では「わかる診断士」が重宝される
中小企業の経営支援を行う中で、ITに関する課題は避けて通れません。
たとえば、以下のような相談が多く寄せられます。
• 「在庫管理をエクセルからシステム化したい」
• 「会計ソフトをクラウドに移行したい」
• 「業務効率化のために何か良いツールはないか?」
こうしたときに、基本的なITの構造や言葉が理解できていなければ、ヒアリング自体が成り立ちません。
逆に、少しでも仕組みを理解していれば、「何に悩んでいるか」をくみ取り、“経営とITをつなぐ通訳”のような役割を果たすことができます。
「実務補習」でITスキルが思わぬ武器に
中小企業診断士の登録に必要な「実務補習」では、実際の企業にヒアリングを行い、経営課題を分析し、改善提案を行います。
このとき、現場の業務フローや利用中のシステムを整理する場面で、経営情報システムの基礎知識が非常に役立ちます。
特に、業務プロセスの可視化(BPM:Business Process Management)や、情報の流れの把握は、チーム内で重宝されるスキルです。
実務補習でITの話題に強みを発揮できれば、その後の信用や案件紹介にもつながりやすくなります。
定年後の再就職・副業にも直結する知識
50代・60代以降のキャリアを考える上でも、「最低限のITリテラシー」を持っていることは大きな強みです。
• 再就職での書類作成、報告業務
• 副業でのクラウド会計やSNS運用
• 小規模企業への経営支援・顧問契約
これらの場面では、WordやExcelの操作だけでなく、「情報がどのように流れ、蓄積・活用されていくか」といった仕組みの理解が求められるようになります。
診断士試験で得られる知識は、こうした場面での“即戦力”になるのです。
難しいスキルではなく「経営とのつなぎ方」がポイント
誤解されやすいのですが、診断士に求められるIT知識は「高度な専門スキル」ではありません。
必要なのは、「この業務にはどのようなシステムが合うか」「それをどう経営に役立てるか」を考える視点です。
つまり、ITは単なるテクノロジーではなく、診断士としての“課題解決ツール”として捉えることが重要です。
まとめ|50代こそ、情報システムを“使える知識”に
「情報システム」と聞くだけで身構えてしまう——
そんなITへの苦手意識を持つ50代の方も少なくありません。
しかし、中小企業診断士試験における「経営情報システム」は、イメージと実感をもとに理解できる科目です。
本記事では、以下のポイントを押さえてきました:
• 情報システムは「経営とITの接点」を理解する科目である
• 50代でも実務と結びつけて学べば、理解がスムーズに進む
• 図解・動画・例え話を活用すれば、専門用語も怖くない
• 得た知識は、試験対策だけでなく再就職や副業にも活きる
つまり、試験対策を通じて、ITに強い「実務家診断士」への第一歩を踏み出せるのです。
行動への一歩|今日からできる小さなスタート
「苦手だから…」と避けるのではなく、まずは一冊、図解中心の入門書を手に取ってみましょう。
また、YouTubeやUdemyの講座を1本見るだけでも、「なんとなくわかってきた」という感覚が得られるはずです。
おすすめの最初の一歩:
✅ 『経営情報システム入門(第2版)』を1日10ページ読む
✅ YouTubeで「VPNとは?」の図解動画を1本視聴
✅ QuizletでIT用語カードを3つ覚える
このように、小さな行動からで大丈夫です。
50代からの学び直しにおいて、理解のスピードではなく、続ける工夫が成功のカギを握ります。
情報システムを「避けるもの」ではなく、「使える知識」として捉え直すことで、診断士としての視野も実務対応力も大きく広がっていくでしょう。
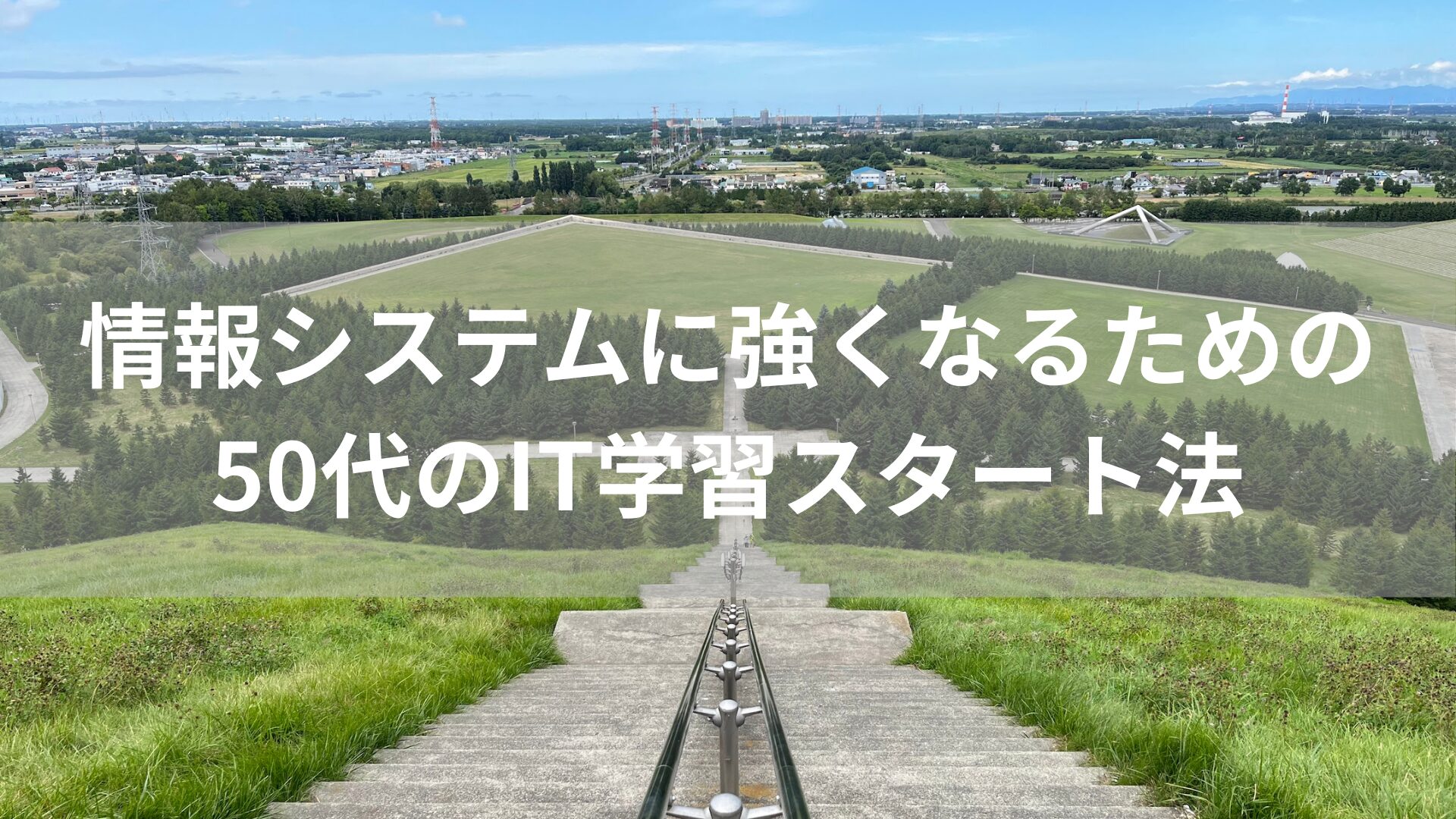

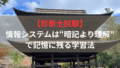
コメント