「いつも時間に追われてイライラしてしまう」「頑張っても成果が見えない」──そんなストレスを抱えていませんか?
仕事、介護、家事が重なると、気持ちも体も限界になりがちです。
でも、その時間、本当に必要なものばかりでしょうか?
中小企業診断士が提案するのは、まず現状の「見える化」。
時間を診断し、ムダを減らすことで、ストレスも大幅に軽減できます。
本記事でその具体策を学びましょう。
現状を「見える化」することがなぜ重要なのか
「もっと頑張らなきゃ」「効率よく動かなきゃ」と、つい無理をしていませんか?
仕事も家庭も介護も、一生懸命にこなしているのに、なぜか時間が足りず、心も体も疲弊していく──そんな悪循環に陥っている人は少なくありません。
原因のひとつは、現状の「見える化」ができていないことです。
私たちは普段、無意識のうちに「なんとなく」時間を使い、「なんとなく」優先順位を決めています。例えば、つい後回しにしていた家事が重なったり、想定外の介護対応に追われて本業に集中できなかったり……その結果、「いつも時間に追われる感覚」が強くなるのです。
中小企業診断士の仕事でも、企業が抱える課題の多くは「現状を正確に把握していない」ことが原因です。
売上が減る、コストが増える、といった表面的な現象に振り回されるのではなく、まずは数字やデータで現状を見える化し、問題点を明らかにする──これは時間管理にも全く同じことが言えます。
現状の見える化ができれば、ムダな作業や低い効果しかない行動が一目で分かり、逆に「本当にやるべきこと」が見えてきます。
時間は有限です。
だからこそ、最初の一歩は「どこに時間を使っているか」を記録し、現状を診断すること。
ここから、ストレスの少ない両立生活がスタートします。
次の章では、具体的にどうやって時間を見える化していくのか、その手順をご紹介します。
時間の「見える化」の手順
現状の時間の使い方を見える化する方法は、とてもシンプルです。
ここでは、中小企業診断士が企業診断で実践する「現状把握のフレーム」を応用した、3つのステップをご紹介します。
ステップ1|1週間の時間をすべて記録する
まずは、「何に時間を使っているか」を正確に知るために、1週間分の行動を記録します。
おすすめは紙の手帳やExcelなどの表に、15〜30分単位で実績を書き出す方法です。
仕事、介護、家事、自分の時間……すべて「見える化」してみましょう。
ポイントは、予定ではなく「実際にやったこと」を書くこと。
人は意外と無意識にスマホやテレビに時間を費やしていたり、同じ作業を何度も繰り返していたりします。
それを知るだけでも、「ここは改善できる」という気づきが生まれます。
ステップ2|時間の使い方を分類する
次に、記録した内容を4つのカテゴリに分けます。
• 重要で緊急
• 重要だが緊急ではない
• 重要ではないが緊急
• 重要でも緊急でもない
この「時間のマトリクス」を使うと、あなたの時間の多くが「重要ではないが緊急」なことに奪われているケースが見えてきます。
例えば、突然の介護対応や家族からの頼まれごとがこれに当たります。
一方、「重要だが緊急ではない」仕事や学びは、つい後回しにされがちですが、ここに時間を割くことが長期的な両立のカギになります。
ステップ3|やるべきこと・減らすべきことを決める
最後に、分類結果をもとに、次のようにアクションを決めましょう。
• 「重要かつ緊急」なことは効率よくこなす
• 「重要だが緊急でない」ことにもっと時間を割く
• 「重要でない」ことは減らす・委ねる・やめる
例えば、介護サービスを利用して負担を減らす、家事代行を活用する、仕事の中で誰かに任せられる業務を見つける、といった選択肢が出てきます。
「全部自分でやらなければならない」という思い込みを手放し、必要なものに集中することが、ストレスの少ない両立生活への第一歩です。
見える化した結果を活かす改善アクション
現状の時間を見える化し、ムダや優先順位の低い行動が明らかになったら、次は改善アクションです。
ここでは、中小企業診断士が企業支援の現場でも用いている「仕組み」と「習慣」の改善ポイントを3つご紹介します。
優先順位を決める「時間の予算化」
時間もお金と同じで、予算を決めることで無駄遣いを防げます。
1週間の時間を把握したら、次の1週間で「最も大切にしたい時間」に優先的に配分します。
例えば、「仕事に40時間、介護に15時間、家事に10時間、自分の学びに5時間」というように、予算を意識するだけで本当に必要なことが見えてきます。
このとき、「重要だが緊急ではないこと」に時間を確保するのがコツです。
未来のための学びや健康維持の時間は、長い目で見て必ずリターンがあります。
ムダな作業を減らす「仕組み化」
見える化の過程で、同じ作業を何度もやっている、手順が定まっていない、といったムダが見つかった人も多いでしょう。
例えば、介護の記録をノートで管理していて情報が散らかるなら、アプリで一元管理する。
家事も「曜日で担当を決める」「マニュアルを作る」など、仕組みにしてしまうと頭の負担も減ります。
仕事でも、簡単なルーチンはテンプレート化やツールで自動化できないか検討してみましょう。
他人の力を借りる「外注と分担」
「全部自分でやらなければ」と思い込んでいませんか?
見える化した結果、どうしても時間が足りない場合は、他人の力を借りることを検討します。
介護保険サービスの利用、家事代行、職場での業務分担……これらは決して甘えではなく、限られたリソースを最適化するための有効な選択肢です。
他人の力を借りることで、本来自分しかできない重要な役割に集中できるようになります。
現状の見える化と改善アクションを組み合わせれば、時間は必ず取り戻せます。
次の章では、こうした改善を習慣化するために役立つ「診断士おすすめの時間管理ツール」をご紹介します。
時間管理を習慣化するツール活用法
現状の見える化と改善アクションができても、三日坊主で終わってしまっては意味がありません。
大切なのは、「習慣として定着させる仕組み」をつくることです。
ここでは、中小企業診断士が実務の中でも活用している、おすすめの時間管理ツールをご紹介します。
カレンダーアプリで「予定を見える化」
GoogleカレンダーやOutlookなどのカレンダーアプリは、予定の管理だけでなく、時間の予算化にも役立ちます。
改善したい時間配分をそのまま予定に書き込み、仕事・介護・家事・学びの時間を色分けしておくと、バランスが一目でわかります。
家族とカレンダーを共有すれば、介護や家事の負担も分担しやすくなります。
タスク管理アプリで「ToDoを一元化」
忙しい日々の中では、「やるべきこと」を頭の中だけで管理するのは危険です。
TodoistやMicrosoft To Doなどのタスク管理アプリを使い、仕事・家庭・介護のタスクをまとめて管理しましょう。
優先順位をつけたり、リマインダーを設定することで、抜け漏れやストレスを減らせます。
時間記録アプリで「習慣化を定着」
見える化した時間の記録を習慣にするには、タイムトラッキングアプリが便利です。
TogglやaTimeLoggerを使えば、スマホで簡単に時間の使い方を記録できます。
毎週見返して振り返ることで、自分の改善状況が分かり、モチベーションの維持につながります。
ツールはあくまでサポート役ですが、使いこなすことで時間管理が習慣化し、ストレスが減り、やりたいことに集中できる環境が整います。
無理なく続けられる仕組みをつくり、より充実した毎日を手に入れましょう。
まとめ:見える化から始まる、ストレスの少ない両立生活
仕事、介護、家庭の両立は、ただ頑張るだけでは乗り越えられません。
現状が見えていない状態で動き続けると、無理やムダが積み重なり、心身の負担は大きくなる一方です。
だからこそ、まずは現状を「見える化」することが大切です。
1週間の行動を記録し、優先順位を決め、やるべきこととやめるべきことを見極める。
そして、仕組み化や外注、ITツールの力を借りて、習慣として定着させる。
この一連の流れが、限られた時間の中で、ストレスを減らしながら自分らしい生活を取り戻すための第一歩になります。
時間は、あなたの人生そのものです。
中小企業診断士の視点で見つけた「ムダ」を削り、本当に大切なことに集中するために、ぜひ今日から「見える化」を始めてみてください。
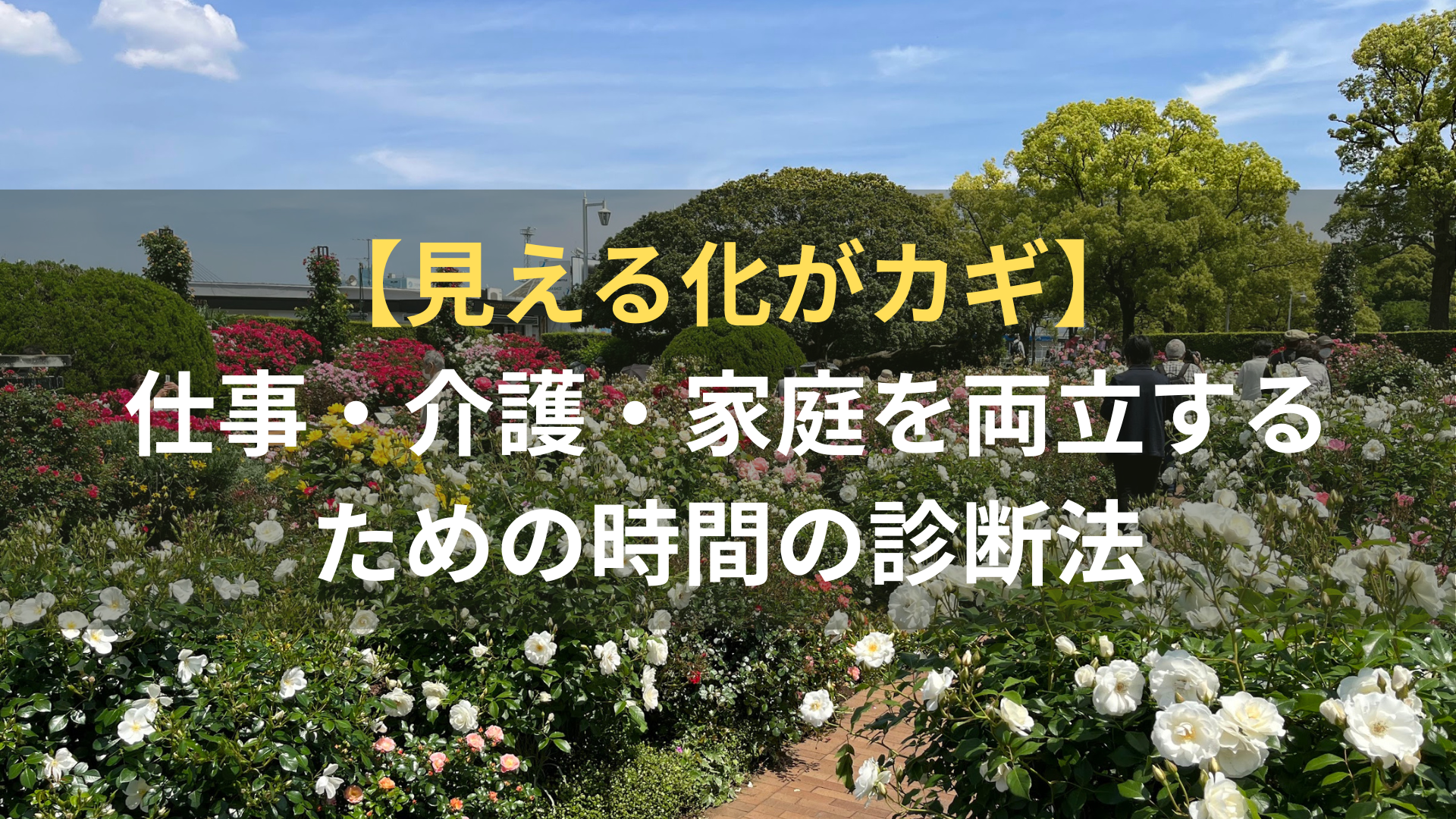


コメント