中小企業診断士試験の中でも「運営管理」は、比較的得点しやすい科目といわれています。
ですが実際に学び始めると、「生産管理」と「店舗・販売管理」、2つの分野がまったく別物に感じて、混乱する人も多いのではないでしょうか?
どちらも重要なのに、片方に偏った学習になってしまう――そんな悩みを抱える受験生のために、本記事では「運営管理を一気に理解する」横断的な学習法をご紹介します。
運営管理は“二分化”されて学びにくい?
中小企業診断士の1次試験における「運営管理」は、出題範囲が大きく2つの分野に分かれています。
一つは製造業の現場を扱う「生産管理」、もう一つは小売・サービス業の現場を扱う「店舗・販売管理」です。
この2分野、出題内容も用語もまったく異なるため、最初はまるで“別の科目”を2つ同時に勉強しているような感覚になることも珍しくありません。
たとえば、生産管理では「IE(インダストリアル・エンジニアリング)」「レイアウト設計」「設備保全」などの専門用語が飛び交い、
一方の店舗管理では「陳列方法」「接客マナー」「POSシステム」など、全く性質の異なるトピックが並びます。
そのため、学習初期にありがちなのが、
• 片方(多くは店舗管理)を先に進めすぎてしまい、
• もう片方(多くは生産管理)が手薄になる
という“バランスの悪い”状態に陥ることです。
また、インプット段階では知識が断片的になりやすく、過去問を解こうとしても「どこで学んだ内容だったか思い出せない」という混乱を招きがちです。
こうした“学びにくさ”の原因は、両分野を「分断して学んでしまう」ことにあります。
実はこの2つの分野には共通する考え方や用語も多く、互いに補完し合うような関係性が存在しているのです。
次章では、その“つながり”に注目しながら、生産管理と店舗管理を効率的に学ぶためのコツをご紹介していきます。
生産管理×店舗管理の関連性
一見まったく異なるように思える「生産管理」と「店舗・販売管理」ですが、実は共通する視点やプロセスが数多く存在します。
この“つながり”を意識することが、運営管理を効率よく、そして本質的に理解するための鍵となります。
在庫管理は両分野の架け橋
たとえば「在庫管理」は、生産管理においても店舗管理においても重要なテーマです。
• 生産管理では、材料や仕掛品の在庫を適切に管理し、ムダをなくすことが求められます。これはJIT(ジャストインタイム)やEOQ(経済的発注量)といった考え方と密接に関係しています。
• 一方、店舗管理では、売れ筋商品を切らさず、不良在庫を持たないようにすることが求められます。ここではPOSシステムによる販売データの活用やABC分析といった手法が出てきます。
つまり、在庫管理というテーマを「生産と販売の中間にある視点」として捉えることで、両分野を橋渡しすることができるのです。
情報とモノの流れは一本でつながっている
もう一つの例は、「SCM(サプライチェーン・マネジメント)」という概念です。
SCMは、生産から販売までの一連の流れを最適化する考え方であり、
• 生産側では、調達・製造・在庫の連携
• 販売側では、需要予測・店舗補充・顧客ニーズ対応
といった観点から出題されます。
生産現場と店舗現場は、バラバラに存在しているわけではなく、情報とモノの流れでつながった“ひとつの流れ”として捉えるべきなのです。
この視点を持てば、単なる暗記から一歩抜け出し、「なぜこの知識が重要なのか」が実感できるようになります。
システム・ITも共通語
さらに、両分野に共通するテーマとして、「情報システム」の活用もあります。
• 生産現場では、生産管理システム(MRP、ERP)
• 販売現場では、POSや販売管理システム
これらは「業務の効率化」という共通目的のもとで活用されており、ITリテラシーが問われる点でも共通しています。
このように、出題分野を“線”でつなぐ意識を持つことで、学習の定着度は大きく変わります。
次章では、この「関連性」をうまく活かしながら、2つの分野を横断的に理解するための具体的な学習法をご紹介します。
科目を横断的に理解するための工夫
運営管理の2分野を効果的に学ぶためには、それぞれを“別の知識”として覚えるのではなく、「つながり」と「構造」で整理することが重要です。
ここでは、科目を横断的に理解するための具体的な工夫を3つご紹介します。
図解で学ぶ!つながる用語マップ
多くの受験生がつまずく原因は、用語がバラバラに頭に入ってしまうことです。
たとえば、「工程分析」「物流」「棚卸資産管理」などは、それぞれ独立した単元で出てきますが、実務ではすべてが一連の流れの中にあります。
このとき効果的なのが、「用語マップ」や「フロー図」を使って関連づけることです。
• 材料調達 → 生産計画 → 製造 → 出荷 → 流通 → 店舗補充 → 顧客販売
このような流れに沿って用語を配置すると、意味や役割がグッと理解しやすくなります。
図解を自作するのが難しい場合は、市販の参考書やYouTubeの図解動画、図表の多い問題集などを活用するとよいでしょう。
事例で覚えるシステム運用(SCM・ERPなど)
横断的理解に有効なのが、システム系の用語を「具体的な現場のイメージ」で捉えることです。
たとえばERP(統合基幹業務システム)は、
• 生産部門では材料の発注や在庫管理に活用され
• 販売部門ではPOSや売上データとの連携で販売計画に貢献します。
このように、一つのシステムがどの部署でどう使われているのかを「物語」として覚えることで、複数分野をまたぐ知識が自然に定着します。
企業の業務プロセス全体を見渡す視点は、診断士としての思考力そのものにもつながります。
キーワード検索 → 比較 → 統合の学習法
インプットの段階で「これは生産管理だけの話かな?」「店舗でも似た考え方があったはず…」と感じたら、あえて自分で比較してみることが有効です。
たとえば「在庫管理」で検索して、
• 生産管理ではどのように扱われているか
• 店舗管理ではどう活用されるか
を並べて整理することで、共通点と相違点がクリアになります。
この「比較 → 統合」のプロセスを意識的に繰り返すことで、単なる暗記から“診断士らしい視点”への進化が期待できます。
次章では、実際の試験でこうした「つながり」をどう活かすのか、複合出題への対応方法について具体的に見ていきます。
複合出題への対応力をつけるには
中小企業診断士試験の「運営管理」では、年々“横断的な視点”を問う出題が増えています。
つまり、生産管理と店舗管理それぞれの知識を単体で覚えているだけでは太刀打ちできない問題が多くなってきているのです。
ここでは、複合出題に強くなるための実践的な対策を2つ紹介します。
過去問での“つなげて解く”練習
複合問題に対応するには、「解きながら知識をつなげる」習慣をつけることが大切です。
たとえば、以下のような出題は過去にも見られます:
Q. サプライチェーン全体の効率化を図る際に、需要予測情報を活用して在庫を最適化する方法として最も適切なものはどれか。
このような問題では、
• 生産側の在庫管理知識(MRP、JIT)
• 販売側の情報活用(POS、需要予測)
• さらにSCM全体の理解
といった「複数領域の知識」が問われています。
こうした問題を解くときは、答え合わせ後に「これはどの分野にまたがる知識か?」と自分で分析する癖をつけましょう。
出題の“背景構造”に気づけるようになると、初見問題にも強くなります。
模試・予想問題で弱点を洗い出す
複合問題に対応するには、模試や予想問題を活用して「知識のつながりが弱い部分」を発見するのも効果的です。
• 生産系の専門用語は覚えたのに、販売分野の言い換え表現に惑わされて失点した
• ITやシステム関連で、どの領域に使われるのか混乱した
こうした“曖昧ゾーン”を把握することで、今後の復習の優先順位が明確になります。
また、模試を受けたあとは、単に点数を気にするのではなく「この問題はどの分野と分野の組み合わせだったか?」を意識して振り返るようにしましょう。
これが、診断士試験特有の「複合的思考力」を磨くことにつながります。
複合出題は、暗記型の学習では太刀打ちできません。
だからこそ、横断的に学んできたあなたの“構造的な理解”が、大きなアドバンテージになります。
次章では、学びの最後の仕上げとして、試験本番に向けたツール・教材の活用方法をご紹介します。
まとめ|「点」でなく「線」で覚える学習法
「運営管理」は、生産管理と店舗管理という2つの分野を扱う広範な科目です。
だからこそ、知識を「点」としてバラバラに暗記するのではなく、「線」でつなげて理解することが、合格への近道になります。
本記事では、以下のような“横断的理解”の重要性をお伝えしてきました:
• 在庫管理・SCM・情報システムなど、共通テーマの活用
• 図解やフローで構造を見える化し、記憶を強化する方法
• 過去問や模試で「つながり」を意識して実践力を鍛えるアプローチ
これらの視点は、単に1次試験対策にとどまらず、将来2次試験や実務に進んだ際にも必ず役に立つ「診断士的思考」の土台になります。
特に、50代以降のシニア世代にとっては、「理解できる構造をつくる」ことこそが最も効果的な学習法。
単なる詰め込みではなく、経験や常識ともリンクした“意味のある学び”として定着させることができます。
ぜひ、今回ご紹介したような「つながり」に注目しながら、運営管理の学習を進めてみてください。
あなたの診断士合格を、心より応援しています。

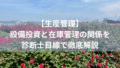
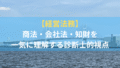
コメント