中小企業診断士試験の事例Ⅱでは、多くの受験生が「強み」と「機会」を答案に書きます。
しかし、模範解答や合格者再現答案と比べると、自分の解答がどこか凡庸で差がつかない――そんな経験はありませんか?
実は「強み=規模」「機会=市場拡大」といった抽象的な書き方に陥ると、一気に得点が伸び悩みます。
本記事では、与件文の根拠をどう活かし、他の受験生と差をつける答案を作るのか、診断士的なテクニックをご紹介します。
ありがちな失敗パターン
事例Ⅱで問われる「強み」と「機会」は、受験生にとって最初に目に入る“書きやすい要素”です。
だからこそ、多くの答案で似通った表現が並びやすく、差がつきにくいポイントでもあります。
ここでは、典型的な失敗パターンを整理しておきましょう。
抽象的すぎる強みの表現
「強み:立地が良い」「強み:品質が高い」といった表現は、誰でも思いつく無難な書き方です。
しかし、採点者からすると「与件文を深く読まずに書いた答案」に見えてしまいます。
診断士試験は“与件文に書かれている情報を、診断士的な視点で翻訳して表現する”ことを求めています。
つまり「駅前に位置し、高齢者層が徒歩で来店しやすい」という具体性や、「地域の伝統製法を守る高品質」といった裏付けを添えてこそ、“他の答案と差がつく強み”になるのです。
使い古された機会の指摘
「機会:市場拡大」「機会:顧客層の増加」などの一言で終わらせてしまうのも、よくある失敗です。
確かに与件文には「高齢化」や「訪日外国人増加」といった社会背景が記されていますが、それをただ“写しただけ”では点は伸びません。
大切なのは「自社の強みとどう結びつくのか」という観点です。
例えば「訪日観光客の増加に対して、英語対応できるスタッフの接客力を活かせる」と書けば、“強みと機会を組み合わせた具体的提案”になります。
強みと機会をバラバラに書く
答案を読むと、「強み」と「機会」が単なる箇条書きになっており、両者がつながっていないケースが散見されます。
診断士試験では「戦略的な一貫性」を評価するため、両者が有機的に組み合わさっていないと加点が難しいのです。
強みと機会をバラバラに挙げるのではなく、「〇〇という強みを活かし、△△という市場機会に対応する」とワンセットで書くことが差別化につながります。

差がつく「強み」の書き方
事例Ⅱにおける「強み」は、単なるキーワードの列挙ではなく、“顧客にとってどのような価値をもたらすのか”を明確に示すことが重要です。
与件文を根拠にしながら、自社資源を具体化し、顧客ベネフィットに変換して書くことで、他の受験生と差をつける答案になります。
ここでは、その具体的なポイントを見ていきましょう。
与件文から「根拠」を拾う
強みを表現する際に欠かせないのが、与件文に書かれた事実を必ず根拠にすることです。
例えば「老舗である」という情報が与件にあった場合、そのまま「強み=老舗」と書いてしまうと弱い答案になります。
これを「地域住民に長年愛され、信頼関係を築いている」という形に変換すると、強みが顧客価値につながります。
つまり、“事実を拾い、顧客にとっての意味を付与する”のが差別化のコツです。
強みは「資源」から「価値」へ翻訳する
診断士的な答案では、内部資源(リソース)を顧客価値に変換する力が問われます。
例えば、
• 自社資源:熟練の技術者が多い
• 顧客価値:高品質の商品を安定的に供給できる
• 解答例:熟練技術者による高品質な製品づくりにより、地域顧客から信頼を獲得している
このように「資源 → 価値 → 答案」と段階を踏んで表現することで、与件文の事実を活かした説得力ある強みになります。
差別化につながる表現テクニック
他の受験生と同じ資源を拾っても、表現次第で差が生まれます。
• 「強み:立地が良い」ではなく → 「駅前に立地し、高齢者や観光客が徒歩でアクセスしやすい」
• 「強み:商品の品質が高い」ではなく → 「地域の伝統製法を活かした高品質商品で、地元客から高い評価を得ている」
このように、誰でも書ける表現を避け、“誰のためにどのように役立つか”を示すことが答案差別化のポイントです。
強みを「機会」とセットで活かす準備をする
最後に意識すべきは、強みは単独で完結しないということです。
事例Ⅱでは「強み×機会」を組み合わせることで加点が期待できます。
強みを書くときから、「この資源はどんな機会と結びつけられるか?」と先を見据えて整理しておくと、後の設問で一貫した答案を書きやすくなります。
差がつく「機会」の書き方
事例Ⅱで「機会」を問われると、多くの受験生は「市場拡大」「高齢化」「インバウンド需要」といった言葉を答案に並べがちです。
しかし、こうした表現は誰でも思いつくため、差別化が難しくなります。
合格答案に近づくためには、与件文の変化や兆しを拾い、強みとつなげて具体化することが重要です。
与件文の「変化」に注目する
機会を見抜く最大のポイントは、与件文に書かれた「外部環境の変化」に注目することです。
例:
• 「地元に新しい商業施設ができた」 → 新たな来店客層を取り込む機会
• 「若年層のSNS利用が増えている」 → デジタル発信を強化する機会
このように、単なる環境要因ではなく、自社の行動に直結する“変化”を拾うことで、答案にリアリティが生まれます。
顧客ニーズと結びつける
診断士試験では「顧客の立場で考える視点」が重視されます。
したがって、機会は必ず顧客のニーズ変化と関連付けて書くことが差別化の鍵です。
• 「健康志向の高まり」という一般的な表現ではなく
• 「健康志向の高まりを受け、低カロリー食品を求める顧客層に訴求できる」
と表現すれば、自社の戦略と直結した機会になります。
強みとセットで表現する
機会を単独で書くと凡庸になりがちです。
そこで、強みと組み合わせることで独自性を生み出すことが重要です。
• 強み:伝統的な製法で作る高品質な商品
• 機会:地域の観光客増加
• 答案例:「観光客増加という機会に対し、伝統的製法による高品質な商品を土産物として販売できる」
このように「強み×機会」のワンセットで書けば、答案全体が一貫し、評価が高まります。
機会は「広く」ではなく「絞って」書く
ありがちな失敗は、機会を多く並べすぎて焦点がぼやけることです。
診断士試験の答案は制限字数があるため、重要なのは「一点突破型の機会」を選ぶこと。
与件に書かれた変化のうち、自社の強みともっとも親和性の高いものを選び、深掘りして書くと差別化につながります。

解答プロセスの標準化で安定得点へ
事例Ⅱはマーケティング知識を問う科目ですが、単に知識を並べるだけでは得点にはつながりません。
重要なのは、答案を作成するプロセスを標準化し、どんな与件でも安定して強みと機会を拾えるようにすることです。
ここでは、合格者が実践する代表的な手順を整理します。
強み・機会マトリクスを作る習慣
試験本番で有効なのが、答案を書く前に「強み」と「機会」を縦横に整理したマトリクス表を簡単に作ることです。
• 縦軸:強み(与件から拾った内部資源)
• 横軸:機会(外部環境の変化・顧客ニーズ)
このマトリクスを使うと、「強みA × 機会X」「強みB × 機会Y」といった組み合わせが視覚的に確認できます。
その中から最も効果的なペアを答案に反映させれば、与件に沿った一貫性のある解答が書けるのです。
キーワード集で表現ブレを防ぐ
答案作成では「表現の一貫性」も大切です。
同じ内容でも「地域に根ざす信頼」と「老舗の強み」と書き方がバラバラだと、答案全体の説得力が弱まります。
普段の学習で自分なりのキーワード集を作っておき、過去問で繰り返し練習しておくと、本番でも迷わず書けます。
例えば「接客=顧客満足度向上」「立地=来店容易性」といった定型フレーズを持っておくと安心です。
設問解釈から逆算する
答案を安定させるためには、設問が何を問うているかを先に明確化し、それに沿って強みと機会を組み合わせることも欠かせません。
「販売戦略を問う設問」なら強みは「商品や人材」に焦点を当て、「販路拡大を問う設問」なら「立地や取引関係」に注目する、というように設問の意図から逆算して解答要素を選びましょう。
答案プロセスのルーティン化
最後におすすめなのは、答案作成をルーティン化することです。
1. 与件を読み、強みと機会を抜き出す
2. マトリクスで組み合わせを整理する
3. 設問の意図に沿って適切なペアを選ぶ
4. 自分のキーワード集を使い、文章化する
この流れを普段から徹底して練習しておくことで、本番の緊張下でも安定した答案が書けるようになります。
試験対策に役立つ書籍・参考資料
事例Ⅱでの「強み」と「機会」の抽出スキルを磨くには、ノウハウだけでなく、実際の学習を支える信頼性のある参考書・教材も有効です。
ここでは、マーケティング視点や解答プロセス強化に役立つ実在書籍を3点ご紹介します。
「スモールビジネス・マーケティング:小規模を強みに変えるマーケティング・プログラム」(岩崎邦彦 著)
中小企業診断士であり試験委員でもある岩崎邦彦氏による一冊。
消費者ニーズの多様化や高齢化、地産地消など現代のマーケ環境に即した戦略構築を解説し、小規模企業が持つ強みをマーケティング機会にいかに転換できるかを示しています。
事例Ⅱにおいて、「強み×機会」の具体的イメージを掴むのに最適です。
「ふぞろいな合格答案シリーズ」
二次試験対策の定番とされるこのシリーズは、事例Ⅱを含む各事例の合格答案だけでなく不合格答案も掲載されている点が特徴。
その差異からどこで差が生まれるのかを具体的に学べます。
自分の答案がどの水準にあるか客観視しつつ、本質的な答案力を養うのに最適な教材です。
「中小企業診断士試験2次試験 過去問題集」シリーズ(過去5年分掲載版)
過去5年分の二次試験問題と解答解説をまとめたこのシリーズは、事例Ⅱの頻出テーマや解答プロセスを学習する上で重要です。
解答作成の枠組みや思考ステップの習得に役立ち、安定得点の下地づくりに不可欠です。
活用のバランスと戦略的選定のすすめ
上記3冊にはそれぞれ特徴があります:
| 書籍名 | 特長 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| スモールビジネス・マーケティング | マーケの視点を中小企業に落とし込む理論書 | 強みと機会を結びつける洞察の強化素材として |
| ふぞろいな合格答案シリーズ | 合格・不合格答案の対比により答案差を見える化 | 合格答案の“質”を具体的に学ぶ |
| 過去問題集(5年分) | 出題傾向と解答プロセスの実践練習が可能 | 時間管理と型の習得に有効 |
どれか一冊に偏るのではなく、それぞれの強みをバランスよく使い分けることで、単なる知識の蓄積にとどまらない、「差がつく答案力」が備わります。

まとめ:強みと機会を“つなげて書く”ことで答案は差別化できる
事例Ⅱの答案で大きな差がつくポイントは、「強み」と「機会」を単独で書くのではなく、与件文を根拠にしながら両者を結びつけて具体的に表現することです。
この記事では、ありがちな失敗パターンを確認し、差別化につながる強みと機会の書き方、そして安定して答案を作成するためのプロセスを整理しました。
振り返ると、大切なのは次の3点に集約されます。
1. 与件文の事実を顧客価値に翻訳すること
「老舗=信頼」「立地が良い=高齢者が通いやすい」など、事実を顧客にとっての意味に変えることで、強みは答案の説得力を持ちます。
2. 外部環境の変化を機会として拾うこと
「市場拡大」といった一般的な表現ではなく、「SNS利用増加」「地域イベントの開催」といった具体的な変化を拾うことで、機会は自社の戦略に直結します。
3. 強みと機会をワンセットで書くこと
「伝統製法(強み)×観光客増加(機会)=土産需要を取り込む」など、両者を掛け合わせて答案化することで、戦略的一貫性を示すことができます。
さらに、答案を安定させるには、マトリクスによる整理やキーワード集の活用といったプロセスの標準化が効果的です。これらをルーティン化することで、どんな事例でも一定水準の答案が書ける“再現性”が生まれます。
中小企業診断士試験は、単なる暗記や知識披露ではなく、与件文から課題を抽出し、現実的な提案につなげる力を評価する試験です。
だからこそ、「強み×機会」という視点を意識した答案練習を繰り返すことが、合格への確実なステップになります。
シニア世代の受験生であれば、実務経験や生活者としての視点を答案に活かせる強みがあります。それを適切に表現できれば、大きなアドバンテージとなるでしょう。
本記事で紹介した考え方やプロセスを参考にしながら、ぜひ日々の過去問演習や答案練習に取り入れてください。
積み重ねの先に、“差がつく答案”を書ける自分が待っています。

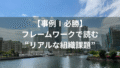

コメント