「計算問題が出ると、どうしても手が止まってしまう…。」
そんな経験はありませんか?
特に50代から診断士試験に挑戦する方の多くは、「公式を覚えられない」「計算が苦手」と悩みます。
ですが、安心してください。
損益分岐点やNPV、CVP分析は、理屈さえ理解してしまえば、公式を丸暗記しなくても解けるようになります。
本記事では、シニア層のあなたに向けて、これらの分析の本質と理屈をやさしく解説します。
計算が苦手でも解ける!損益分岐点分析の考え方とステップ
「公式を覚えるのが大変」「数字が並ぶと頭が真っ白になる」──診断士試験に挑戦するシニア層の方から、よくこんな声を耳にします。
ですが、損益分岐点分析は本質を理解すれば、実はとてもシンプルな仕組みです。
ここでは、公式を丸暗記せずに解けるようになるための、損益分岐点分析の考え方とステップをお伝えします。
そもそも損益分岐点とは?
損益分岐点とは、売上高と費用がちょうど釣り合い、利益がゼロになる売上の水準のこと。
つまり、この売上を超えれば黒字、下回れば赤字という「経営の分かれ目」です。
このとき重要なのは、費用が2種類に分かれるということです。
• 固定費:売上に関係なくかかる費用(家賃、人件費など)
• 変動費:売上に応じて増減する費用(材料費、外注費など)
固定費は、売上がゼロでも必ず発生するため、売上を積み重ねて固定費をカバーする、という発想が基本になります。
損益分岐点を求めるステップ
損益分岐点売上高は次のステップで求められます。
1. 限界利益率を求める
• 売上高から変動費を引いたものが限界利益。
• その限界利益を売上高で割ったものが「限界利益率」です。
• 限界利益率 = (売上高 − 変動費)÷ 売上高
2. 固定費を限界利益率で割る
• 損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ 限界利益率
これだけです。公式をそのまま覚えようとするよりも、
「固定費を限界利益で埋める」
というイメージで理解しておくと、数字の意味がつかめます。
計算に苦手意識がある人へ
まずは数字を当てはめてみることから始めましょう。
例えば、
• 売上高:1,000万円
• 変動費:600万円
• 固定費:300万円
この場合、
• 限界利益=1,000万円−600万円=400万円
• 限界利益率=400万円÷1,000万円=0.4
• 損益分岐点売上高=300万円÷0.4=750万円
となります。
「売上が750万円を超えると黒字になる」という意味です。
こうして意味を確認しながら数字を当てはめると、丸暗記しなくても自然に覚えられるでしょう。
NPV(正味現在価値)の出し方|診断士試験でのポイント
損益分岐点分析が「現状の損益の分かれ目」を求めるのに対して、NPV(正味現在価値)は、将来の投資判断に役立つ指標です。
こちらも公式を丸暗記するのではなく、「何を比べているのか」という理屈を理解しておくと、迷わず解けるようになります。
NPVとは?
NPVとは、将来得られるお金の現在価値の合計から、最初に投じるお金を引いたものです。
簡単に言えば、「将来のキャッシュフローを今の価値に直してみたとき、投資する価値があるか」を判断するもの。
NPVが
• プラスなら投資すべき
• マイナスなら見送るべき
というのが基本的な考え方です。
「なぜ将来のお金を今の価値に直すのか?」
ここが一番大事なポイントです。
将来のお金には「時間的価値」があるからです。
たとえば、今手元に100万円あれば、それを預けて利息をつけたり、別の投資で増やせたりします。
つまり、「今の100万円」と「5年後の100万円」は価値が違う、ということですね。
だからこそ、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引く計算をしてから比較するのです。
計算ステップ
NPVの計算は次のステップで行います。
1. 将来のキャッシュフローを求める
• 例えば、毎年100万円ずつ5年間もらえる場合。
2. 現在価値に割り引く
• 割引率(利率)が5%の場合、次の式で現在価値を計算します。
「将来のお金 ÷ (1+利率)^年数」
• 例)2年後の100万円の場合:
100万円 ÷ (1+0.05)^2 ≒ 90.7万円
3. すべての現在価値の合計から初期投資額を引く
• 合計がプラスなら投資すべき、という判断になります。
計算のコツ
診断士試験では、現在価値係数表(PV表)が与えられるケースが多いです。
これを使えば電卓での累乗計算が不要になるので、試験本番では必ず確認するクセをつけましょう。
また、現場では「将来価値係数表」と混同する人が多いので、名称と意味をしっかり押さえておくのがポイントです。
数字の意味と考え方がわかれば、NPVの問題も決して難しいものではありません。
「未来のお金の価値を今に換算して比べる」
──このイメージさえ持てば、計算はスムーズに進められるでしょう。
CVP分析の本質|限界利益がなぜ重要か
最後にご紹介するのが、CVP分析(Cost-Volume-Profit analysis)です。
これは、損益分岐点分析やNPVと並び、診断士試験・実務の両方でよく使われる考え方です。
CVP分析を理解するカギは、「限界利益」という指標がなぜ大切かを知ることにあります。
CVP分析とは?
CVP分析とは、日本語では「損益分岐点分析」とほぼ同義です。
ただし、損益分岐点を求めるだけでなく、売上やコストが変動したときに利益がどう変わるか、という視点まで広げるのが特徴です。
たとえば、
• 売上が10%増えたら利益は何%増える?
• 固定費を削減すると、損益分岐点はどう変わる?
こういったシミュレーションをするのがCVP分析です。
なぜ「限界利益」が重要なのか?
限界利益とは、売上高から変動費を引いた金額のことです。
この限界利益は、「売上が1円増えたときに、どれだけ利益が増えるか」を示す指標です。
ポイントは、固定費は売上が増えても基本的に変わらないという点。
だから、売上が増えるごとに限界利益が積み重なり、一定の固定費を超えた分がすべて利益になるのです。
逆に、限界利益率が低い(変動費が多い)ビジネスだと、売上が増えても利益が増えにくい、ということになります。
CVP分析の着眼点
CVP分析では、以下の3つを意識することが大切です。
1. 限界利益率が高いか低いか
• 高ければ固定費の回収が早く、利益が出やすい。
2. 固定費が大きすぎないか
• 固定費が大きいと、売上をかなり積まないと黒字にならない。
3. どの売上水準で黒字に転じるか
• 損益分岐点売上高を超えるかどうかが分かれ目。
これらを組み合わせて、売上目標やコスト構造の見直しを考えるのがCVP分析の本質です。
試験でのポイント
診断士試験では、「売上が○%増えたとき、利益がどうなるか?」というように、変化率を問われるパターンが多いです。
このときも限界利益率を理解していれば、落ち着いて答えられるでしょう。
限界利益率を暗記するのではなく、
「売上が増えると、固定費を超えた分が利益になる」
というイメージを持っておくことが大切です。
CVP分析もまた、単なる計算問題ではなく、経営の意思決定に直結する重要な分析です。
理屈がわかれば、数字の意味が見えてきて、計算が苦手な方でも自信を持って解けるようになるはずです。
理解が深まるおすすめ書籍
ここまで、損益分岐点・NPV・CVP分析の理屈や本質をご紹介してきました。
「なるほど、意味はわかったけど、もっと深く知りたい」
「練習問題もやりながら理解を定着させたい」
そんな方には、診断士試験対策に役立つ書籍の活用をおすすめします。
ここでは、理屈を重視しながら実践的な力も身につけたい方にぴったりの教材を3つご紹介します。
📘 1. 『中小企業診断士 最速合格のための第1次試験過去問題集 財務・会計』
試験対策で絶対に外せないのが過去問演習。
この過去問題集は、計算問題をただ解くだけでなく、なぜこの公式を使うのか、どのように考えるべきか、といった「背景の解説」が充実しているのが特徴です。
限界利益やNPV計算の典型問題パターンも網羅されています。
📘 2. 『中小企業診断士試験 過去問完全マスター 2 財務・会計(2025年版)』
試験対策において、過去問を徹底的にこなすことは王道かつ効果的な学習法です。
こちらの書籍は、過去5年〜10年分の財務・会計分野の過去問と、その詳しい解説が豊富に収録されています。
図表や別冊解説が充実しており、理屈を丁寧に理解しながら解ける構成になっていますので、丸暗記ではなく「なぜそう解くのか」を腑に落としながら演習を進められます。
📘 3. 『出る順中小企業診断士FOCUSテキスト 2 財務・会計(FOCUSシリーズ)』
こちらは、図表やイラストを多用し、項目別・論点順に整理されたテキストで、初学者にも優しい構成が魅力です。
過去問に直結する重要ポイントを、「出る順」で学べるため、学習の要点を見逃しません。
QRコードから過去問へのリンク解説もあり、理屈と演習を両立するスタイルに合います。
これらの教材を活用すれば、「なぜこうなるのか?」がより深く腑に落ち、計算問題に対する苦手意識がぐっと減るはずです。
ぜひ、自分に合ったスタイルで学びを続けてみてください。
まとめ|「理屈」がわかれば計算は怖くない
中小企業診断士試験の財務会計に出てくる、損益分岐点、NPV、CVP分析。
計算問題というだけで苦手意識を持つ方が多いのは事実です。
特に、50代からの学び直しで挑戦している方にとっては、「公式を丸暗記しなきゃいけない」と感じると、心が折れそうになりますよね。
ですが本記事でお伝えした通り、これらの分析は「なぜそう計算するのか」という理屈がわかれば、公式を無理に覚えなくても自然に身についていきます。
• 損益分岐点分析では、「固定費を限界利益で埋める」
• NPVでは、「未来のお金の価値を今に換算して比べる」
• CVP分析では、「限界利益が固定費を超えた分が利益になる」
こうしたイメージを持つだけで、数字の意味が腑に落ち、問題に取り組むハードルがぐっと下がるはずです。
加えて、書籍という学習ツールを活用することで、さらに理解を深め、自信をつけることもできます。
診断士試験の財務会計は、決して一握りの計算が得意な人のためだけの科目ではありません。
理屈から理解して積み上げていけば、どなたでも合格レベルに到達できます。
ぜひ、今日から「意味を理解する学び方」に切り替えて、前向きに進めてみてくださいね。

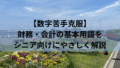

コメント