「毎回の模試で財務・会計の点数が安定しない…」そんな悩みを抱えていませんか?
苦手意識を克服するために、参考書を増やしたり過去問を繰り返したりしても、思うように成果が出ない。
実は、それはあなたの努力不足ではなく、“やり方”に原因があります。
診断士試験に合格した私が実践したのは、心理学的に理にかなった「習慣化ルーティン」です。
本記事では、シニア世代でも無理なく続けられ、得点が安定する復習法をお伝えします。
なぜ財務・会計は「習慣化」で差がつくのか
中小企業診断士試験の一次科目の中でも、とりわけ「財務・会計」は多くの受験生が苦手意識を持つ科目です。
計算問題は手が止まりやすく、理論問題は複雑で、一度理解したつもりでもしばらく経つと忘れてしまう…。
模試や過去問で毎回の得点が安定しないのは、決してあなただけではありません。
財務・会計が難しく感じる理由のひとつは、この科目が知識と計算処理の「定着度」を問う科目だからです。
つまり、一夜漬けで一時的に覚えても、時間が経てば忘れてしまう。そして試験本番では、知識が定着している受験生とそうでない受験生の差が顕著に表れます。
特に、50代以降の学び直し世代にとっては、学生時代のような短期記憶に頼る方法では限界があります。
記憶力の衰えを感じやすい年代だからこそ、無理なく続けられる「習慣化」で知識を定着させる戦略が有効なのです。
さらに心理学の研究によれば、人間の脳は繰り返し行うことで新しい回路を作り、長期記憶として定着する仕組みを持っています。
つまり、毎日少しずつの学習でも、適切なタイミングで繰り返す「ルーティン化」こそが、財務・会計の得点を安定させる近道なのです。
次の章では、この心理的メカニズムを具体的に解説しながら、ルーティン化がもたらす意外なメリットについて詳しくお伝えします。
得点を安定させる復習の心理的メカニズム
「習慣化」がなぜ財務・会計の得点を安定させるのか、その理由は心理学の理論にあります。
人間の記憶は、残念ながら一度覚えたら終わりではなく、時間とともに急速に薄れていきます。
有名なエビングハウスの忘却曲線によれば、学んだ知識の約半分は24時間以内に忘れてしまうと言われています。
しかし、適切なタイミングで繰り返し復習することで、記憶の定着度は飛躍的に向上します。
特に効果的なのが、「間隔反復(スパイシング)」と呼ばれる方法です。
これは、復習する間隔を少しずつ伸ばしながら繰り返すことで、長期記憶に移行しやすくなるという理論です。
例えば、学んだ当日に復習し、翌日もう一度、3日後、1週間後…と繰り返すことで、脳が「重要な情報」として記憶を強化します。
また、習慣化にはメンタル面でのメリットもあります。
「今日はやるべきかどうか」を毎日判断するのは意外と負担が大きいものです。
しかし、ルーティンとして決まった時間や場所で復習する習慣をつけると、意思決定の負担が減り、継続しやすくなるのです。
こうした心理的メカニズムをうまく活用することで、学習の効率が高まるだけでなく、試験本番での得点が安定する状態を作ることが可能になります。
次の章では、実際に私が診断士試験で取り入れていた具体的な「習慣化ルーティン」の例をご紹介します。
診断士が実践する習慣化ルーティン例
ここからは、私自身が中小企業診断士試験の財務・会計で実践し、得点を安定させるのに役立った具体的なルーティンを紹介します。
ポイントは「無理なく毎日続けられること」と「心理学的に効果のある間隔反復」を組み合わせることです。
朝5分の計算ドリル法
1つ目は、朝の時間を活用する方法です。
人間の脳は起床後がもっともクリアで記憶の定着率が高い時間帯。
そこで私は、毎朝5分だけ、前日に間違えた計算問題を解き直す習慣をつけました。
ポイントは、短時間で終えられるように問題を絞ることです。
例えば、前日に解いた10問のうち、間違えた2〜3問だけを朝に再確認する。
これを毎朝続けることで、自然と苦手パターンが克服され、安定した得点力につながりました。
週末の弱点ノート見直し法
2つ目は、週末にまとめて振り返る習慣です。
平日に解いた問題や気づいたことを「弱点ノート」に書き溜めておき、週末に30分ほどかけて見直します。
このとき、同じ問題を再度解くのではなく、理論の流れや数字の意味を確認する「読み返し中心」で行うのがコツです。
これにより、全体の流れや数字の意味づけが頭の中で整理され、計算ミスや暗記漏れを防げるようになります。
小さく続けることが最大のコツ
ここで大切なのは、「習慣化すること」を最優先にする点です。
最初から完璧を目指す必要はありません。
むしろ、ハードルの低い小さな行動を毎日積み重ねることで、気づけば試験本番で安定した得点力が身についています。
次の章では、こうしたルーティンをより楽に、効率的にするためのおすすめ学習ツールやグッズをご紹介します。
おすすめ学習ツール・グッズ
習慣化を成功させるためには、心理学の知見を活かした「仕組み」と、学習をサポートしてくれる便利なツールを活用するのがおすすめです。
ここでは、私が実際に試して効果を感じた学習ツールやグッズを紹介します。
計算ドリル書籍のおすすめ
短時間で繰り返し練習するためには、薄くて基礎問題が中心の計算ドリルが便利です。
一問一答形式で解けるものを選ぶと、朝のルーティンにもピッタリ。
例えば、Amazonなどで手に入る以下のような書籍が特におすすめです。
• 『中小企業診断士 最速合格のための第1次試験過去問題集 財務・会計』(TAC出版)
→ 過去問ベースで問題が厳選されており、出題傾向の確認にも最適です。
• 『スピード問題集 財務・会計』(TAC出版)
→ 短い時間で基礎固めができる一冊。持ち歩きやすいサイズ感も◎。
これらは当ブログのAmazonリンクから購入も可能ですので、ぜひチェックしてみてください。
習慣化を助けるタイマー・アプリ
ルーティン化の強力な味方が、「時間を区切る仕組み」です。
学習時間を可視化することで、ダラダラ学習を防ぎ、集中力が高まります。
おすすめは、ポモドーロ・テクニックに対応した学習タイマーやアプリ。
以下のようなものがあります。
• 学習用デジタルタイマー
→ 25分/5分のポモドーロ設定が簡単にできるモデルが便利です。
(Amazonで「学習タイマー ポモドーロ」で検索すると多数ヒットします)
• スマホアプリ「Focus To-Do」
→ 無料で使えるポモドーロアプリ。学習記録も残せます。
これらを組み合わせると、学習のリズムが整いやすくなり、無理なく続けられる環境が整います。
心理学のメカニズムとツールの力を借りることで、習慣化はぐっとやりやすくなります。
最後に、本記事のまとめと、これから取り組む方へのメッセージをお伝えします。
まとめ|習慣化で財務・会計の安定得点を実現しよう
中小企業診断士試験の財務・会計は、苦手意識を持つ受験生が多い科目です。
しかし、心理学的に理にかなった「習慣化」という武器を手にすれば、誰でも安定した得点を目指すことができます。
今回ご紹介したように、ポイントは次の3つです。
• 毎日のルーティンに組み込み、知識の定着を促す
• 間隔をあけた反復で、長期記憶に残す
• 無理なく続けられる仕組みとツールを活用する
これらを意識して、まずは朝5分の計算ドリルからでも構いません。
小さく続けることが、やがて大きな成果につながります。
シニア世代の学び直しは、若いころのように時間や記憶力に頼るのではなく、仕組みや習慣の力で効率よく進めるのがコツです。
私自身もこの方法で財務・会計の苦手を克服し、合格をつかみました。
ぜひ、今日からあなたも自分なりの習慣化ルーティンを作り、安定した得点を目指してみてください。
そして、このブログでは引き続き、学び直しに役立つ情報やおすすめツールも紹介していきますので、ぜひブックマークして定期的にチェックしてくださいね。
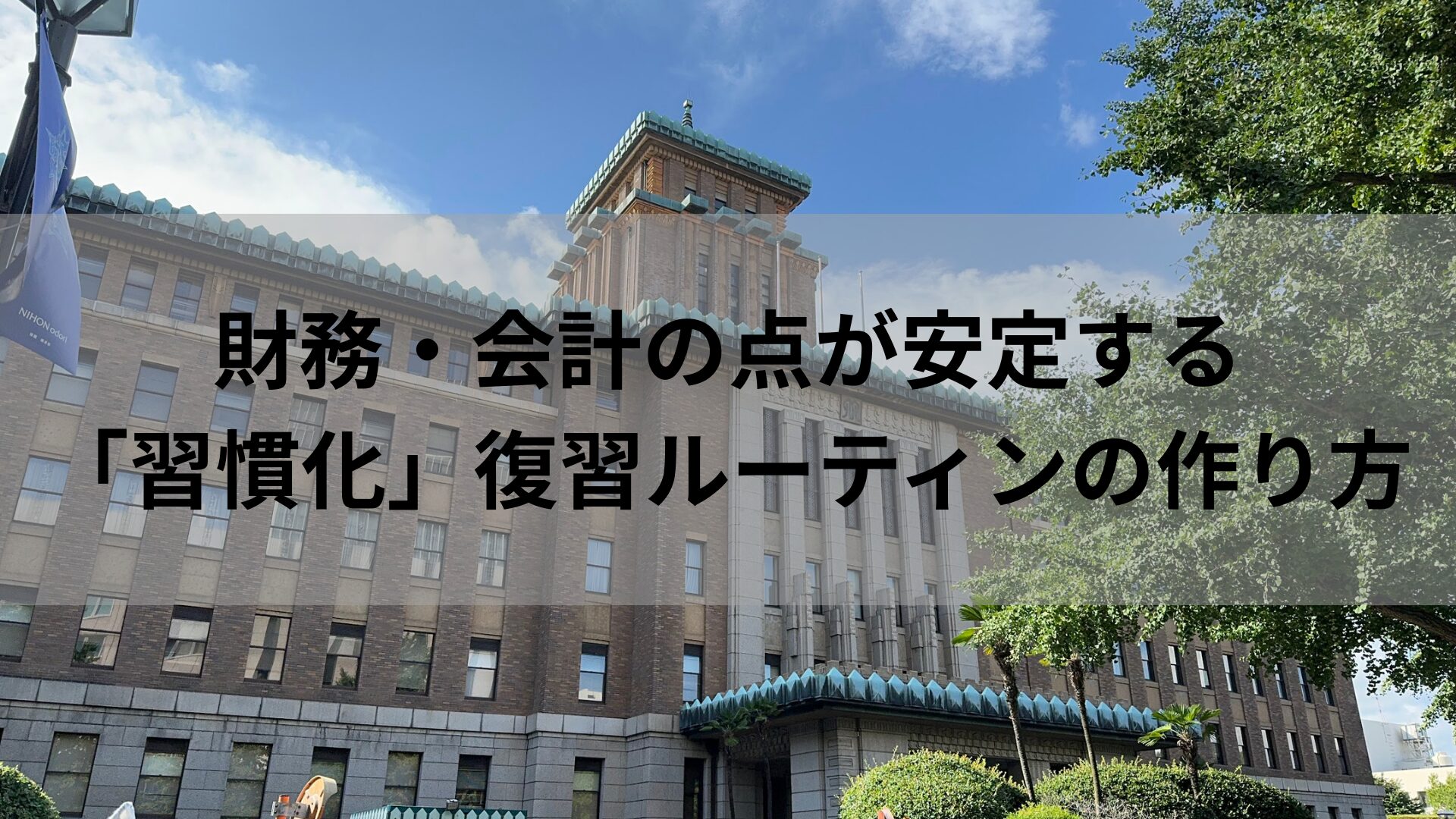

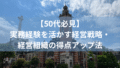
コメント