私が中小企業診断士の資格を取るために選んだ道として登録養成課程に進んだことは、さまざまな意味で有意義なことであり、すぐに診断士として実践するのに最適な道であると自負しております。
この記事では、私がどのようにして登録養成課程を選び、どのようにしてその課程を進み、そしてどのようにして診断を実践したのかを書き綴ってみたいと思います。
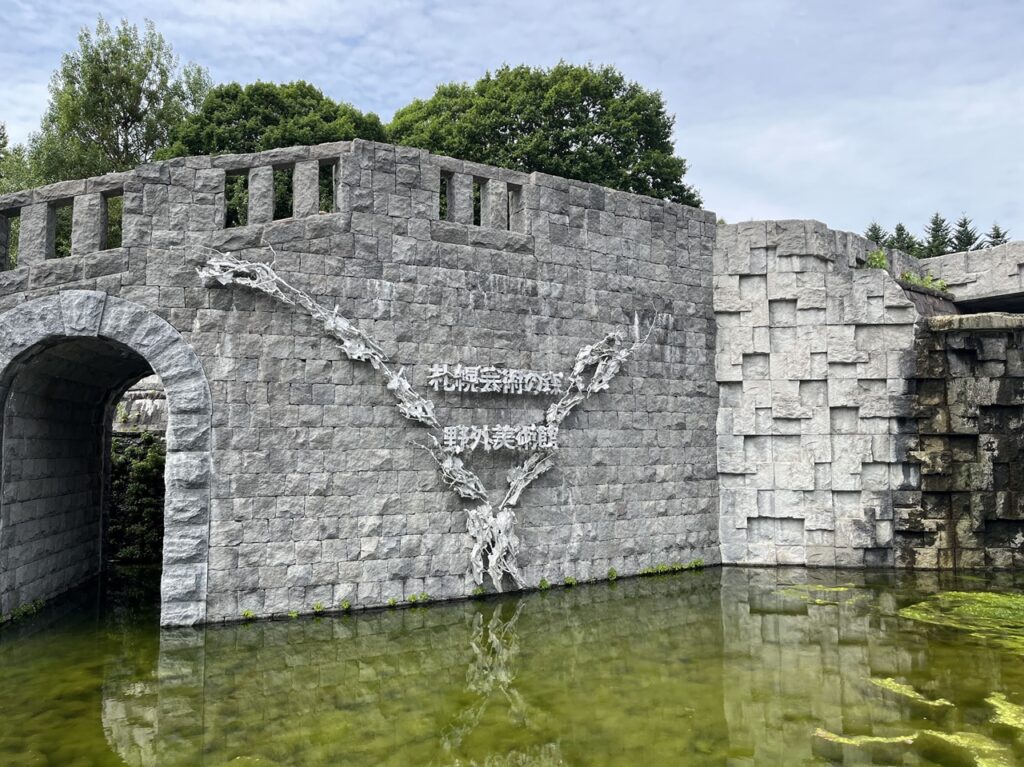
2次試験での失敗が契機
登録養成課程は、診断士1次試験が合格したあと、2次試験を経ないで診断士になる道であることは、もうすでにご存知の方も多いかと思います。
これはつまり、2次試験そのものが苦手、または2次試験の特定の事例が苦手で、2次試験に合格できなかった場合の、診断士になるためのもう一つの選択肢と言えるでしょう。
私も2次試験での失敗が契機となって、登録養成課程に進んだわけですが、その理由は別の記事にも書いたとおり、すでに税理士資格があったため、財務・会計の1次試験免除を選んだため、その試験勉強を十分にしてこなかったことが大きな理由ではあります。
つまり、2次試験での事例Ⅳが足枷となって、2回の試験を満足な結果が得られなかったのです。
そのため、定年間近であったということもあり、是が非でも資格を取るためには登録養成課程に進むことが必須と考えました。
登録養成課程に進むための試練
私は、唯一民間企業が主催する「日本マンパワー」の登録養成課程を選びました。
その理由は、当時勤めていた会社からの通学がしやすかったからでした。
登録養成課程は1年間通わなくてはならないため、当然ながら無理なく通えることが前提となるわけです。
また、資金面での問題もありましたが、幸か不幸か、入学する前年末に父が亡くなり、相続によって資金の手立てができました。
そして、登録養成課程に進むためには、それを主催する機関の「入学試験」に受かる必要があります。
これは意外と見落とされがちなことかもしれません。
日本マンバワーでは診断士試験講座もあったので、そこで使われているテキストや問題集を早速入手し、短期間ながら試験勉強を行なってどうにか合格することができました。
このように、登録養成課程でのさまざまな試練を乗り越えて、この先1年間の受講生活が始まったのです。

カリキュラムに従って進んでいく
日本マンパワーの登録養成課程は、3月下旬の開講から翌年3月下旬の修了までの1年間、神田にあるセミナールームに通うことになります。
始まって数ヶ月は座学がほとんどですが、ところどころグループ討議による演習を行い、グループのメンバーが変わる変わる演習結果の発表をしていきます。
行う内容は2次試験の4つの事例をさまざまな観点から細分化したもので、中には助言能力を養う科目もあり、実践を踏まえた上でのカリキュラム設計がなされています。
そして、座学も3ヶ月を過ぎた7月中旬に最初の診断実習が始まります。
診断実習は1年で5回、1グループ6人ほどのグループに分かれて行われ、それぞれグループごとに実際にある民間企業に伺って、3週間ほどかけて総合的な経営診断を行います。
そして、グループ討議を何度も重ねて診断結果をパワーポイントにまとめ、実習の最終日にその企業の代表者である社長を前に発表する流れとなります。
5つの診断実習は診断士実務への第一歩
日本マンパワーの登録養成課程での診断実習は、次のカリキュラムで進められます。
1回目(7月中旬〜):製造業診断実習
2回目(9月下旬〜):流通業診断実習
3回目(11月中旬〜):戦略策定実習(製造)
4回目(1月上旬〜):戦略策定実習(流通・サービス)
5回目(2月中旬〜):総合ソリューション実習
各グループにはそれぞれ担当講師が割り当てられ、その講師の助言により診断実習が進められます。
また、グループにはそのまとめ役としてリーダー、サブリーダーをメンバー持ち回りで担当することになります。
各メンバーは、必ず1回はリーダーまたはサブリーダーにならなければならず、それは診断士試験で学習した「リーダーシップ」を実践の中で身につけることになることから、その後の診断実務に活かされていくわけです。
登録養成課程の醍醐味というのは、まさに診断実習を行うことにより成り立っていると言うことができ、この課程を経験し実践していくことで、診断士としての実務の何たるかを体験ことになります。

中小企業診断士養成課程・演習・実習基準(中小企業基盤整備機構 資料)より
診断実習は実際にどのように進められるか
診断実習では、各メンバーがそれぞれの分野を担当して進めていきます。
具体的にはリーダーは全体のまとめ役に、サブリーダーはリーダーの補佐をしながら一つの分野の担当も行い、そのほかのメンバーも、それこそ2次試験の4つの事例に分けて診断をしていくのです。
診断は単にその会社の様々な状況を当事者などから聞くだけでなく、時には自ら実験することで1次資料を得ることが必要になる場合もあります。
例えば製造業であれば、作業効率がどのようになっているかを実際の作業の流れから時間を測るなどしてサンプリングをします。
また、流通業であれば、店舗の立地状況から特定の時間における人の流れや回遊傾向などを実際にモニタリングをします。
そのようにして、あらゆる観点から資料を収集し、それを分析し検証していくことにより、その先の改善するための課題が見えてくるのです。
そして、それを診断先にわかりやすくプレゼンテーションすることにより、経営改善に役立ててもらうことが、診断士の最終目的となります。

診断士資格の取得は独立への道しるべ
診断士試験は単なる資格取得にとどまらず、試験を通して真の経営コンサルタントになるための課程といえるでしょう。
それは、その先に経営の専門家として活躍していく道を切り開くための様々なスキルを身につけることができる、「専門家養成ギブス」ともいうべき効果を持つものです。
その意味では、単に企業内診断士としているよりも、さまざまな業種の経営を支える独立診断士として活躍する方が、診断士制度の主旨に見合っていると言えるかもしれません。
この記事をきっかけに、診断士の魅力を享受し、診断士を目指すきっかけになればうれしく思います。
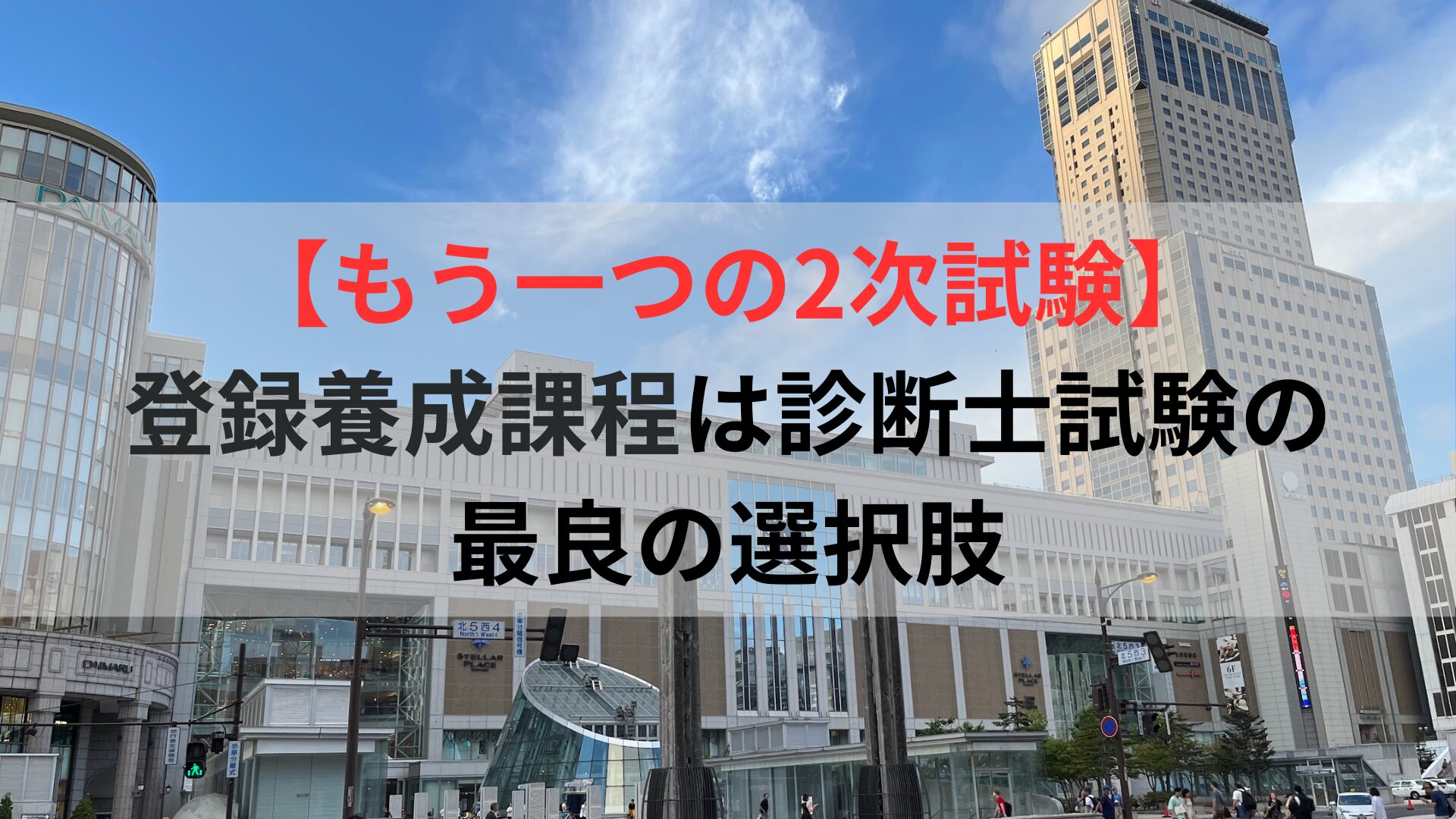


コメント