中小企業診断士2次試験の最大の難関のひとつが「与件文の読み方」です。
「読むのが遅くて解答時間が足りない」「速読すると内容が頭に残らない」と悩む受験生は少なくありません。
試験本番では、与件文を効率よく読み解き、設問に直結する情報を瞬時に拾う力が合否を分けます。
本記事では、診断士の実務経験に基づいた与件文読解のコツを解説し、読解スピードを落とさず正確に理解するための方法を紹介します。
与件文は「速読」ではなく「精読の高速化」
中小企業診断士2次試験の与件文は、ビジネスの現場を想定した長文ケーススタディです。
文字数は4,000字前後に及び、限られた80分の中で読み切るだけでも大きな負担となります。
ここで多くの受験生が陥るのが「速読=正解」と誤解してしまうことです。
実際の試験で求められるのは、単に速く読むことではなく、設問に直結する情報を効率よく抽出する“精読の高速化”です。
文章を丸ごと頭に入れようとすれば時間が足りず、逆に表面的に読み飛ばせば出題者の意図を見落とすリスクが高まります。
診断士の実務でも、経営者からのヒアリングや決算書、調査レポートを短時間で読み取り、重要な論点を整理する力が必要です。
つまり、「精読の高速化」は試験だけでなく、実務につながる本質的なスキルでもあります。
ポイントは、与件文を全体から細部へと段階的に読むことです。
まず段落構成や登場人物を把握し、次に設問との関連を意識しながら情報を拾っていく。
こうした手順を意識することで、ただの速読ではなく「必要な部分を的確に、しかも速く」読むことが可能になります。

設問解釈と与件読解の同時進行法
与件文の読解スピードを上げるために最も効果的なアプローチが、設問解釈と読解を切り離さず、同時進行で行うことです。
多くの受験生は「まず与件文をすべて読む→次に設問に取りかかる」という流れを取りますが、この方法では読み直しが増え、貴重な試験時間を浪費してしまいます。
診断士試験の2次問題は、「設問が問いたい内容」と「与件文に書かれている事実」が必ず対応しています。
つまり、先に設問を読み、キーワードや論点を把握してから与件文に進むことで、必要な情報をアンテナ高く拾えるようになります。
例えば「今後の成長戦略を助言せよ」という設問があれば、与件文を読む際に「強み」「制約条件」「競合環境」といった要素を優先的に探す視点が働きます。
逆に設問を確認せずに与件文に入ると、あらゆる情報を均等に追ってしまい、結果としてスピードも精度も落ちてしまうのです。
実務でも、コンサルタントが経営者へヒアリングを行う際には「今日の面談の目的(例:資金繰り改善、販路拡大)」を意識しながら話を聞きます。
試験の与件文読解も同様に、目的意識を持った読解がスピードと正確性を同時に高めるカギとなります。
次章では、こうした「設問とリンクした読解」を支えるために有効な、出題者の意図を読む行間読解のポイントについて解説していきます。
出題者の意図を読む「行間読解」
与件文を速く、かつ正確に読み解くためには、単なる事実の拾い読みだけでなく、出題者の意図を感じ取る「行間読解」が欠かせません。
診断士試験では、文章の中にヒントや制約条件が巧みに埋め込まれており、それを見抜けるかどうかで解答の質が大きく変わります。
特に注意すべきは以下の3点です。
• 強調表現
「しかし」「一方で」「特に」「最大の」などの語句は、出題者が着目してほしいシグナルです。
これらを見落とすと、問題の核心を外した解答になりがちです。
• 制約条件
「資金が限られている」「人材が不足している」といった表現は、答案作成の方向性を決定づける要素です。
ここを無視すると、実現性を欠いた回答となり減点されてしまいます。
• 因果関係
「〜のため」「その結果」といった接続表現は、課題と解決策をつなぐ筋道を示しています。
設問の答えを組み立てる“論理の骨格”として活用できます。
このように、与件文はただの背景説明ではなく、「どう答えてほしいか」という出題者のメッセージが随所に散りばめられているのです。
診断士の実務においても、経営者が本音を直接口にせず、遠回しな言葉や強調のニュアンスに解決の糸口が隠される場面は少なくありません。
試験の与件文も、それと同じ姿勢で読み解くことが求められます。
次章では、この「行間読解」で拾った要素を整理する具体的な方法として、キーワードマーキングの型について解説していきます。

誤読を防ぐキーワードマーキングの型
与件文を速く読んでも、内容を誤って理解してしまえば解答の精度は大きく落ちてしまいます。
そこで有効なのが、一貫したルールで行うキーワードマーキングです。
自己流で線を引きすぎると、かえって情報が整理できず混乱することもあるため、シンプルな「型」を持つことがポイントです。
診断士受験生におすすめしたいのは、以下の3分類によるマーキングです。
• 数字やデータ
売上、従業員数、市場シェアなど。解答の根拠となる客観情報。
• 因果関係
「〜のため」「その結果」「一方で」など。課題と解決策を結びつける論理の流れ。
• 制約条件や強調表現
「資金が限られている」「特に問題なのは」など。答案の方向性を決める要素。
この3分類を決めた色や記号でマーキングしておけば、解答作成時に必要な情報を瞬時に引き出すことができます。
例えば「数字=青」「制約条件=赤」「因果関係=下線」といった具合にルール化しておくと、読み返す時間を大幅に削減できるのです。
診断士の実務でも、報告書やヒアリングメモを整理するときに、数字・課題・制約を明確に区別して記録することは基本中の基本です。
つまり、試験でのマーキング習慣は、合格後の実務スキルにも直結するのです。
次章では、このマーキングをさらに活かすための学習法として、診断士が推奨する学習リソースやトレーニング方法をご紹介します。
診断士が推奨する学習リソース
与件文の読み方は「知識として理解する」だけでは定着しません。
実際に手を動かし、繰り返しトレーニングすることで初めて本番で活用できる力になります。
その際に役立つのが、診断士合格者が活用してきた定番リソースです。
1. 過去問題集の徹底活用
過去問は最も信頼できる教材です。
少なくとも直近5年分を繰り返し解くことで、設問と与件文の対応関係や、出題者が好む表現パターンが自然と身につきます。
特に「段落ごとに要約して設問と結びつける」訓練をすると、読解スピードが大きく向上します。
👉 Amazonで購入できる『中小企業診断士 第2次試験過去問題集』シリーズは定番の一冊です。
2. 解法プロセスに特化した参考書
単なる知識ではなく「どう読むか」「どう答えるか」に特化した参考書を使うと、与件文の読解手順が体系的に整理できます。
👉 『ふぞろいな合格答案』シリーズは、実際の再現答案をもとに解答プロセスを学べる人気教材です。
3. オンライン講座・演習会の活用
独学では気づきにくい「読み飛ばしの癖」や「設問解釈のズレ」を矯正するには、オンライン講座や演習会の利用も効果的です。
診断士スクール各社が提供する模擬演習やZoom添削指導は、客観的なフィードバックを得られる貴重な機会となります。

まとめ
中小企業診断士2次試験における与件文の読み方は、単なる速読ではなく、「設問とリンクさせた精読の高速化」が合格へのカギです。
設問先読み、行間読解、マーキングの型、そして日々のトレーニングを積み重ねることで、読解スピードと正確性は確実に磨かれます。
さらに、過去問や参考書、オンライン講座といった学習リソースを活用すれば、効率的にスキルを定着させることが可能です。
与件文を制することは、試験合格のみならず、診断士として実務で活躍するための第一歩となるでしょう。


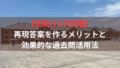
コメント