中小企業診断士試験の事例Ⅲ(生産)は、与件文をどう「課題」に落とし込むかが合否を分けます。
「問題点と課題を混同してしまう」「設問に合った表現ができない」と悩んだ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、診断士的な思考プロセスを“型”として整理し、失点を防ぐ課題分析トレーニングの方法を解説します。
シニア世代の学び直しにも応用できる、再現性の高いアプローチを一緒に身につけていきましょう。
事例Ⅲで問われる「課題分析」とは何か
事例Ⅲ(生産)で最も重視されるのが「課題分析」です。
与件文を読んで、企業が抱える問題点を的確に整理し、設問に沿った形で表現できるかどうかが、得点の分かれ目になります。
一見すると単なる「問題探し」に思えるかもしれませんが、診断士試験における課題分析はもっと奥が深いものです。
ポイントは 「与件文の事実を根拠に、改善余地のある論点を抽出すること」にあります。
つまり、単なる事象の列挙ではなく、経営資源や生産プロセスとの関係性を踏まえた論理的整理が求められるのです。
たとえば、以下のような違いがあります。
• 問題点の指摘にとどまる場合
「在庫が多い」「納期遅れが発生している」
→ 単なる現象の羅列であり、これだけでは減点対象となる可能性が高い。
• 課題として整理できている場合
「生産計画と現場の実行管理が不十分なため、在庫過多や納期遅延が発生している」
→ 原因と結果のつながりが示され、改善すべき方向性が明確。
このように「課題」として記述することで、答案全体が設問要求に即した筋道の通った内容になります。
また、事例Ⅲにおける課題分析は、他の事例科目(ⅠやⅡ)と比べて 現場の“モノづくり”プロセスに直結 している点も特徴です。
工程設計、作業管理、品質管理など、生産マネジメントの要素を踏まえて記述することで、得点が安定して伸びやすくなります。
要するに、課題分析とは 「事実をもとに、経営資源や生産プロセスと結びつけながら、改善すべき論点を論理的に整理する作業」なのです。
この視点を持つことで、答案の質が大きく変わり、失点を防ぐ大きな武器となります。

課題分析で失点しやすい典型パターン
事例Ⅲの課題分析では、「わかったつもり」で答案を書いても、得点に結びつかないケースが少なくありません。
特に以下のような典型パターンは、多くの受験生が陥りがちです。
自分の答案に当てはまっていないか、確認してみましょう。
問題点と課題を混同してしまう
最も多い失点パターンは、「問題点」と「課題」を区別できていないケースです。
例えば「機械が老朽化している」というのは単なる事実(問題点)ですが、これをそのまま答案に書くと減点対象になりがちです。
診断士試験では「だから改善すべきなのは何か?」を問われています。
正しくは「機械の老朽化により生産効率が低下しているため、設備更新や保全体制の強化が課題となる」と記述する必要があります。
設問の要求から外れてしまう
課題を的確に抽出していても、設問の要求とズレてしまうと得点は伸びません。
「今後の生産体制の改善策を問う問題」に対して、「人事評価制度の課題」を書いてしまうのは典型的な例です。
与件文に書かれているからといって、設問に関係の薄い課題を答案に盛り込むと、部分点すらもらえないことがあります。
課題の粒度がバラバラになる
答案に書く課題が、「抽象的すぎるもの」と「具体的すぎるもの」で混在しているケースも失点につながります。
たとえば「経営管理体制の不備」と「在庫棚卸ルールがない」という課題を並列で書いてしまうと、答案全体の一貫性が失われます。
診断士試験では、課題の粒度をある程度そろえ、論理的に並べることが大切です。
経験や常識に引っ張られてしまう
特にシニア受験生に多いのが、自身の業務経験や常識に引っ張られて答案を書いてしまうケースです。
「現場ではこうしていたから」という実務感覚は武器になる一方で、与件文に根拠がない記述は減点対象です。
大切なのは「与件文に書かれた事実に基づく」こと。経験は補助的に活かす程度に留めるのが安全です。
これらの典型パターンを知っておくだけでも、失点を大幅に減らすことができます。
次のステップでは、こうした失敗を避けるために有効な「課題分析の型」をご紹介します。
再現性を高める“型”の活用法
課題分析で安定した得点を確保するには、思いつきや経験に頼らず、「型」 に沿って答案を組み立てることが欠かせません。
診断士試験は60点を安定して取ることが合格のカギであり、そのためには再現性のあるプロセスを身につける必要があります。
課題分析の基本プロセス(型)
事例Ⅲで有効とされる課題分析の型は、次の3ステップに整理できます。
1. 現状把握(与件文の事実を整理)
与件文から生産現場の事実を抜き出す。
例:「受注量に対して在庫が多い」「納期遅れが頻発している」。
2. 課題抽出(原因と影響を結びつける)
問題点の背景にある原因を特定し、それが企業に与える影響を考える。
例:「生産計画が現場と連動していないため、在庫過多や納期遅延を引き起こしている」。
3. 解決方向性の提示(設問の要求に合わせる)
抽出した課題を、設問の趣旨に沿った形でまとめる。
例:「生産計画と現場実行管理の連携強化が課題」。
この流れを答案に落とし込むことで、課題が「事実に基づき、原因と影響が明示された一貫性のある内容」になります。
演習で使える“課題フレーズ集”
課題分析を効率的にトレーニングするには、あらかじめ使えるフレーズを準備しておくのも有効です。
例えば:
• 「〜が不十分であるため、〜が課題となっている」
• 「〜の仕組みが未整備で、〜に影響を与えている」
• 「〜の老朽化により、〜の改善が求められる」
このような定型文を活用すれば、答案作成時に迷わず書き出せるため、制限時間内での安定感が増します。
型を定着させるポイント
単に型を知るだけでは不十分で、実際に「過去問や演習で繰り返す」ことが重要です。
ポイントは以下の通りです。
• 毎回の答案で必ず「現状 → 課題 → 解決方向性」の流れをチェックする
• 書き終えた答案を見直し、課題が事実に基づいているか検証する
• 型を意識した添削を受けることで弱点を補強する
型を意識した学習を継続することで、課題分析力は自然と安定し、「ぶれない答案」を書けるようになります。

効果的なトレーニング方法
課題分析を得点源に変えるには、「知識を知っている」段階から「実際に書ける」段階へ進むことが不可欠です。
ここでは、日々の学習に取り入れやすい具体的なトレーニング方法を紹介します。
過去問を「課題抽出」だけで解いてみる
いきなり答案全文を書こうとすると時間がかかり、思考も散漫になりがちです。
まずは過去問を使い、課題抽出だけを行う練習 から始めましょう。与件文を読んだら、設問ごとに「課題は何か?」を一文で書き出す練習を繰り返します。
このトレーニングにより、与件文から課題を拾い上げる感覚が磨かれ、答案の土台が安定していきます。
制限時間を意識したアウトプット練習
課題分析は「考える力」と同時に「書くスピード」も重要です。
特にシニア受験生は、文章をまとめるのに時間がかかる傾向があるため、制限時間を設けて課題を短文で書き出す練習を取り入れましょう。
例えば「10分で課題を3つ挙げる」といった短時間演習を繰り返すと、本試験での時間配分に強くなります。
学習ノートの活用法
課題分析の力を定着させるには、演習結果を整理するノートを作るのがおすすめです。
• 与件文の引用部分
• 抽出した課題
• 改善の方向性
これらを一目で確認できるようにまとめておくと、自分の弱点が可視化されます。
さらに、過去問を年度ごとに整理しておけば、出題パターンの理解も深まり、試験直前の復習にも役立ちます。
学習仲間や添削サービスの活用
独学で答案を書き続けても、自分では気づかないクセが残ることがあります。
可能であれば、学習仲間との答案交換や、専門の添削サービス を利用してフィードバックを受けましょう。
他人の視点から見てもらうことで、「課題の粒度が揃っていない」「与件文の根拠が弱い」といった改善点に気づきやすくなります。

まとめとおすすめ学習ツール(書籍・講座紹介)
ここまで、事例Ⅲで失点しないための課題分析プロセス(“型”)と、それを定着させるトレーニング方法をご紹介してきました。
最後に、学習効果をさらに高めるための おすすめ教材と講座 を、実際に販売・提供されているものの中から、特に信頼性と実績のあるものとしてセレクトしました。
書籍:事例Ⅲ対策におすすめの3冊
「ふぞろい な答案分析 7: 中小企業診断士2次試験」
過去の受験答案を多数収録し、採点視点での文章構成や答案骨子の傾向を学べるシリーズ。
事例Ⅲの課題分析力・答案構成力を高めたい方にぴったりです。
「みんなが欲しかった! 中小企業診断士の教科書 (上) 2025年度版」
図解や補足が豊富な定番テキスト。
基礎からしっかり理解したい方に適しており、現場感を交えた具体的解説で事例Ⅲの内容理解が深まります。
「みんなが欲しかった! 中小企業診断士 合格へのはじめの一歩 2026年度版」
これから学習を始める方に最適なガイドブック。
試験全体の流れや学習プランを俯瞰でき、事例Ⅲ対策への無理のないスタートになります。
書籍:理解を深めるための補助教材
『ザ・ゴール コミック版』
制約理論(制約 bottleneck)をわかりやすい物語として学べる名著。
生産現場における本質的な課題抽出や改善手法を直観的に理解でき、事例Ⅲの課題分析にも応用しやすくなります。
講座:オンライン学習で効率アップ
アガルート中小企業診断士講座(事例Ⅲ対策含む)
設問理解、SWOT分析のスピード化、戦略・戦術判断など、実戦的なテクニックに重点を置いた講座が提供されています。
無料体験もあるため、講師の教え方や教材との相性を確認するのにも最適です。
本記事の内容を活用すれば、「事例Ⅲにおける課題分析」という得点源を、診断士思考の“型”として自分のものにできるはずです。
ぜひ、上記の教材とトレーニング方法を組み合わせて実践し、まずは失点しない安定した答案力を築き上げてください。
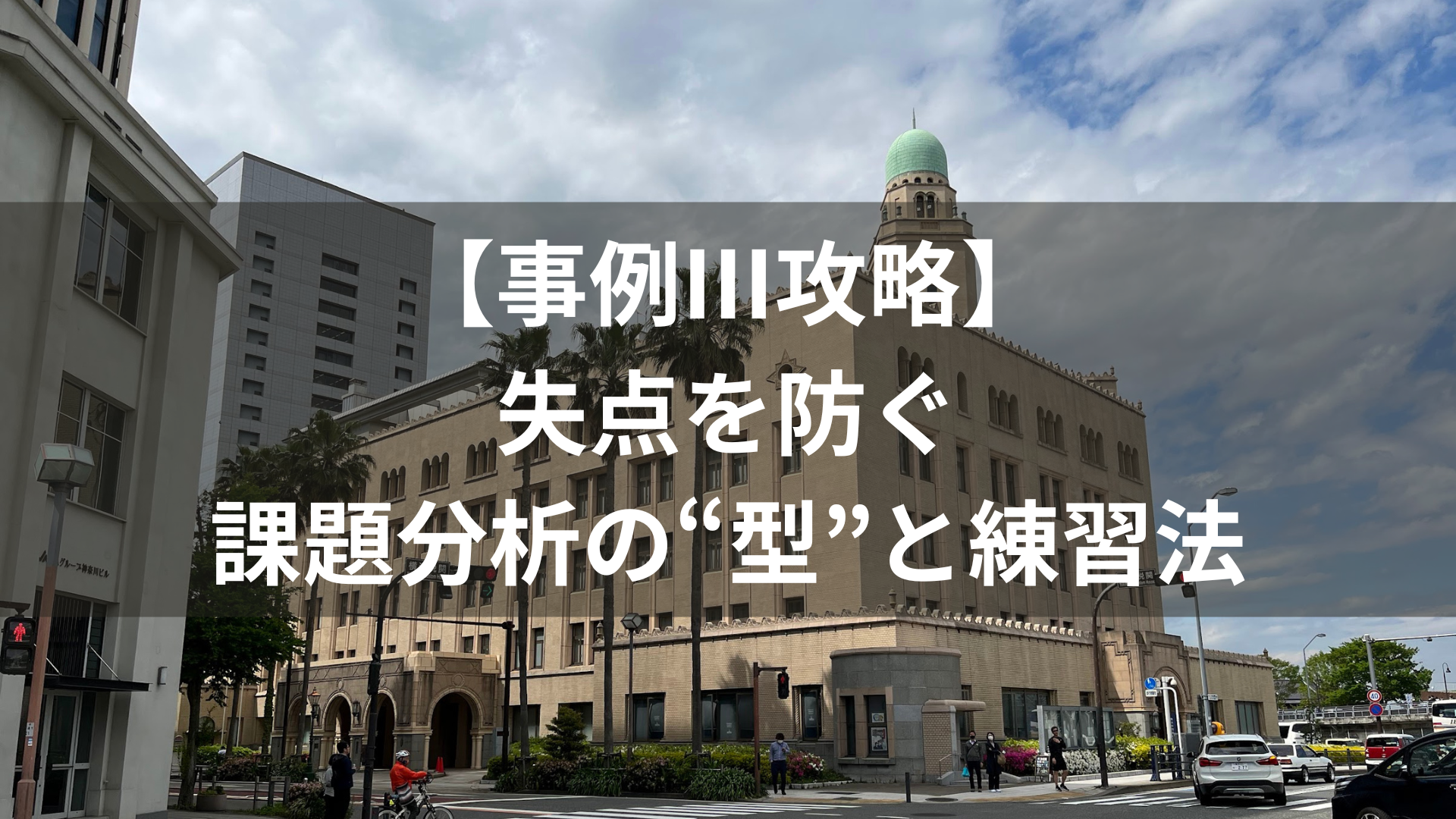


コメント