事例Ⅰは「覚えている知識」だけでは点数が伸びません。
なぜなら、与件文は現実の企業をモデルにしており、単純な理想論ではなく、その企業の制約や背景まで踏まえた提案が求められるからです。
そこで力を発揮するのが、組織・人事のフレームワークです。
正しく使えば、与件文から課題を素早く抽出し、再現性の高い答案を作れます。
本記事では、診断士視点でフレームワークを“試験用に最適化”する方法を詳しく解説します。
事例Ⅰに必要なフレームワーク一覧
事例Ⅰ(組織・人事)の出題範囲は幅広く見えますが、出題テーマを整理すると大きく「組織構造」「人的資源管理」「組織文化」の3本柱に集約されます。
これらを効率的に分析するために、あらかじめフレームワーク(分析の型)を頭に入れておくことが不可欠です。
単に知識として暗記するのではなく、「与件文にどう適用するか」という“橋渡し”を意識すると、答案の再現性が格段に高まります。
1. 組織構造分析フレーム
代表例
• 職能別組織(機能別組織)
• 事業部制組織
• マトリクス組織
これらの組織形態は、それぞれ強みと弱みがはっきりしています。
たとえば職能別組織は専門性の深化に強く、効率的な業務運営が可能ですが、部門間の調整コストが増すという弱点があります。
事例Ⅰでは、与件文中に「専門知識の深化」「部門間の意思疎通不足」といった表現が出てきた場合、それが組織構造の長所・短所に直結している可能性が高いのです。
試験対策では、長所=強化策、短所=改善策という対応関係を瞬時に想起できるよう、日頃から整理しておくことが重要です。
2. 人的資源管理(HRM)の4機能
人的資源管理は、事例Ⅰの中心テーマです。特に次の4機能は必ず押さえておきましょう。
• 採用(Recruitment)
• 配置(Placement)
• 評価(Evaluation)
• 育成(Development)
与件文では、「採用難」「若手社員の離職」「評価基準の不透明さ」「研修制度の不足」といった形で課題が提示されます。
ここでのポイントは、課題→原因→施策を一貫してつなげること。
たとえば「採用難」であれば、原因は「知名度不足」「採用チャネルの限定」などと推測し、施策として「地元学校との連携強化」「中途採用チャネルの多様化」など具体策に落とし込みます。
このように、HRMの4機能を課題整理のチェックリストとして活用すると、抜け漏れを防ぎやすくなります。
3. 組織文化・風土分析
組織文化は数値化が難しい分、与件文の形容詞や雰囲気を示す言葉から読み取る力が必要です。
例:
• 「保守的な社風」→変化への抵抗が強い
• 「トップダウン型の意思決定」→現場の意見が反映されにくい
• 「家族的経営」→従業員の定着率は高いが、成果主義との相性に課題
試験対策では、組織文化を強み・弱みの両面から整理できるようにしておくと、施策提案で説得力が増します。
また、シニア層の受験生にとっては、長年の職場経験を通じて培った“空気を読む力”が大きな武器になりますが、答案では主観を排し、与件文の事実に基づく記述が求められます。
4. 補助フレーム:ライフサイクルと戦略適合
事例Ⅰでは、企業の成長段階(創業期・成長期・成熟期・再建期)に応じた組織課題を問う設問が頻出します。このとき有効なのが企業ライフサイクルモデルです。
• 創業期:トップ依存、制度未整備
• 成長期:部門間調整、権限委譲
• 成熟期:硬直化、人材流出リスク
• 再建期:組織再編、モチベーション低下
ライフサイクルと経営戦略の整合性を確認することで、提案に現実味が生まれます。
まとめ
事例Ⅰに必要なフレームワークは、組織構造・人的資源管理・組織文化の3本柱を軸に、ライフサイクルや戦略適合の補助フレームを組み合わせるのが最も実戦的です。
これらを「覚える」段階で終わらせず、「与件文にどうマッピングするか」まで想定しておくことで、短時間でも的確な課題抽出と一貫した答案作成が可能になります。

与件文に隠れるフレームのヒント
事例Ⅰの与件文は、一見すると会社紹介や社長インタビューのような穏やかな文章ですが、その中には組織課題を特定するためのヒントが随所に埋め込まれています。
与件文を読むときは、「どのフレームワークの要素に当てはまるのか」を意識して拾い出すことで、答案作成の方向性が早い段階で定まります。
1. キーワードの裏にある意味を読む
与件文では、直接「課題」とは書かれず、やわらかい表現や形容詞で示されることが多いです。
例:
• 「若手社員の定着率が低い」→人的資源管理(育成・評価制度の課題)
• 「現場裁量が少ない」→組織構造(権限委譲不足)
• 「長年変わらないやり方」→組織文化(保守性・変革抵抗)
ポイントは、抽象的な表現をフレームの言葉に変換すること。これにより、課題の分類と施策提案が一貫します。
2. 数値データとの組み合わせで確度を上げる
与件文には売上推移や社員数構成、離職率などの数値データが掲載される場合があります。
例:
• 売上は増加しているのに利益率が低下 → 生産性低下や組織間連携の問題
• 従業員の平均年齢が高い → 後継者育成・技術伝承の必要性
• 新卒採用数が年々減少 → 採用チャネルや魅力発信の課題
数値は客観的な証拠になるため、答案に説得力を持たせられます。
シニア層の受験生は、実務で数値管理に慣れている方が多いため、その強みを答案構成に活かしましょう。
3. ストーリー展開を追う
与件文は時系列で語られることが多く、「過去 → 現在 → 未来」の流れの中に課題が潜んでいます。
• 過去の成功要因 → 現在の強みとして活かせるか
• 環境変化(市場縮小、競合増加) → 新たな組織対応の必要性
• 将来の方針 → それを実現するための組織再設計や人材育成の課題
試験中は、段落ごとに「これは組織構造?HRM?文化?」と分類メモを取る習慣をつけると、設問解答で迷いにくくなります。
4. 制約条件も拾う
事例Ⅰでは「こうしたいが〇〇のため難しい」という制約条件が頻繁に登場します。
例:
• 「多額の設備投資は難しい」→低コスト施策が必要
• 「熟練職人が高齢化」→短期間での技能移転が求められる
• 「地理的に採用対象が限られる」→オンライン研修や広域採用策
制約条件は施策の現実性を高める重要なヒントであり、提案の説得力を左右します。
まとめ
与件文は単なる文章ではなく、フレームワークを適用するための素材集です。
キーワード・数値・ストーリー・制約条件をフレームに紐づけながら整理することで、答案の骨子が自然と固まります。
これに慣れれば、試験本番での迷いが大幅に減り、限られた80分を効率的に使えるようになります。
フレーム適用の手順
事例Ⅰの最大のポイントは、限られた80分の中で課題抽出 → 原因分析 → 施策提案までを一貫して行うことです。
そのためには、与件文を読みながらフレームワークを即座に適用し、答案の骨格を固める必要があります。
以下は、試験本番で使える「5ステップ適用法」です。
ステップ1:与件文の第1読解で粗スクリーニング
試験開始直後、まず与件文を通読し、キーワードにフレームのラベルを貼る作業を行います。
例:
• 「離職率が高い」→ HRM(評価・育成)
• 「部門間の連携不足」→ 組織構造(調整機能不足)
• 「保守的な社風」→ 組織文化(変革抵抗)
この段階では深掘りせず、「どのフレームに属するか」だけをざっくり分類します。
ステップ2:設問文で優先テーマを特定
設問文は、出題者が「どのフレームの課題を答えてほしいか」を明確に示しています。
• 「人材育成の方策を述べよ」→ HRM(育成)中心
• 「組織構造上の課題を指摘せよ」→ 組織構造中心
与件文のラベル付け結果と設問テーマを照合し、重要度の高い部分から分析を始めます。
ステップ3:課題→原因→施策の三段階で整理
各テーマについて、次の順でメモを作ります。
1. 課題:与件文の事実を簡潔に表現
2. 原因:背景や制約条件を整理
3. 施策:原因に対応する現実的な改善策
ポイントは、課題と施策が直接リンクするように書くこと。リンクが弱いと、答案全体の一貫性が崩れます。
ステップ4:骨子を作成し、漏れをチェック
80分の試験では、骨子作成に5〜7分程度を確保できると理想です。骨子には以下を盛り込みます。
• 設問ごとの課題・原因・施策
• 使用するキーワード(フレーム用語)
• 制約条件への配慮点
作成後は、「組織構造」「HRM」「文化」の3分野に抜けがないかを確認します。
ステップ5:答案執筆でフレーム用語を自然に織り込む
答案では、フレーム用語を意図的に使うことで、採点者に「体系的な知識を持っている」と印象づけられます。
例:
• 「権限委譲を進めることで…」
• 「評価基準の明確化と育成計画の整備により…」
ただし、用語の羅列は避け、与件文の事実と結びつけて説明することが重要です。
まとめ
フレーム適用の最大の効果は、思考の順序を固定化し、迷いを減らすことにあります。
これにより、試験本番でも安定したパフォーマンスを発揮でき、時間配分にも余裕が生まれます。
慣れるまでは過去問演習でこの5ステップを繰り返し、頭と手を自動化モードにすることが合格への近道です。
現実感のある提案に仕上げるコツ
事例Ⅰの答案でよくある失敗は、「教科書的には正しいが、この企業には合わない提案」になってしまうことです。
出題者が求めているのは、あくまで与件企業の現状や制約に即した“実行可能な施策”です。
ここでは、現実感を高めるための4つのポイントを紹介します。

1. 制約条件を踏まえて優先順位をつける
与件文には、企業の資源制約や市場環境が必ず書かれています。
例:
• 「人員増強は難しい」→既存人材の活用や効率化が優先
• 「多額の投資はできない」→低コストの改善策が必要
• 「地域採用に依存」→地元ネットワークやオンライン活用
施策は必ず制約条件を前提に組み立てることで、現実的かつ説得力のある答案になります。
2. 短期施策と中長期施策をセットで示す
1つの施策だけでは片手落ちに見える場合があります。
例:
• 短期:評価基準の明確化、OJT強化
• 中長期:人材育成体系の構築、リーダー候補の計画的育成
このように、「すぐできること」と「将来に向けた準備」を組み合わせると、実務的な視点を感じさせられます。
3. 強みを活かしつつ弱みを補う
企業の強みを無視した改善案は、現場に受け入れられにくくなります。
例:
• 強み:家族的な社風 → 弱みの形式的評価制度を補う形で導入
• 強み:高い技術力 → 若手育成や技術伝承施策と連動させる
答案では、「強みを活かしつつ、課題を解消する」構造を意識しましょう。
4. 用語はシンプルかつ実務的に
フレーム用語や専門用語は採点者に知識を示す武器ですが、多用しすぎると机上論に見えます。
「ジョブローテーション」や「職能資格制度」といった用語は効果的ですが、具体的な狙いや実行手順とセットで書くことが重要です。
まとめ
現実感のある提案は、
1. 制約条件を踏まえる
2. 短期と中長期をセットで示す
3. 強みを活かし弱みを補う
4. 用語を具体化して使う
この4点を押さえることで実現できます。
こうした提案は、試験だけでなく診断士登録後の実務でも通用する“生きた知識”となります。

参考書籍・ツール紹介
事例Ⅰ(組織・人事)を安定して得点源にするためには、フレームワークの理解と適用練習を繰り返すことが不可欠です。
ここでは、実際に入手可能で、試験対策に直結する参考書籍とツールを紹介します。
1. 『中小企業診断士 最速合格のための第1次試験過去問題集 企業経営理論』(同友館)
事例Ⅰ対策の基礎となる「組織・人事」の一次知識を網羅した過去問題集です。特に組織論や人的資源管理の章は、二次試験での課題抽出の土台になります。
• おすすめポイント:解答解説が簡潔で、設問ごとに関連理論が整理されているため、復習しやすい。
• 活用法:過去問を解く→該当理論を確認 → 二次試験の事例で適用練習。
2. 『事例攻略のセオリー 中小企業診断士2次試験』(同友館)
二次試験全体の答案作成プロセスを体系的に学べる1冊。特に事例Ⅰの章では、与件文から課題を拾い、原因と施策をつなぐ手順が具体的に示されています。
• おすすめポイント:過去事例をベースにした再現答案と解説が豊富。
• 活用法:解説の骨子作成手順を自分の答案に取り入れる。
3. 『中小企業診断士 2次試験合格者の頭の中にあった全知識』&『同 全ノウハウ』(同友館)
2次試験に特化した対策書。出題頻度の高い論点ごとに、頻出キーワード・解答パターン・注意点が整理されています。
• おすすめポイント:フレームワークごとの解答例が豊富で、実戦向き。
• 活用法:本記事で紹介したフレームとの対応を意識しながら、該当ページを重点学習。
4. スマホで学べる「スタディング 中小企業診断士講座」(Web講座)
スタディングは、効率的な学習カリキュラムとスキマ時間活用に最適化されたオンライン通信講座です。2025年の第2次試験において合格者数が230名以上という実績があり、学習者に評価されています。
• おすすめポイント:スキマ時間にスマホで学習可能。
• 活用法:記事で解説した「5ステップ適用法」の復習に利用。
5. 思考整理ツール「Xmind」
答案作成の骨子を素早く作る練習には、マインドマップツールが効果的です。Xmindは無料版でも十分な機能があり、課題→原因→施策の流れを視覚的に整理できます。
• おすすめポイント:ドラッグ&ドロップで構造を組み替えられるため、試験前の思考整理に最適。
• 活用法:過去事例の与件文を読み込み、マインドマップで分類練習。
まとめ
本記事で紹介したフレームワークを定着させるには、書籍で体系を学び、オンライン講座やツールで実戦練習を重ねるのが最短ルートです。
リンク先から直接購入や申込が可能なので、ぜひ今日から学習サイクルに取り入れてください。
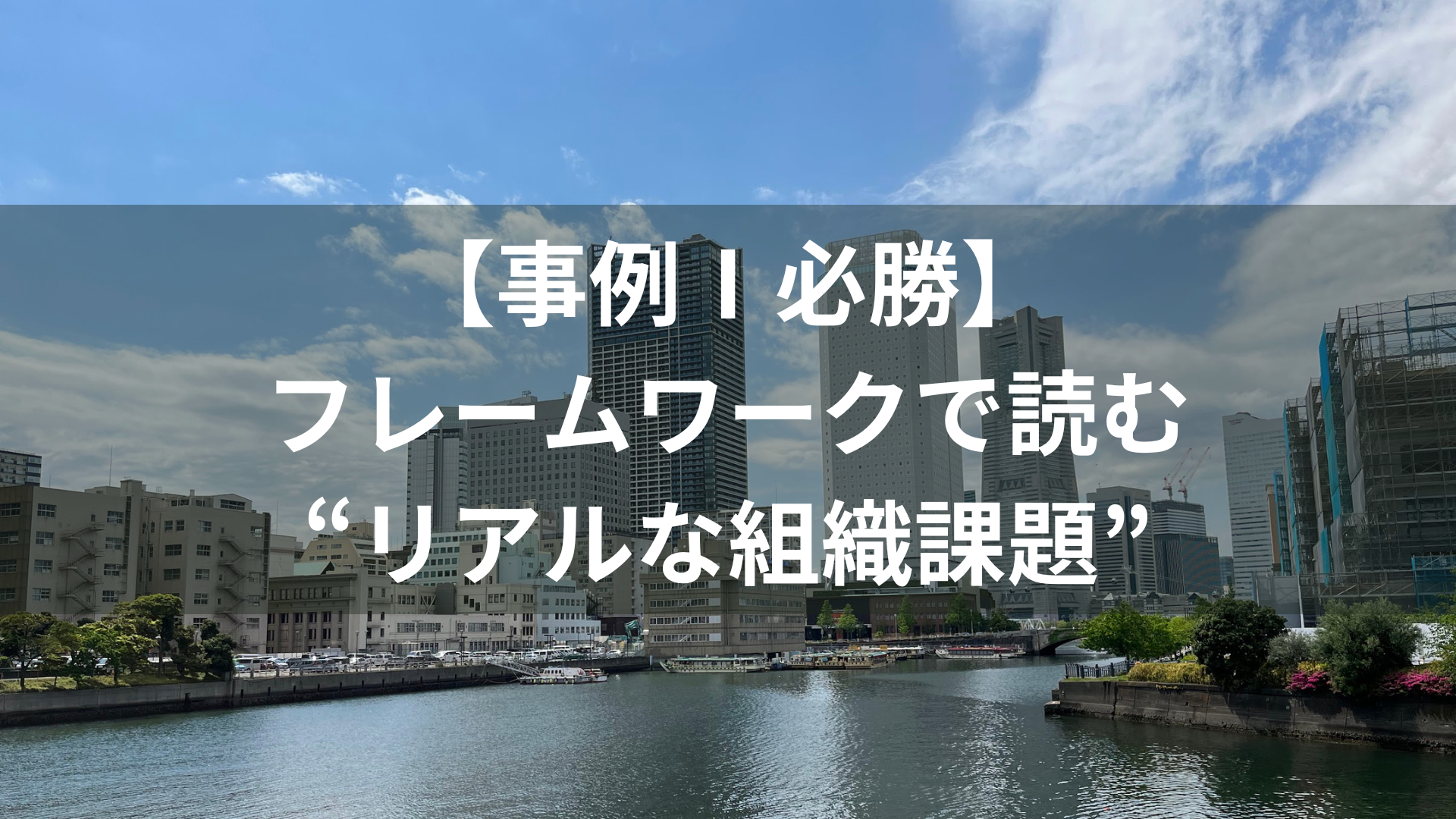
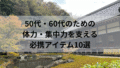

コメント