中小企業診断士は「試験合格」だけで完結する資格ではありません。
登録には「実務経験」を証明するステップがあり、それを満たす仕組みが「実務補習」と「実務ポイント」です。
この2つの制度は似ているようで、目的・方法・コストに大きな違いがあります。
今回は制度の全体像を俯瞰しつつ、シニア層が押さえておきたい注意点を紹介します。
実務補習と実務ポイント制度の位置づけ
中小企業診断士試験に合格した後、最初に直面するのが「登録要件を満たすための実務経験」です。
診断士は単なる試験合格者ではなく、実際に企業支援に携わる「実務家」としての力を持つことが求められるため、この仕組みが用意されています。
ここで選択肢となるのが 「実務補習」 と 「実務ポイント制度」 です。
実務補習は、中小企業診断協会が主催する公式プログラムで、現実の企業を対象にグループで診断・助言を行うものです。
短期間で集中的に実務を体験できる点が最大の特徴で、「試験合格から登録までをスムーズに進めたい人」に向いています。
一方で、平日を含む複数日程に参加する必要があり、仕事や家庭の予定との調整が難しいケースも少なくありません。
これに対して実務ポイント制度は、診断士としての活動実績をポイント化し、一定数を満たすことで実務要件をクリアできる仕組みです。研修参加や執筆活動、公的機関での支援実績など、幅広い活動が対象になります。
そのため「時間をかけてじっくり活動を積み重ねたい人」や「既にコンサルタントや士業として実務に関わっている人」に適しています。
ただし、計画的に活動を行わないと、必要なポイントが集まらず資格登録が遅れてしまうリスクもあります。
つまり両者は、どちらが優れているというよりも「どのように診断士としてキャリアをスタートさせたいか」によって選ぶべき制度です。
短期集中で一気に学ぶか、長期的に経験を積み重ねるか。ここを理解しておくことが、後の選択を迷わず行うための第一歩になります。

実務ポイント取得のメリットとデメリット
実務ポイント制度は、診断士としての活動を広く認定する仕組みであり、柔軟に実務要件を満たせる点が大きな魅力です。
しかし一方で、制度を十分に理解していないと「思ったよりポイントがたまらない」「登録が遅れる」といった落とし穴もあります。
ここでは、メリットとデメリットを整理してみましょう。
メリット①:多様な活動をポイント化できる
実務ポイント制度の最大のメリットは、その柔軟性です。
協会や研究会での活動、公的機関での経営支援、さらには専門誌への寄稿や講演なども対象となります。
すでに税理士や社労士など他士業として活動している人にとっては、日常の業務がそのままポイントになるケースも少なくありません。
特にシニア層にとって、これまでのキャリアを活かしやすい制度と言えます。
メリット②:自分のペースで進められる
実務補習と違い、特定の期間に拘束されることがありません。
仕事や家庭の都合に合わせて活動を選び、数年かけてポイントを積み上げることが可能です。
定年後にゆとりを持ちながら資格活用を目指す人には、特に相性が良い制度です。
デメリット①:計画性が必須
一方で、ポイントは自動的に貯まるものではありません。
対象となる活動を計画的にこなし、証明書や報告書をきちんと残す必要があります。
「活動はしたが申請に必要な書類がない」といった理由でカウントできない事例も見られます。
デメリット②:登録までに時間がかかる
実務補習なら15日コースを受講すればすぐに要件を満たせますが、ポイント制度は活動を積み上げる方式のため、早くても数か月〜数年を要するのが一般的です。
資格登録を急ぎたい場合には不利に働くこともあります。
実務補習と実務ポイントの比較
実務補習と実務ポイント制度は、いずれも中小企業診断士の登録要件を満たすための仕組みですが、その性質や使い勝手は大きく異なります。
ここでは両者を並べて比較し、自分に合った選択肢を見極める材料としましょう。
比較①:目的と学び方の違い
実務補習は「診断士としての実務を短期集中で体験する」ことに主眼があります。
実際の企業を対象に、グループで診断・報告書を作成するプロセスを経験できるため、実務スキルの習得や仲間との交流に直結します。
一方、実務ポイントは「診断士としての活動実績を広く証明する」仕組みです。
現場での支援、研修、執筆など多彩な経験を積み上げることで、徐々に資格者としての幅を広げていく形になります。
比較②:期間と柔軟性
実務補習は15日間(または5日コース×3回など)の決められた日程をこなせば、一気に要件を満たせるのが強みです。
ただし、平日も含まれるため、現役世代には日程調整が大きな課題になります。
対して実務ポイントは、数か月から数年にわたり自分のペースで取り組める柔軟さがあります。
特に定年後のシニア層や、既に士業として活動している人には取り組みやすい方法です。
比較③:コスト面の違い
実務補習は受講料が必要で、15日コースで十数万円と決して安価ではありません。
短期で確実に登録を済ませられるメリットはあるものの、経済的負担が伴います。
一方で実務ポイントは、活動そのものが仕事や学び直しの一環になり得るため、直接的な受講料は不要です。
ただし、セミナー受講や研修参加などで費用が発生するケースもあるため、全てが無料で済むわけではありません。
比較④:キャリア設計との相性
診断士として「早く登録し、肩書きを活かして活動を始めたい」人は実務補習向きです。
逆に「長期的に診断士活動を積み上げ、将来的に独立や地域貢献につなげたい」人には実務ポイントが合っています。

どちらを選ぶべきかの判断基準
実務補習と実務ポイント制度、どちらを選ぶかは「自分のキャリアのステージ」と「ライフスタイル」によって大きく変わります。
ここでは、具体的な判断基準を示します。
判断基準①:資格登録を急ぐかどうか
「試験に合格したらすぐに診断士として登録し、名刺に肩書きを載せて活動したい」という方には、実務補習が最適です。
15日間を集中的にこなせば一気に要件を満たせるため、時間的なメリットは非常に大きいといえます。
一方、「登録は数年かけても良いので、自分の活動実績を積み重ねながら資格を活かしたい」という方には、実務ポイント制度が合っています。
急がずとも、自身のペースで経験を証明できるからです。
判断基準②:現役世代か定年後か
現役世代の場合、平日の休暇取得が難しく、実務補習の日程調整に苦労することが少なくありません。
そのため、仕事との両立を考えると実務ポイントの方が現実的なケースもあります。
定年後やリタイア後の方であれば、時間の融通が利きやすく、実務補習に参加することも比較的容易です。
むしろ補習で得られる受験仲間やネットワークは、今後の活動に大きな資産となるでしょう。
判断基準③:独立志向か継続学習志向か
将来的に独立してコンサルタントとして活動することを考えている方は、実務補習を通じて「診断プロセスの型」を早期に身につけるのが効果的です。
一方で「資格を学び直しの証明として活用したい」「地域活動や副業で徐々に力を試したい」という方は、実務ポイントを活用する方が自分に合ったスタイルを築きやすいでしょう。

まとめ:自分に合った制度選びで診断士ライフをスタート
中小企業診断士の登録要件を満たすためには、「実務補習」と「実務ポイント制度」という2つの選択肢があります。
どちらも診断士としてのスタートに不可欠なプロセスですが、その性質は大きく異なります。
• 短期集中で一気に登録したい人は実務補習
• 自分のペースで活動を積み上げたい人は実務ポイント制度
このシンプルな整理を出発点に、自分のキャリア設計やライフスタイルに照らし合わせて判断することが大切です。
特にシニア層にとっては、「資格を取ること」以上に「資格をどう活かすか」が重要です。
補習を通じて仲間を得るのも、ポイント制度を使って実績を重ねるのも、いずれも診断士としての未来を築く有効な道筋です。
大切なのは、自分に合った方法を選び、計画的に行動すること。
これから診断士として歩み出す方にとって、本記事が制度理解と選択の後押しとなり、資格を単なる肩書きで終わらせず、キャリアや地域貢献につなげる一助となれば幸いです。


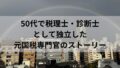
コメント