私は今まで、いくつかの資格を取得し、サラリーマン生活から独立することを夢見ていました。
振り返ってみると、今手元に残っているのは財務会計に関連する資格であり、具体的には日商簿記、ファイナンシャルプランナー、税理士、中小企業診断士になります。
語学は得意ではないので、英語などの資格はほぼ皆無であり、情報系も得意分野ではありますが、本腰入れて取得するには至りませんでした。
ここでは、その財務会計分野の資格取得に関する私の体験談を記していこうと思います。

日商簿記2級の取得
私が国税局に入局したのが昭和62年4月ですので、もう40年以上も前になります。
私は国税専門官として採用されましたので、当然ながら国税専門官という公務員試験を受験し合格したことが前提となっています。
つまり、就職するために試験勉強し合格することができた、というわけで、これも広い意味で資格取得のための勉強といえるでしょう。
国税専門官は最初の3ヶ月で基礎研修を受講し、その後の3年間は税務署に赴任し実務経験を積みます。
そして3年後に6ヶ月の専門官研修を受講し、国税調査官という職位を得て大きく羽ばたいていくのです。
その専門官研修の過程で日商簿記2級の取得があり、これが研修修了の条件の一つとなっているため、この2級取得のための試験勉強も行わなければなりませんでした。
最初は3級から取得を始め、2級取得へと段階的に進んでいきます。
そして、意欲があれば1級の取得を目指すことで箔がつくのですが、実務ではそこまで要求されていないため、私は2級までの取得で終えました。
ファイナンシャルプランナー2級の取得
私は40代のころにファイナンシャルプランナー2級技能士の資格を取得しました。
これは国税の実務に直接関わる部分が多々あり、いずれは独立開業した際のセールスポイントや対応業務の拡大、既存業務との相乗効果を期待したことが受験する動機となっています。
ファイナンシャルプランナー試験は、当時から日本FP協会ときんざい(金融財政事情研究会)の2系統での資格があり、私は3級はきんざいの試験を、2級は日本FP協会の試験を受験しました。
2種類ある理由などの背景などはこの記事の目的ではないので詳細は省きますが、日本FP協会は世界基準である「CFP」を管理している団体なので、そちらとの互換も考えて試験を変えました。
それにより、2級ファイナンシャルプランナー技能士の資格以外に、日本FP協会が直接管理する「AFP」の資格も取得することができました。
ただ、当時はまだ公務員であり兼業することはできないので、AFPは取得はしたものの活用せずに脱退しました。(維持費がかかるため)
いずれ税理士として独立した際に、ファイナンシャルプランナーとしても活動できるための下地を作ったことになります。

税理士資格の取得
税理士資格については、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、国税に関する実務に一定年数経験することによって自動取得(税理士試験の全科目免除)することができます。
税理士資格の全試験免除をするために必要な要件として、次のように規定されています。
・ 10年又は15年以上税務署に勤務した国税従事者は、税法に属する科目が免除されます。
・ 23年又は28年以上税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者は、会計学に属する科目が免除されます。
(税理士の資格取得 – 日本税理士会連合会)私の場合は国税をリタイアしたのが勤続26年であり、指定研修として国税専門官の専科研修を修了したので、税法の科目、会計学の科目のいずれも免除することができました。
もっとも、公務員としての兼業はできないので、実際に公務員を退職することで税理士として登録ののち活動することになります。
厳密には、税理士の場合、資格があっても税理士としての活動は禁止されており、全国組織の税理士会に所属することで税理士としての活動が許されるのです。
その意味では、単なる資格ではなく、職業として職務を行うための資格ということができます。

中小企業診断士資格の取得
そして、私が定年間近の50代最後の年に取得した、中小企業診断士資格のお話をいたします。
別の記事で試験勉強についていろいろと書いていますので、ここでは体験談としての記載にとどめます。
私は国税専門官として26年勤務したあと、国税時代の元上司で現在税理士とし活動されている方の勧めで、50歳で国税から退職いたしました。
といっても、そこですぐに税理士になるわけではなく、民間企業の経理責任者への転職を勧められたのです。
いきなり税理士になるよりも、まだ若いうちに民間企業経験するのも悪くないな、と思ったので、その勧めに応じることになりました。
民間企業の経理責任者、職名は財務部長なのですが、半分以上は経営に携わる立場であることから、それまで税務に関するさまざまな知識はあっても、経営に関する知識はほとんどなかったので、その知識や経験を得るための資格とて、MBAと中小企業診断士に注目し、その中で税理士と同じ国家資格である中小企業診断士の資格を取得することにいたしました。
診断士資格は1次試験が7科目、2次試験がその7科目に関連する4事例の筆記試験と実務補習を経て、ようやく取得できる資格なので、それなりに難関ではあります。
その辺りの苦労話は別の機会にお話しするとして、なんだかんだでその民間企業の定年前の59歳になんとか取得することができました。
思えば自分なりの経験を踏まえて、段階的に実務に通じる資格取得をしてきたと自負しております。
以上、経験談としては少し表面的な記述になりましたが、シニアの学び直しとしての観点から得るものが少なからずあると思いますので、読者の皆様の参考になれば幸いです。
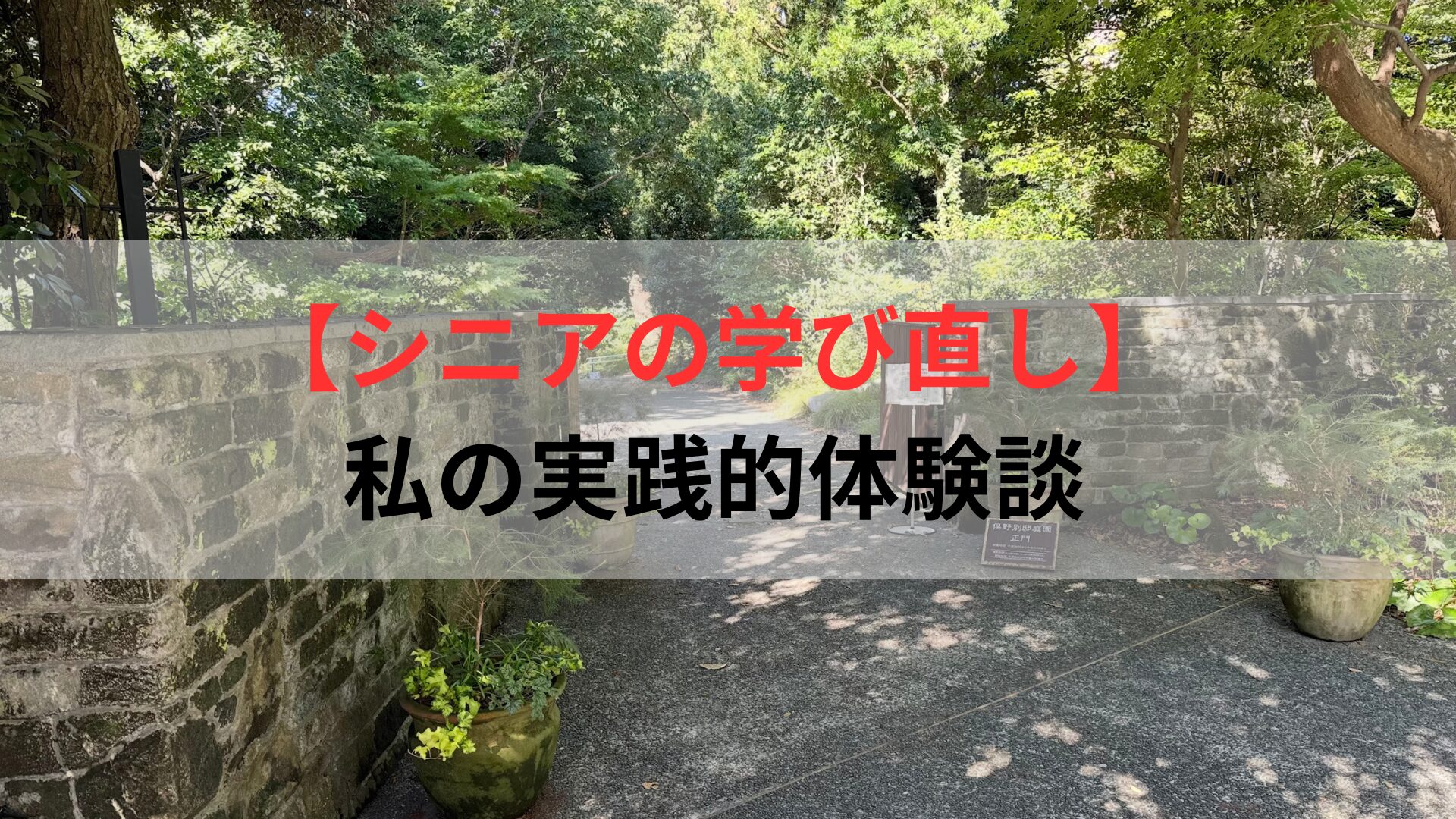


コメント