中小企業診断士試験の「情報システム」科目は、受験生の得点差が大きく出やすい分野です。
実際に、令和5年度の合格者アンケートでは、「情報で苦戦した」という声が最も多く寄せられました。
しかし、その要因の多くは「用語の丸暗記」に頼ってしまう学習スタイルにあります。
この記事では、試験出題の流れを“業務プロセス”としてとらえることで、知識の定着率と理解度を高める効率的な学習法をお伝えします。
IT初心者でも安心して学べる方法を、中高年層にもわかりやすく解説していきます。
なぜ「丸暗記」は情報システム攻略に向かないのか
中小企業診断士試験の一次試験における「情報システム」は、出題範囲が広く、専門用語が飛び交う独特の科目です。
通信技術、業務システム、データベース、セキュリティ、さらには最新トレンドであるクラウドやAIまで含まれており、まるで「ITの全領域を広く浅くなぞる」ような内容です。
このような試験構成に対し、過去の合格者の中でも一定数が「とにかく用語を覚える」という丸暗記戦略を取っています。
しかし、その学習スタイルには明確な限界があります。
特に50代以降の受験生にとって、暗記一辺倒の学習は記憶の定着率が低く、短期間で忘却しやすいというリスクがつきまといます。
加えて、近年の出題傾向を見ると、単なる定義や用語の知識だけでは解けない「つながり」や「業務理解」が問われる問題が増えています。
たとえば、以下のような出題がその典型です。
• 「受発注システムの導入に際し、外部ベンダーと締結すべき契約として最も適切なものはどれか」
• 「POSデータを活用した在庫管理に関する説明として正しいものはどれか」
これらの設問では、単語の意味を知っているだけでは正解できません。
システムの役割や導入場面における“仕組み”を理解していなければ対応できないのです。
さらに、試験本番では記憶の“再生”ではなく“判断”が求められます。
つまり、「これはAだ」と思い出すだけでなく、「この選択肢はなぜ正しく、他がなぜ間違っているか」を比較し、選び抜く力が必要なのです。
この力は、暗記では養えません。知識同士を有機的につなげ、背景や文脈ごと理解して初めて発揮されるものです。
特に中高年の学習者にとって、こうした“背景理解”を重視する学び方は、脳の働きに合った効率的なアプローチとも言えます。
年齢を重ねると短期記憶力は低下する一方で、「意味づけ」や「既存の知識との関連づけ」による記憶保持は強化される傾向にあるからです。
したがって、情報システムを攻略するためには、「暗記ではなく、しくみの理解を中心とした学習法」にシフトすることが、合格への近道となるのです。

「仕組みで覚える」ための3つの視点
情報システムを“ただの用語の羅列”として覚えようとすると、どこかで記憶が崩壊します。
しかし、その用語がどんな場面で、どのように使われているのかという“仕組み”を理解すれば、驚くほど記憶に定着しやすくなります。
ここでは、情報システムを構造的に理解するために有効な「3つの視点」を紹介します。
●視点①:入力→処理→出力の「情報の流れ」でとらえる
情報システムを理解する最初の軸は、「情報の流れ」です。
すべての業務システムは、
入力(Input) → 処理(Processing) → 出力(Output)
という基本構造で動いています。
たとえば、売上伝票を入力し、在庫情報を更新し、売上レポートを出力するという一連のプロセスです。
このフローを意識すると、各用語がどの段階に属しているのかが明確になり、頭の中で“位置づけ”できるようになります。
たとえば、スキャナは「入力」、RDB(リレーショナルデータベース)は「処理」、BIツールは「出力」に関わる技術です。
こうした分類を行うことで、「この用語は何のためにあるのか?」という問いに答えられるようになり、単なる丸暗記から脱却する大きな第一歩になります。
●視点②:業務プロセスとシステム機能を“つなげて”覚える
次に大切なのは、業務とシステムがどう関係しているかを理解することです。
たとえば、「受発注管理システム(OMS)」という用語を見たとき、「企業のどの業務に使われているか?」がすぐに思い浮かべられるでしょうか。
これは「受注入力 → 在庫確認 → 発注処理 → 納品管理」といった業務フローとセットで理解すべきものです。
業務プロセスと関連づけて学ぶことで、それぞれのIT用語の“活躍する場面”が明確になり、理解が一気に深まります。
特に、企業内で働いた経験がある50代・60代の方にとっては、実体験と結びつけながら学ぶことができる強みがあります。
診断士として、クライアントの業務改革を支援する際にも、この“業務×システム”の視点は欠かせません。
●視点③:代表的なシステム構成を「全体像」でとらえる
最後に意識したいのが、「全体像を描く力」です。
情報システムは単体で存在するわけではなく、複数の構成要素が有機的につながりあっています。
たとえば、企業の基幹系システムを例にすると、以下のような構成が一般的です。
• フロント(ユーザーが使う画面)
• アプリケーション層(業務ロジックを処理)
• データベース層(情報の蓄積と検索)
• 通信・ネットワーク層(データのやり取りを支える)
このような“階層構造”や“レイヤー構成”を図解で学ぶことで、それぞれの用語がどの部分に関わっているのか、役割と位置づけが明確になります。
診断士試験では、ERPやSCM、CRMなどの横文字の「統合システム」に関する問題も多く出題されますが、まずは構成図レベルでの「鳥瞰的理解」を持っていることが、正解への大きな近道となります。
この3つの視点を組み合わせることで、情報システムは“ばらばらの用語の集合”から、“理解可能な構造体”へと変わります。
そしてそれこそが、年齢を重ねても学び続けられる「理解重視の学習スタイル」への第一歩となるのです。
実務経験がなくてもOK!楽天ブックスやAmazonで買えるおすすめ書籍3選
実務未経験でも、情報システムを「仕組み」で理解できるようになる学び方に合致した書籍を厳選しました。以下はAmazonや楽天ブックスで購入可能かつ理解と分析力を備えた構成のものだけをご紹介しています。
① 中小企業診断士 最速合格のための 第1次試験 過去問題集〈5〉経営情報システム 2025年度版(TAC出版)
特徴:令和元年~令和5年度までの「経営情報システム」分野の本試験問題を5年分まるごと収録し、選択肢ごとに丁寧な図付き解説を掲載(約100点分) 。
なぜ理解学習に向いているか:図や表で比較されている解説は、単語の意味だけでなく「なぜこの選択肢が正しく、他は誤りなのか」を論理的に理解させる構成。
これは「背景 → 文脈 → 選択肢」の判断力を養うのに最適です。
② 出る順中小企業診断士 FOCUSテキスト 経営情報システム(東京リーガルマインド)
特徴:試験頻度の高いテーマを優先して掲載し、QRコードから累題(過去問)に即アクセス可能な「トライアル解説」付き。初学者でも効率良く知識が整理可能なテキストです 。
理解への工夫:章ごとに「業務・システムの接点」「現場での使われ方」「選択肢の判断基準」を明確に整理。
「点を打ち込む」よりも「線でつなぐ」理解構造が自然に形になります。
③ 図解即戦力 ITインフラのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書
特徴:クラウド、サーバー、ネットワーク、セキュリティなど、情報システムの基盤技術を図解とイラストで体系的に解説した入門書。
学び方の意図: ITインフラを構成する技術を、「ハードウェア」「ネットワーク」「クラウド」などのレイヤー構造で整理し、各用語の「意味・役割・仕組み」をセットで解説。
業務との関連性にも触れており、中小企業診断士試験の背景理解に最適です。
📘 書籍選びのポイントと活用法
| 📌 選び方 | ✅ 理由・効果 |
|---|---|
| 1. 図・表がある本 | 頭の中で仕組みをイメージ化でき、記憶の定着が進む(特にシニア層に有効) |
| 2. 解説が「なぜ」中心 | 問題の背景や選択肢の比較で論理的判断力を養える |
| 3. 過去問を反復できる構成 | 類型理解→繰り返し解答で知識が定着しやすい学習サイクルを作れる |
🔁 学習スタイルの提案
テキストで背景を把握 → 過去問で判断力を磨く → 図解本で全体像をつかむという三段階学習が合格への効率的な流れです。
書いた書籍が「難しく感じられる」場合には、「IT革命が面白いほどわかる本」のようなやさしいイラスト中心の入門書で、まず“文脈・構造”を読める状態にしてから、経営情報システム特化の問題集に進むのも効果的です。

まとめ|「覚える」から「理解する」へ。情報システム攻略の第一歩を
情報システムは、「横文字だらけで難しそう」「覚えることが多くてつらい」というイメージを持たれやすい科目です。
特に年齢を重ねると、記憶力の面で不安を感じ、暗記中心の学習では限界を感じやすくなります。
しかし本記事でお伝えしたように、情報システムは“仕組み”を理解することで、知識が自然とつながり、記憶にも残りやすくなる分野です。
つまり、「暗記しないと受からない科目」ではなく、「構造を理解すれば武器になる科目」なのです。
本記事の重要ポイントを振り返りましょう
✅ 単なる用語の暗記ではなく、「入力→処理→出力」という情報の流れで理解することが第一歩
✅ IT用語を業務プロセスと関連づけて学ぶことで、実務にも活きる知識となる
✅ 図解と過去問を併用した“構造理解型の教材”を活用すれば、実務経験がなくても合格ラインに届く
これから学習を始める方も、いまつまずきを感じている方も、「理解で覚える」学び方に切り替えるだけで、情報システムがぐっと身近に感じられるはずです。
次の一歩|やるべきことは「教材を変えること」から
まずは、図解中心の参考書や、業務の流れと結びつけて解説している問題集を手に取ってみてください。
本記事で紹介した書籍はすべてAmazonなどで購入可能です。
理解重視の学び方に切り替えれば、あなたの中で「わからない」が「わかる」に変わる瞬間が、きっと訪れます。
学び直しに遅すぎることはありません。情報システムを“得点源”に変える力は、あなたの中にすでにあります。
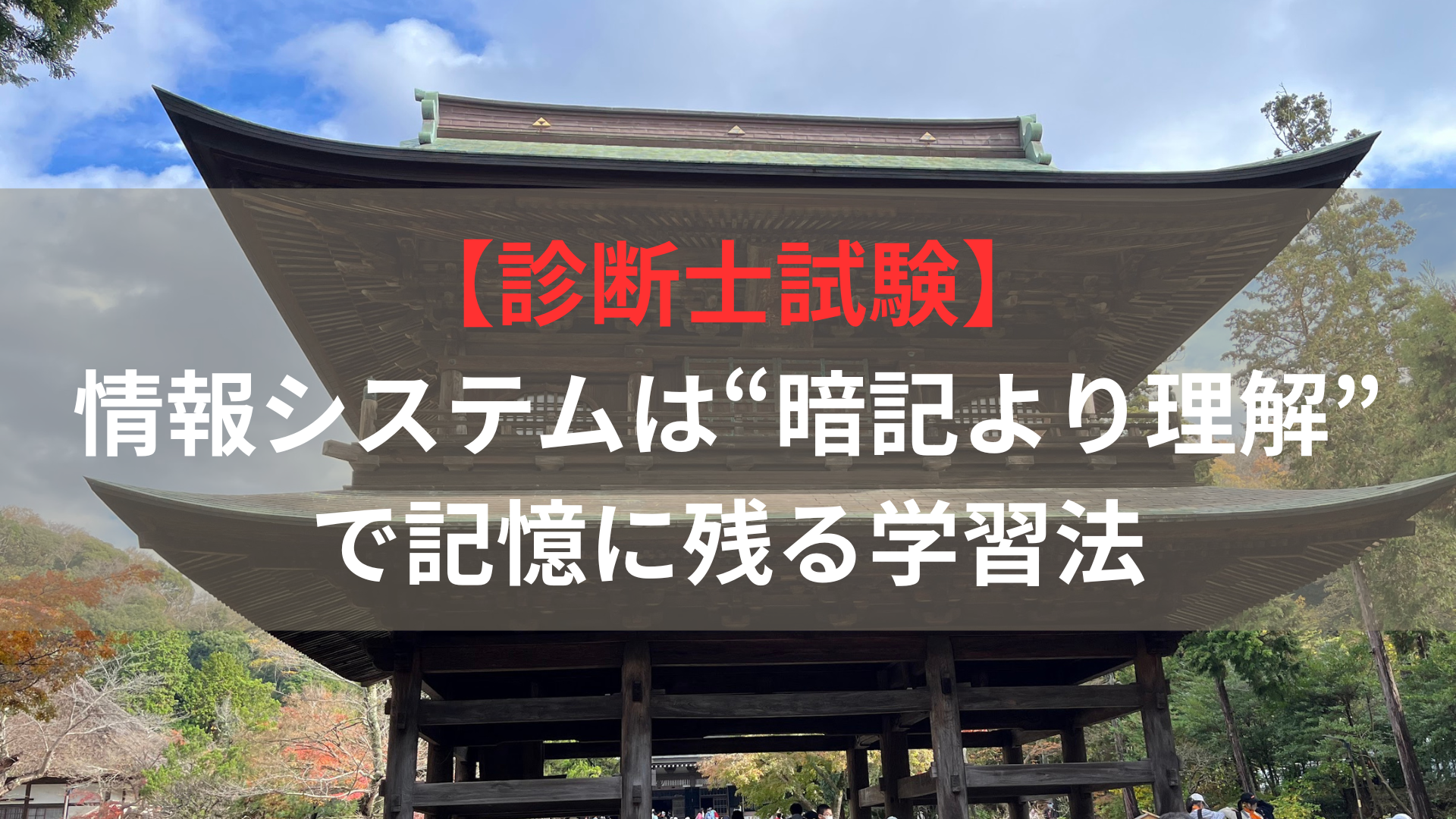

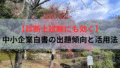
コメント