中小企業診断士2次試験の壁は、知識よりも「制限時間内に筋の通った文章を書く力」です。
50代で挑戦する方の多くが、「頭ではわかっているのに文章にすると伝わらない…」という悩みを抱えています。
これは経験不足ではなく、文章の組み立て方=“フレーム”の欠如が原因。
本記事では、記述が苦手な方でも合格答案を作れる「フレーム思考」の具体的な使い方を、試験に直結する形で解説します。
2次試験で求められる文章力の正体
中小企業診断士2次試験の合否を分ける最大のポイントは、「与えられた情報を整理し、論理的かつ簡潔に表現する力」です。
1次試験のように知識をマークシートで選ぶだけではなく、事例企業の課題を読み取り、自分の言葉で助言することが求められます。
ここに、多くの受験生がつまずく理由があります。
知識があっても得点できない理由
50代の受験生は、実務経験が豊富な方が多く、ビジネス知識や解決策のアイデアも豊富です。
しかし、その経験値が逆に文章の冗長化を招き、「結局何を伝えたいのか」が採点者に伝わらないケースが少なくありません。
採点者は短時間で大量の答案を読むため、論点が埋もれた文章は大幅減点のリスクがあります。
“書く力”ではなく“構成力”
2次試験における「文章力」とは、文学的な表現力や語彙の豊富さではありません。
重要なのは、制限時間80分の中で、設問の意図に沿った骨格(構成)を瞬時に組み立てる力です。
この「骨格」を作るために有効なのが、後述するフレーム思考です。
フレームを使えば、解答に必要な要素を抜け漏れなく並べ、論理的な流れを作ることができます。
採点者が求める3つの要素
2次試験の模範解答や高得点答案を分析すると、共通して以下の要素が盛り込まれています。
1. 設問の要求に正確に答えている(論点のズレがない)
2. 理由・根拠が明確(与件文や知識に基づく)
3. 文章構成が簡潔で読みやすい(一文が長すぎない)
この3つを確実に押さえることが、合格答案への第一歩です。
次のパートでは、この3要素を効率的に満たすための「フレーム思考」について詳しく解説します。
フレーム思考による解答パターン化
2次試験では、制限時間80分という制約の中で「読み取り → 構成 → 記述」を行います。
ここで多くの受験生が失敗するのは、答案作成の順序や流れが毎回バラバラになってしまうことです。
このムラをなくし、安定して得点できる答案を作るために有効なのがフレーム思考です。
フレーム思考とは?
フレーム思考とは、文章の骨格(枠組み)を先に作り、その枠に情報を当てはめていく手法です。
診断士2次試験では、設問ごとに使える型(パターン)を事前に準備しておくことで、解答作成のスピードと精度を飛躍的に上げられます。
例えば、よく使われるフレームは以下の通りです。
• 原因 → 影響 → 対策(問題解決型)
• 現状 → 課題 → 解決策 → 効果(提案型)
• 強み → 活用方法 → 期待効果(資源活用型)
フレームを使った解答作成の流れ
1. 設問解釈
設問文から「聞かれていること」と「答えるべき要素」を明確化します。
例:『課題とその改善策を述べよ』 → 「課題」「改善策」という2つの要素を明確に分ける。
2. フレーム選択
設問の要求に合った型を選びます。課題と改善策を問うなら「課題 → 解決策」の2段構成が有効。
3. 与件文から情報抽出
選んだフレームの各要素に対応する情報を、与件文や知識から拾い出します。
4. 骨組み作成
抽出した情報をフレームの順番に並べる。ここではまだ文章化しません。
5. 文章化
骨組みをもとに、設問の要求に沿った簡潔な文章へ落とし込みます。
フレーム化の最大のメリット
フレームを使えば、設問ごとにゼロから文章を考える必要がなくなります。
結果として、「何を書くか」で迷う時間が減り、「どう書くか」に集中できるため、時間内に安定した品質の答案を作れるようになります。
さらに、模試や過去問を通じて繰り返し同じ型を使うことで、試験本番でも自動的に手が動くレベルまで習熟できます。
練習法と上達のステップ
フレーム思考は、知識ではなく“技能”に近い性質を持っています。
したがって、理解しただけでは身につかず、反復練習によって自動化することが不可欠です。
ここでは、50代受験生でも無理なく続けられる3ステップの練習法を紹介します。
ステップ1:過去問の設問をフレーム化する
まずは過去5年分の2次試験問題を用意します。
設問ごとに「問われている要素」を抽出し、フレーム化します。
例:『B社の課題と改善策を述べよ』 → 課題 → 改善策
この作業を繰り返すと、出題パターンが限られていることに気づき、試験本番で迷う時間を大幅に減らせます。
ステップ2:与件文の情報を枠に当てはめる練習
次に、選んだフレームの各要素に、与件文から抜き出した情報を配置します。
この段階では文章化せず、「骨組みメモ」の形で構成だけ作ることがポイントです。
慣れてくると、与件文を読みながら即座にフレームに沿って分類できるようになります。
ステップ3:時間を計って文章化する
最後に、実際の試験時間を意識して文章化します。
最初は制限時間を長め(15〜20分/設問)に設定し、徐々に短縮。
文章化の際は、1文の長さを短くし、キーワードを盛り込む習慣をつけます。
模試や過去問を使い、このステップを繰り返すことで、フレーム作成から文章化までの流れが定着します。
練習を習慣化するコツ
• 毎日1問だけ解く(心理的負担を減らす)
• 週1回は時間無制限で復習(思考の質を高める)
• 作成した答案を添削に出す(第三者の視点で改善点を把握)このサイクルを続ければ、「構成がまとまらない」状態から脱し、試験本番でも迷わず書き始められる力がつきます。
学習効率を上げる教材・ツール
フレーム思考は独学でも身につきますが、限られた時間で効率よくレベルアップするには、体系的な教材や添削サービスの活用が効果的です。
ここでは、50代受験生が実践しやすく、かつ試験対策に直結する学習リソースを紹介します。
1. 記述力を鍛える過去問分析書
• 『中小企業診断士 最速合格のための第2次試験過去問題集』(同友館)
過去問と模範解答に加え、設問解釈や構成例まで掲載されており、フレーム化の練習に最適です。
特に、答案構成例を自分の解答と見比べることで、抜けやすい要素を発見できます。
• 『ふぞろいな合格答案』シリーズ(同友館)
実際の受験生答案と採点コメントが豊富に掲載されており、自分の文章がどこで減点されるかを把握できます。
フレーム思考の適用例も多数含まれています。
2. 添削付きオンライン講座
• TAC 2次試験直前答練(通信講座)
制限時間内で答案作成 → 添削 → 解説講義のサイクルを短期間で回せる講座。
特に添削コメントが具体的で、「どの要素が不足しているか」を的確に指摘してくれます。
• MMCの事例演習講座(通信)
フレームの使い方と文章表現の両方を同時に鍛えられる設計。添削後のフィードバックが詳細で改善点が明確です。
3. AI・デジタルツール
• Notion/Evernote
過去問の設問と自作フレームをデータベース化して整理可能。キーワード検索で即座に類似問題を引き出せます。
教材選びのポイント
• 自分の弱点(設問解釈/文章構成/表現力)に直結するものを選ぶ
• 「読んで終わり」ではなく、「解いて添削を受ける」教材を優先
• 書籍+演習+添削の3点セットで学習効率を最大化するこれらの教材やツールを活用すれば、フレーム思考を短期間で習得し、試験本番で安定した得点を取れる文章構成力が身につきます。
まとめ|フレーム思考で“迷わない文章力”を手に入れる
中小企業診断士2次試験で求められるのは、知識量よりも設問に沿って論理的に構成された文章を書く力です。
その核心にあるのが「フレーム思考」であり、これを習得すれば、答案作成で迷う時間を大幅に減らせます。
本記事でお伝えした内容を振り返ると――
• 文章力とは“構成力”であり、型を持つことで安定した答案が作れる
• フレームを選び、情報を枠に当てはめる流れを身につければ、試験本番でも自動的に手が動く
• 過去問分析・時間計測練習・添削サービスを組み合わせることで、短期間で得点力を高められる
この方法は、合格後の実務にもそのまま活用できます。
診断報告書、提案書、助言書――すべてのビジネス文書は「フレーム構造」を意識すれば、短時間で読み手に届く内容に仕上げられます。
試験本番までの限られた時間、ただ闇雲に文章を書くのではなく、「型」を武器に戦略的に訓練する。
それが、50代からの挑戦でも合格を引き寄せる最短ルートです。
今日から過去問を1問選び、自分だけのフレームを作る練習を始めてみてください。
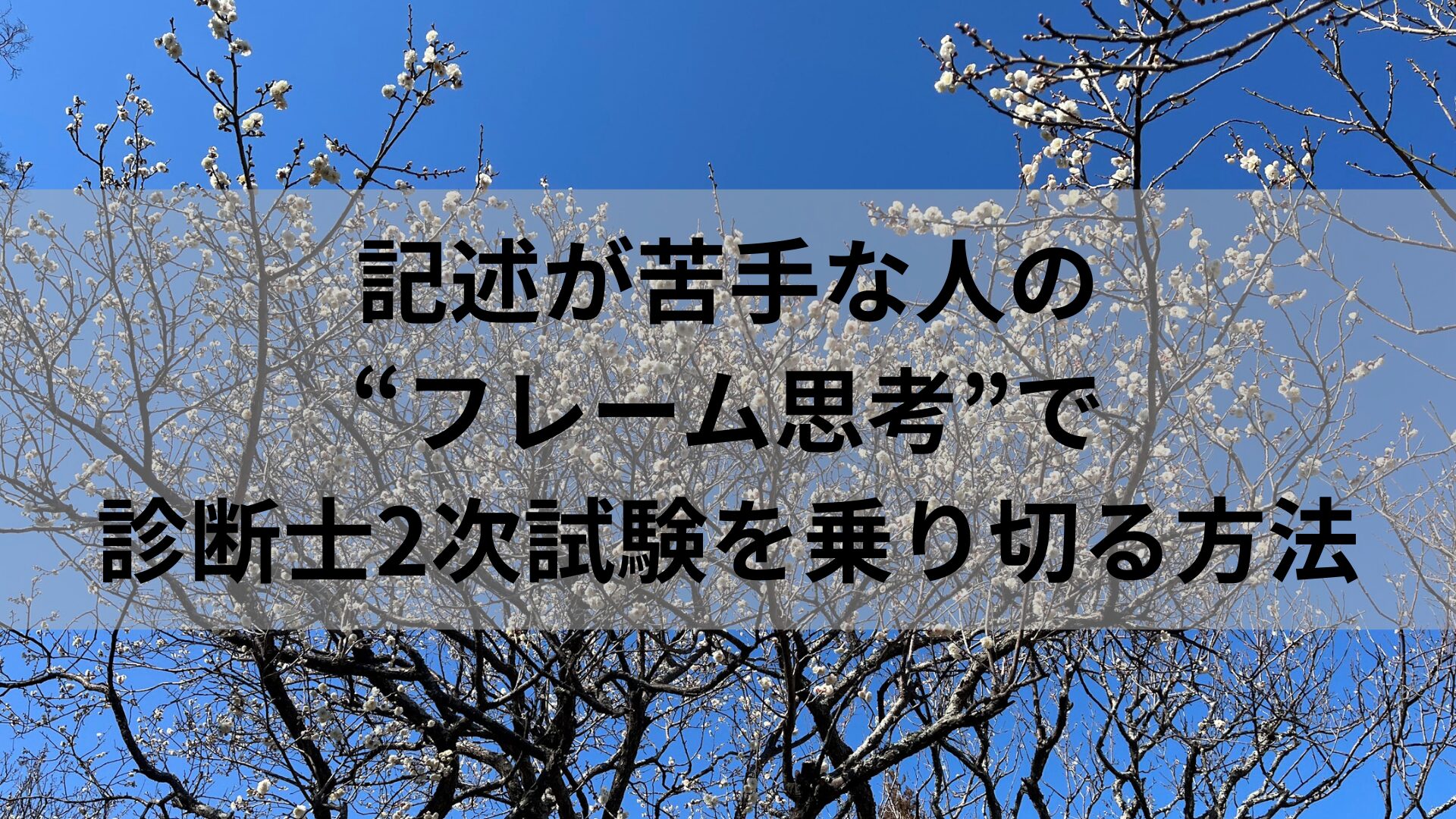

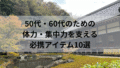
コメント