会議の席で「BS」「PL」という言葉が飛び交うたびに、なんとなく笑顔でごまかしていませんか?
家計や副業の数字も、「なんとなく」で処理していませんか?
数字が苦手だからこそ、最低限の財務・会計の用語を知るだけで、不安が減り、自信がつきます。
本記事では、数字が苦手なシニアの方に向けて、経営や生活にすぐ役立つ基本用語をわかりやすくお伝えします。
なぜ数字が苦手な人に財務・会計の知識が必要なのか
会議や打ち合わせの席で、「BS(貸借対照表)」や「PL(損益計算書)」といった言葉が飛び交い、うまく話についていけずに曖昧にうなずいてしまった経験はありませんか?
家計や副業の収支を見直したくても、数字の意味がよく分からず、「まあこんなものか」とごまかしてしまったことはありませんか?
こうした経験は、多くのシニア層に共通する悩みです。
私たちは長い職業人生の中で、現場感覚や経験則に頼って仕事や家計を切り盛りしてきました。
しかし、いざ経営改善や生活設計と向き合うとなると、改めて「数字」という壁にぶつかる方が少なくありません。
でも、安心してください。
財務や会計の知識といっても、複雑な計算ができる必要はありません。
最低限の基本用語を理解し、数字の「見方」が分かるだけで、状況を把握する力がぐっと高まります。
特に、次のような場面では基本的な知識が役立ちます。
• 経営の現場での意思決定に説得力を持たせたいとき
• 家計や副業の収支をしっかりと管理したいとき
• 将来の資金計画を立てたいとき
中小企業診断士として現場に立ってきた私の実感としても、「数字の苦手意識が薄れると、経営や生活の選択肢が広がる」という方はとても多いです。
逆に、「知らないまま」にしておくと、無駄な出費や誤った判断につながりやすいのも事実です。
この記事では、数字が苦手な方のために、中小企業診断士の視点で本当に役立つ基本用語とそのポイントを、やさしく解説していきます。
あなたも、ここから「数字が見える安心感」を手に入れていきましょう。

数字嫌いを克服するための心構え
「数字が苦手」という気持ちは、多くの人が持つ自然な感情です。
特に、これまで現場で体感や感覚を重視してきたシニア世代の方にとっては、いまさら数字に向き合うことに抵抗を感じるのも無理はありません。
けれども、最初にお伝えしたいのは、完璧に理解する必要はない ということです。
財務や会計の知識は、専門家のように細かい分析ができるレベルを目指すものではありません。
経営や家計の「状況を把握し、判断する材料」として最低限の言葉と仕組みを知るだけで十分なのです。
たとえば、こんな風に考えてみてください。
• 「読めなくてもいいから、知っている単語が増えるだけで安心」
• 「全部覚えなくても、よく出る3つの用語だけでも意味が分かれば十分」
これくらいの気持ちで始めると、気が楽になります。
中小企業診断士として現場で感じるのは、むしろ「全部覚えようとして挫折する人」が多いということです。
基本は、「わからないことは専門家に任せる。でも、会話の内容が少しわかるだけで、自信が持てる」というレベル感が理想です。
また、財務や会計を学ぶときは、数字そのものではなく「言葉と仕組み」を先に覚える のがポイントです。
いきなり表や計算式を見て嫌になるのではなく、たとえば「利益とは何か」「資産と負債の違い」など、言葉の意味を身近な例に置き換えて覚えるだけで、ぐっと理解が進みます。
数字嫌いを克服する一歩は、「完全にできるようになる」ではなく、「少しでも分かるようになる」。
そんな前向きな気持ちで、次の基本用語の解説に進んでいきましょう。
最低限知っておきたい基本用語10選
ここからは、数字が苦手な方でも覚えやすい、財務・会計の基本用語を厳選してご紹介します。
どれも経営や家計の管理、将来設計の場面でよく出てくる言葉ばかりです。
まずは「聞いたことがある」「意味が少しわかる」というレベルを目指してみましょう。
① 売上(うりあげ)
会社や個人が、商品やサービスを提供して得た金額の総額のことです。
よく「儲け」と混同されますが、売上はあくまで「収入の入り口」であり、ここから経費を引いた金額が本当の儲けになります。
② 経費(けいひ)
売上を得るためにかかった費用のこと。
家賃、人件費、材料費、交通費などが該当します。
「どれだけ経費を抑えられるか」が利益を増やすポイントになります。
③ 利益(りえき)
売上から経費を差し引いた残りの金額。
具体的には「売上 - 経費 = 利益」で計算されます。
会社や家庭のお金が「いくら残るか」を示す指標です。
④ 損益計算書(そんえきけいさんしょ/PL)
一定期間の「売上」「経費」「利益」をまとめた報告書です。
いわば「経営の成績表」。利益が出ているか赤字かが一目でわかります。
⑤ 貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう/BS)
ある時点での「資産」「負債」「純資産」の状況を表す表です。
会社や個人の財産がどのくらいあるか、借金がどれくらいかを確認するのに使います。
⑥ 資産(しさん)
現金や預金、土地、建物など「持っている財産」のこと。
長期的な安定を考えると、資産の内訳を理解することが大切です。
⑦ 負債(ふさい)
借金や未払いの費用など「返さなければならないお金」のこと。
資産と負債のバランスを意識するのが健全な経営や家計の基本です。
⑧ キャッシュフロー
「お金の流れ」のこと。
利益が出ていても現金が足りない、というケースもあり、実際の資金繰りを見るのに役立ちます。
⑨ 固定費(こていひ)・変動費(へんどうひ)
固定費は毎月必ずかかる費用(家賃や人件費)、変動費は売上に応じて変わる費用(材料費など)です。
これを理解するだけでも支出のコントロールがしやすくなります。
⑩ 原価(げんか)
商品やサービスを作るのに直接かかった費用のこと。
原価を正しく把握することで、適切な販売価格や利益率を計算できます。
これらの用語は、難しい計算式や数字を覚える前に、「言葉の意味と役割」を理解するだけでも大きな一歩です。
次の章では、こうした用語を無理なく学び、身につけるための勉強法をご紹介します。

数字が苦手な人におすすめの勉強法
ここまで読んで、「用語の意味はわかったけれど、これからどうやって身につければいいの?」と思われる方も多いでしょう。
数字が苦手な人にとって大切なのは、「無理なく、日常の中で慣れていくこと」です。
ここでは、シニア世代の学び直しにおすすめの方法をいくつかご紹介します。
📖 1. 書籍で用語に親しむ
まずは、やさしい入門書を1冊手元に置き、気になるときに読み返す習慣をつけましょう。
図やイラストが多く、専門用語をかみ砕いて説明している書籍がおすすめです。
特に「図解」や「マンガ形式」の本は、数字が苦手な方でも理解しやすいと評判です。
📝 Amazonで「財務会計 入門」で検索すると、読みやすい本が見つかります。
🎥 2. 動画講座でイメージをつかむ
最近はYouTubeやオンライン講座で、無料・有料の「会計入門講座」が多数公開されています。
動画だと耳と目で覚えられるので、書籍よりもイメージがつかみやすく、挫折しにくいのがメリットです。
1日10分程度の動画から始めると続けやすいでしょう。
🗂 3. 家計や副業の数字で練習する
学んだ用語を、すぐに自分の家計簿や副業の帳簿に当てはめてみましょう。
「売上」「経費」「利益」を毎月の家計で計算するだけでも、理解が深まります。
いきなり仕事で活用するよりも、身近な数字で慣れるのがコツです。
💬 4. 専門家に相談してみる
ある程度用語がわかるようになると、税理士や中小企業診断士など専門家との相談がスムーズになります。
「何を聞けばいいのかわからない」という状態から脱するだけで、経営改善や資産形成の相談がしやすくなります。
数字が苦手でも、こうして少しずつ「見える化」していくことで、不安が薄れ、自信につながります。
ぜひ、今日から一歩ずつ試してみてください。
まとめ:数字が苦手でも一歩ずつ学べば大丈夫
数字が苦手だからといって、財務や会計を避けてしまうのはもったいないことです。
実際に経営や家計の現場では、難しい計算や高度な知識が求められる場面はそれほど多くありません。
必要なのは、基本用語の意味を理解し、数字の「見方」に慣れることです。
今回ご紹介したように、まずは10個ほどの基本用語からスタートし、書籍や動画を活用して少しずつ学び、日常の家計や副業に当てはめてみるだけで十分です。
完璧を目指すのではなく、「少しでもわかるようになる」ことが、数字への苦手意識を克服する第一歩になります。
中小企業診断士としても、多くの現場で「最初の一歩を踏み出した人」の成長を見てきました。
あなたもぜひ、この記事をきっかけに、「数字が見える安心感」を手に入れてください。
一歩ずつの積み重ねが、必ずあなたの自信につながります。
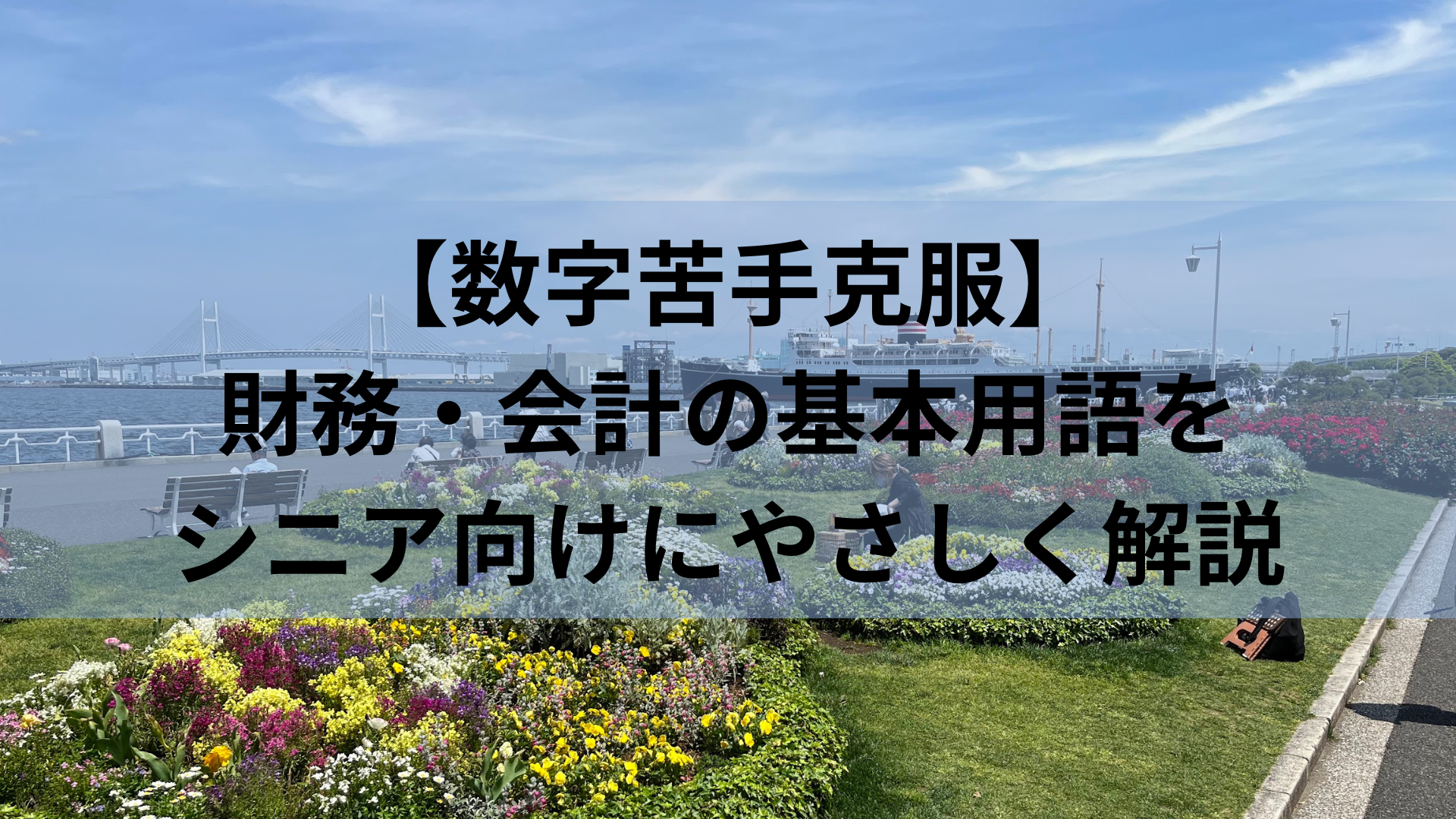


コメント