「経済学だけはどうも苦手…」そう感じていませんか?
50代からの学び直しでは、抽象的で数字の多い経済学は大きなハードルです。
でも、少し学ぶだけで仕事や資産形成に役立つ知識になるのも事実。
本記事では、経済学が苦手な50代が挫折せずにマクロ・ミクロを学び直すコツと、おすすめ教材を診断士の視点で紹介します。
なぜ50代は経済学で挫折しやすいのか?
50代からの学び直しで経済学に挑戦する人の多くが、途中で「難しすぎる…」と感じて手を止めてしまいます。
実際、私自身も診断士試験の勉強を始めた頃に強く感じたのは、数字やグラフ、専門用語の壁でした。50代になると、新しい知識を吸収するスピードが若い頃より落ちていると感じる人も多く、「こんなに難しいのに、本当に自分に必要なのか?」と疑問を持ちやすいのです。
特に経済学は、現実感のない数式や理論が多く、最初の段階で「これは自分には向いていない」と思い込みやすい科目です。
さらに、社会人経験が長いからこそ「現場ではこうだ」という自身の感覚と、経済理論とのズレを感じる場面も出てきます。
この違和感が積み重なると、勉強へのモチベーションは簡単に低下してしまいます。
加えて、50代は仕事や家庭の責任が重い時期です。
限られた時間の中で効率よく学ばなければならないというプレッシャーが、経済学のように一見抽象的で時間のかかる分野では、強い負担に感じられるでしょう。
だからこそ大切なのは、初めから「完璧を目指さない」ことと、最初の一歩にふさわしい教材や学び方を選ぶこと。
無理なく少しずつ理解を積み重ねることで、経済学の魅力が見えてくるはずです。
このあとからは、挫折しないための具体的なポイントや、おすすめの教材について解説していきます。

挫折しないための3つのポイント
経済学の学び直しで大切なのは、「最初のハードルを低くする」ことです。
50代の学び直しは時間や気力が限られるからこそ、無理のないペースで進めることが成功のカギになります。
ここでは、挫折を防ぐために意識したい3つのポイントをご紹介します。
スモールステップで進める
いきなり分厚い専門書に挑むと、高確率で途中で投げ出してしまいます。
まずは薄くて読みやすい入門書や、テーマ別に短くまとめられた解説書などから始めるのがおすすめです。
経済学は「全体像をつかんでから細部を学ぶ」順序が大切ですので、1冊読み切るたびに達成感を味わい、少しずつステップアップしましょう。
成果を実感しながら学ぶ
経済学が現実と結びつかないと感じるのは、学んだことを実生活に活かしていないから。
ニュースや新聞の記事に出てくる経済用語を理解できた、景気動向の意味がわかった、といった小さな成功体験を積み重ねると学習が楽しくなります。
勉強した知識をアウトプットする習慣も効果的です。
仲間やコミュニティを活用する
独学だとモチベーションの維持が難しいこともあります。
そんなときは、同じように学んでいる仲間や、オンラインの学習コミュニティに参加してみましょう。50代同士で悩みや進捗を共有できる環境は、孤独感を軽減し、継続の力になります。
この3つのポイントを意識するだけで、経済学の学びがぐっと楽になります。
次の章では、これらのポイントを実現できる具体的な教材をご紹介します。
50代におすすめの経済学入門書
ここからは、挫折しない学びを実現するために役立つ、50代におすすめの経済学教材をご紹介します。どれもスモールステップで学べる内容なので、経済学が苦手な方でも安心です。
診断士試験の受験生にも評判が高いものを厳選しました。
読みやすい入門書で基礎をつける
✅『中小企業診断士のための経済学入門』(三枝元 著/同友館)
中小企業診断士試験に特化した、数少ない経済学の入門書です。診断士試験に必要なマクロ・ミクロのポイントを、過去問に絡めて平易に解説してくれているので、効率よく学べます。特に「診断士を目指す50代」にとっては、全体像を把握しやすく、現場感覚に沿った説明が多い点も魅力です。
✅『マンキュー経済学入門』(東洋経済新報社)
経済学の定番書で、平易な言葉と事例でマクロ・ミクロを体系的に学べます。分厚い本ですが、最初は関心のある章だけ読むのもOK。
✅『やさしい経済学』(池上彰著/日本経済新聞出版社)
新聞の連載をまとめた形で、ニュースの背景がわかるようになる一冊。通勤や休憩時間の隙間学習にもぴったりです。
✅『今までで一番やさしい経済の教科書[最新版]』(木暮太一 著)
学生や主婦にも人気の経済学入門書。10万部突破の実績があり、専門用語に頼らずイラストや図解でわかりやすく解説。経済の基礎をストーリー仕立てで学べるため、50代にも取り組みやすい一冊です 。
✅『試験攻略入門塾 速習!マクロ経済学/ミクロ経済学 2nd edition』(石川秀樹 著)
中小企業診断士一次試験向けに書かれており、難しい数式を排しグラフや表を多用して視覚的に学べる構成。50代の学び直しにも優しい設計で、動画とセットで取り組むと理解がさらに深まります 。
どれもAmazonなどの通販で手に入り、レビューも高評価です。
特に三枝元先生の本は診断士志望者向けに書かれているので、診断士を目指しているなら最優先で読んでおきたい一冊です。
書籍と動画を組み合わせて使うと、理解が深まりやすくなります。これらの教材は、どれも50代の学び直しに向いており、無理なく続けやすいものばかりです。
次の章では、こうして身につけた経済学の知識が50代にどのように役立つのかを、診断士の視点で解説していきます。

診断士試験を視野に入れた学び直しのススメ
50代から経済学を学ぶなら、単に知識を増やすだけでなく「資格取得」という明確なゴールを設定するのがおすすめです。
特に中小企業診断士試験は、経済学が主要科目のひとつであり、学びの成果が資格という形で残ります。
診断士試験の一次試験では、マクロ経済学とミクロ経済学の両方が問われますが、出題される内容は難解な理論ではなく、実務に役立つ基本的な考え方が中心です。
つまり、50代の学び直しにぴったりのレベル感で構成されているのです。
さらに、診断士資格は合格後の活用方法も豊富です。
企業の経営支援に携わる、セミナー講師として活躍する、自身の投資判断に活かす、など実生活やビジネスで幅広く役立ちます。
経済の仕組みを理解していることが、顧客や同僚からの信頼につながり、キャリアの延長戦に大きな武器となるでしょう。
また、資格試験という具体的な目標があると、学習のモチベーションも維持しやすくなります。
これまで紹介してきた書籍で基礎を固めた後、診断士試験の過去問や問題集に挑戦してみるのも良いでしょう。
実際に出題される問題に触れることで、自分の理解度を測りながら知識を強化できます。
経済学の学び直しは、50代にとってキャリアの選択肢を広げる大きなチャンスです。
ぜひ、診断士試験という「挑戦の場」を視野に入れつつ、無理のないステップで学び続けてみてください。
まとめ|経済学の学び直しは50代からでも遅くない
経済学は、一見難しく感じる科目ですが、正しい学び方と自分に合った教材を選べば、50代からでも無理なく身につけることができます。
今回ご紹介したように、スモールステップで進め、成果を実感し、仲間と学び合うことが継続のコツです。
特に、中小企業診断士試験を目標にすることで、経済学の学びがキャリアや人生設計に直結し、やりがいを感じながら取り組めるでしょう。
50代からでも学び直しは決して遅くありません。
むしろ、豊富な経験を持つからこそ、経済学の知識を現実に活かす力があります。
今日が一番若い日です。
ぜひ、この記事で紹介した入門書や動画講座から、あなたに合った一歩を踏み出してみてください。
経済の仕組みが見えるようになると、仕事や生活がもっと楽しく、充実したものになるはずです。

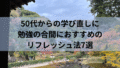
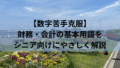
コメント