中小企業診断士として企業の経営課題を分析するには、表面的な数字ではなく「経済の本質」を捉える力が欠かせません。
それは試験の計算問題にも同じことがいえます。
なぜその公式が導かれるのか、どんな理論が背後にあるのかを理解することが、正確かつ柔軟な解答力につながるのです。
この記事では、公式暗記に頼らず理論で理解する学び方をご提案します。
経済公式の本質を理解するメリット
中小企業診断士試験の経済学において、計算問題は合格のカギを握る重要な分野です。
過去問を解いていると、「この公式で計算するだけなのに、なぜか間違える…」という経験をした方も多いでしょう。
その原因の多くは、公式の意味を理解せず、丸暗記で解こうとしている点にあります。
理論がわかると公式が不要になる?
経済学の公式は、単なる数字の操作ではありません。
例えば、価格弾力性の公式一つとっても、需要曲線の傾きや消費者行動の理論を理解していれば、公式が思い出せなくても図や関係性から導き出すことができます。
公式の背景にある理論を理解していれば、途中で数字や公式を忘れてしまっても、問題の文脈や与えられた図から「こうなるはずだ」という方向性が見えるのです。
これは、特に応用問題や初見の問題で大きな強みになります。
本番で応用が効く思考力をつける
診断士試験では、過去問と全く同じ形で出題される問題は少なく、応用力が試される場面が多いのが現実です。
丸暗記に頼っていると、少しでも出題形式が変わっただけで戸惑ってしまうリスクがあります。
理論から理解する学習をしていれば、「問題の本質はどこにあるか」を見抜き、初見問題にも柔軟に対応することが可能です。
これは試験対策だけでなく、将来的に診断士として企業の経営分析や提案を行う際にも役立つ、重要な思考力です。
丸暗記よりも一歩踏み込み、公式の背景にある理論や経済の仕組みを理解することで、計算問題の精度が高まり、応用力も身につきます。
次章では、公式の背景にある理論をどのように学べばよいのか、具体的な学習法をご紹介します。
公式の背景にある理論の学び方
経済公式の本質を理解するためには、ただ公式の定義や計算式を覚えるのではなく、その公式がどのような理論や経済現象を表しているのかを学ぶ必要があります。
ここでは、中小企業診断士試験の受験生におすすめしたい具体的な学び方を3つご紹介します。
需要・供給、限界概念を図で理解する
経済学の多くの公式は、「需要と供給」や「限界概念」に基づいています。例えば、限界費用や限界効用の公式は、それぞれグラフ上の接線の傾きや変化率を意味しています。
公式だけを覚えるのではなく、必ずグラフとセットで学ぶのがおすすめです。
グラフ上でどの部分が計算の対象になるのか視覚的に把握することで、公式の意味が腹落ちし、応用問題にも強くなれます。
📌 ポイント:グラフを書きながら「公式が何を計算しているのか」を言葉で説明する練習をしてみましょう。これだけで記憶の定着度が格段に上がります。
計算過程を言葉で説明する訓練
理論の理解度を高めるもうひとつの方法が「自分の言葉で説明する」ことです。
例えば、「総費用を総生産量で割ると平均費用になる」という計算式の背景を、友人や自分自身に説明する練習をしてみてください。
計算だけで終わらせず、「なぜこの数字を割るのか」「割った結果は何を意味するのか」を言語化することで、理論的な理解が深まります。
これにより、公式を忘れても本質的な計算手順を再現できるようになります。
理論を理解するための参考書や教材を活用する
経済学の理論理解に強いテキストや解説書を1冊用意しておくのもおすすめです。
特に、診断士受験生向けの書籍や講義では、公式の暗記ではなく理論の流れに沿って解説しているものがあります。
また、最近ではYouTubeなどの無料講義動画や、経済学の基礎を学べるオンライン講座も充実しています。
図解や実例を交えて説明してくれる教材を選ぶと、理解がより深まるでしょう。
公式の意味を理解し、理論を身につけることは、診断士試験における計算問題の大きな武器になります。
次章では、この理論理解を過去問演習にどう活かせばよいのか、実践的なアプローチをご紹介します。
理解重視の過去問演習の進め方
公式の本質や理論を理解できるようになったら、次はそれを実戦で活かす練習です。
過去問演習は単なる暗記確認の場ではなく、「理論を使いこなす訓練の場」として活用しましょう。
ここでは、理解重視で取り組むための過去問活用法をご紹介します。
計算式を言い換えて問題を解く
過去問を解く際は、まず公式をそのまま当てはめるのではなく、「この公式が何を求めるものなのか」を確認するクセをつけましょう。
例えば、限界費用の問題なら、「生産量を1単位増やしたときに追加でかかる費用」と言い換えながら計算するのです。
こうすることで、数字の操作だけでなく、理論的に妥当な答えかどうかを判断する力が養われます。
さらに、選択肢問題の場合は、正解以外の選択肢についても「なぜ間違いなのか」を理論的に説明してみると、理解が深まります。
自作問題でアウトプットする
理解度を高めるもうひとつの方法が、自分で問題を作ってみることです。
例えば、過去問の数字を変えたり、状況設定を逆にしたりして、自分なりの問題を作成して解いてみます。
これは「公式の使いどころ」を主体的に考える練習になり、丸暗記では対応できない応用問題にも強くなれます。
間違いノートに理論も書き添える
過去問演習で間違えた問題は、ただ「正しい公式に直す」のではなく、「なぜこの公式を使うべきだったのか」という理論の説明も併せて書き残しておくのが効果的です。
時間が経ってから復習する際も、「背景の理論」まで思い出せるので、知識が定着しやすくなります。
過去問演習は単なる正答率を上げる作業ではなく、公式の背景や意味を確認しながら「理論的な解き方」を身につける場です。
こうした積み重ねが、本試験での柔軟な対応力を生み出します。
まとめ|理論理解で計算問題を得点源に
中小企業診断士試験の経済学における計算問題は、単純な公式の暗記だけでは乗り越えられません。
公式の背後にある経済理論や現象を理解することで、応用問題や初見の出題にも対応できる力が身につきます。
本記事では、公式の本質を理解するメリットとして「応用力が身につく」「公式を忘れても導き出せる」といった診断士的視点を紹介しました。
そして、グラフを活用したり、言葉で説明したりすることで理論を学び、過去問を「理論を確認する場」として活用する具体的な方法をご提案しました。
丸暗記から抜け出し、理論を理解して計算問題に取り組む姿勢は、試験対策だけでなく、診断士としての実務にも必ず役立ちます。
ぜひ今日から、理論理解を重視した学び方で、計算問題をあなたの得点源に変えていきましょう。
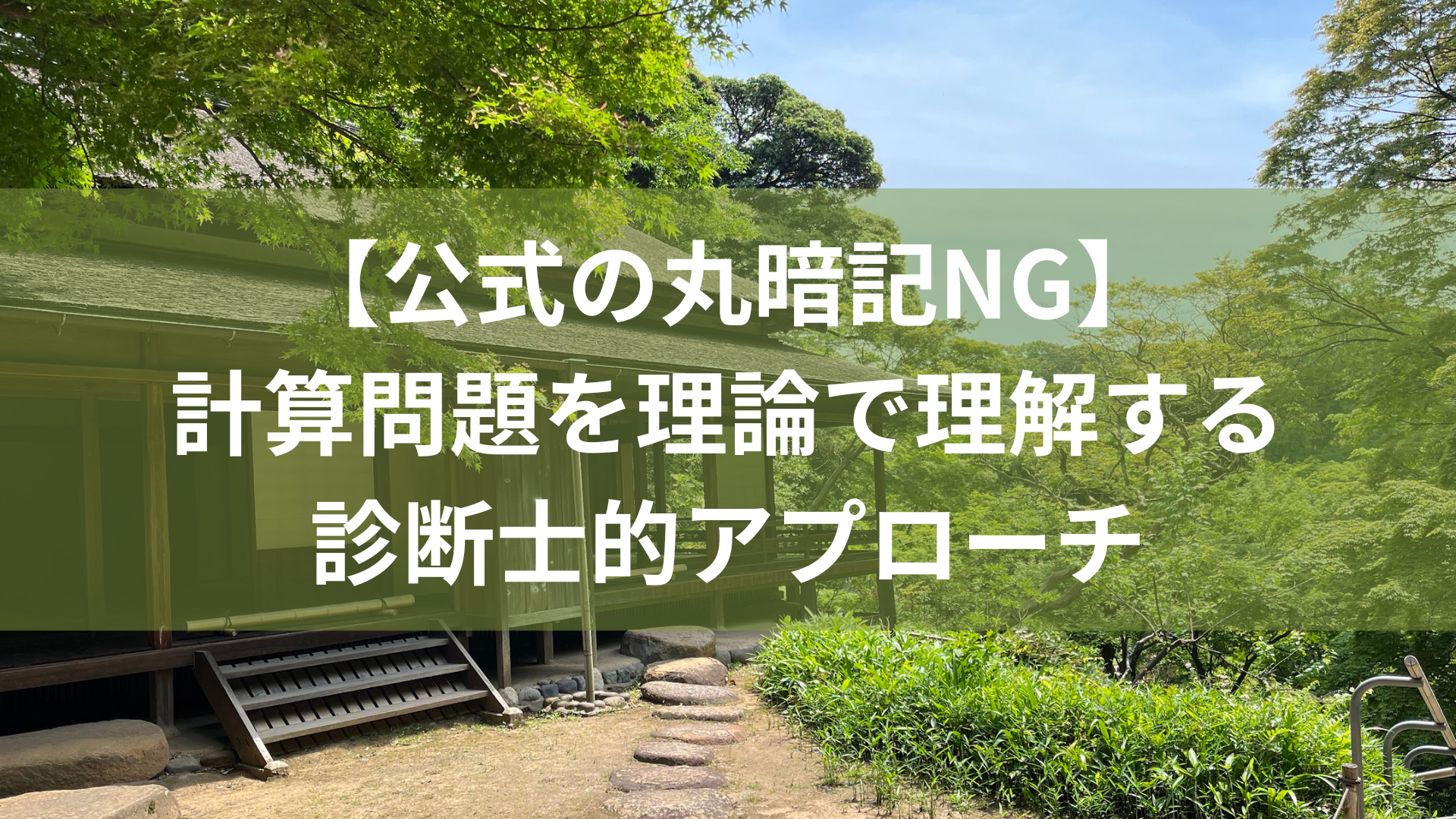

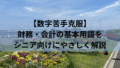
コメント