「講座選び、ちょっと失敗したかも…」
これは、私が50代で診断士試験に挑戦し始めたとき、受講後にふと思った正直な感想です。
年齢的にも“やり直しがきかない”というプレッシャーの中で、講座選びの失敗は痛手です。
本記事では、そんな私の経験をもとに、「シニア世代が講座を選ぶ前に絶対に知っておきたい3つの注意点」を、わかりやすくお伝えします。
なぜ「シニア世代」にこそ診断士講座選びは慎重さが求められるのか
若い頃であれば、多少遠回りしても軌道修正はしやすいものです。
しかし50代、60代になってからの資格挑戦は、“失敗のリカバリーコスト”が圧倒的に高くなります。
私が診断士講座に申し込んだのは、ちょうど定年が視野に入り始めた頃でした。
会社人生を振り返りながら、「次は自分の力で勝負してみたい」と思ったのがきっかけです。
ところが、いざ始めてみると、思いのほか“自分に合っていない”教材や学習ペースに苦しむ日々が続きました。
この経験から気づいたのは、診断士講座は「万人向け」ではないということ。
特にシニア世代にとっては、以下のような要素が講座選びに直結します:
- 学習体力の衰えにどう対応できるか
- 日々の生活習慣に無理なく組み込めるか
- 自分の将来像と学習スタイルが一致しているか
これらを無視して“勢い”や“価格”だけで講座を選んでしまうと、途中で息切れしたり、テキストを開かなくなってしまうことも珍しくありません。
診断士試験は、決して短期決戦ではなく、1~2年にわたる長丁場。
だからこそ、講座選びは「自分自身の再設計」とも言えるほど、慎重さが求められるのです。

受講してわかった!シニア世代が陥りやすい3つの落とし穴
診断士試験の学習を始めてみて、私自身が感じたことがあります。
それは、50代以降の学び直しには、若い世代とはまったく異なる“つまずきやすいポイント”があるということです。
ここでは、私や周囲の受講仲間が実際にハマった「シニア特有の落とし穴」を3つ紹介します。
●落とし穴①:「若者向け設計」の教材が理解しづらい
多くの講座は、20〜30代の会社員をターゲットに作られています。
そのため、スピーディーな映像講義や、スマホ前提の学習設計が中心。
シニア世代にとっては、「速すぎてついていけない」「画面に集中し続けるのがつらい」と感じることも多いのです。
特に講義速度の調整ができない動画や、紙の教材が別売りのコースなどは注意が必要です。
●落とし穴②:「勉強仲間がいない孤独」に負ける
若い世代であれば、SNSや勉強会などを通じて学習仲間を見つけやすい環境にあります。
一方で、シニア層はこうしたコミュニティに馴染めず、孤独な戦いになりがちです。
質問したくても、掲示板の投稿に二の足を踏んだり、オープンチャットの空気に馴染めなかったり…。
こうした孤立感が、モチベーション低下に直結してしまうことは、少なくありません。
●落とし穴③:「使わない機能に課金」してしまう
通信講座の中には、追加料金で模試・アプリ・添削など様々なオプションを提供しているものがあります。
しかし、実際には「使いこなせないまま終わる」ことが非常に多いのです。
特にITに不慣れな世代の場合、活用前提で設計された高機能サービスが“無用の長物”になってしまうことも。
必要なのは、機能の多さではなく「自分が最後まで使いこなせるかどうか」です。
これら3つの落とし穴に共通するのは、「自分の現実的な条件」と「講座の設計」が合っていないこと。
言い換えれば、「合格以前に、継続できる設計になっているか」が最大のポイントです。
次のセクションでは、ではどのように講座を選べば、こうした落とし穴を回避できるのか?
診断士としての視点も交えながら、具体的な選び方を解説していきます。
失敗しない!シニア世代の診断士講座の選び方
シニア世代が診断士試験に挑戦するうえで大切なのは、「無理なく、長く続けられる設計」を持った講座を選ぶことです。
ここでは、50代・60代だからこそ意識すべき講座選びの視点を2つの軸で解説します。
●自分の生活リズムと「学習設計」が合っているか
まず最も重要なのが、日常生活のリズムに無理なく学習が組み込めるかどうかです。
たとえば、
仕事を続けながら勉強する人は「スキマ時間で学べる動画講座」退職後で時間に余裕がある人は「腰を据えて取り組めるテキスト中心型」といったように、自分の生活フェーズに合わせた学習形態を選ぶ必要があります。
また、「週にどのくらいの時間が取れるのか」「朝型か夜型か」といった習慣面の把握も大切です。
「続けられない設計」は、どれだけ質が良くても意味がありません。
●講座以外の“サポート体制”を確認せよ
教材の中身だけでなく、「講座外の環境」も見逃せません。
たとえば、
・質問サポートの回数制限や対応速度
・同世代が参加しやすい勉強会や交流の有無
・学習の進捗管理やモチベーション支援の仕組み
これらは、孤独になりがちなシニア世代にとって非常に重要な支えになります。
特に「途中で学習ペースが崩れたときに、立て直す仕組みがあるかどうか」は、合格までたどり着けるかどうかの分かれ目です。
▼補足:目的に合った「講座タイプ」を選ぶ
また、講座によって力を入れているポイントも違います。
| 目的 | 向いている講座タイプ |
|---|---|
| 独立・副業志向 | 実務直結型・ケーススタディ重視 |
| 企業内昇進志向 | 知識網羅型・理論重視 |
| 教養・学び直し | ゆっくり学べる長期設計型 |
「何のために診断士を取るのか?」を明確にすることも、後悔しない講座選びにつながります。
講座は“教材を買う”のではなく、“未来への環境投資”です。
次章では、その環境投資をどう活かすかを、もう一度まとめてお伝えします。

まとめ|50代・60代の講座選びは「合理性と感性」の両立がカギ
中小企業診断士という資格は、学び直しとしてもキャリアの再構築としても非常に魅力的です。
しかし、講座選びを間違えると、時間・お金・気力のすべてを消耗してしまうリスクがあります。
特にシニア世代にとっては、
- 若い頃のように気合と勢いだけで突破できない
- 一度離脱してしまうと再起が難しい
という現実があるからこそ、最初の講座選びが“命運を分ける”と言っても過言ではありません。
そのうえで大切なのは、「合理性」と「感性」の両方をバランスよく使うことです。
- 合理性=自分の学習環境、習慣、予算、目的に合致しているか
- 感性=「これなら続けられそう」「自分に合っていそう」という直感
シニア世代の講座選びには、この2つの視点を“冷静さと自分らしさ”で見極める力が求められます。
▼最後に|「焦らず、でも妥協せず」に選ぼう
数ある講座の中から、自分にとってベストな一つを選ぶのは、決して簡単ではありません。
ですが、自分の現在地と未来像をしっかり見つめ直すことで、必ず“しっくりくる講座”に出会えるはずです。
あなたの「学び直し」が、人生の新しいステージにつながることを願って――
この記事が、講座選びの一助となれば幸いです。

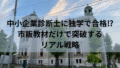

コメント