中小企業診断士2次試験は「実務的な文章力と論理力」が求められると言われますが、実際には事例ごとに評価基準が微妙に異なります。
合格者と不合格者の最大の違いは、この評価基準の“温度差”を理解しているかどうか。
事例Ⅰなら一貫性、事例Ⅱなら因果、事例Ⅲなら網羅性、事例Ⅳなら正確性──。
この記事では、事例別に評価基準を深掘りし、合格答案の条件を明らかにします。
事例Ⅰ(組織・人事)の評価基準
事例Ⅰは「組織・人事」に関する課題解決を問う事例であり、評価基準の中核は一貫性と現実性にあります。
ここでの“一貫性”とは、与件文の事実 → 設問の意図 → 答案の提案が、因果関係でつながっていること。
たとえば「人材流出が続いている」という課題に対し、「人事制度の見直し」を提案する場合、その背景・原因・施策効果が筋道立って説明されていなければ加点は望めません。
もう一つ重要なのが“現実性”です。
診断士試験では、奇抜なアイデアよりも、企業規模や経営資源に適合した施策が評価されます。
与件に「中小規模で予算に制約がある」とあれば、大規模なシステム導入や高額な研修プログラムを提案すると減点対象になる可能性が高いのです。
合格答案の条件は、与件に沿った課題抽出 → 制約条件の明示 → 施策の因果説明を簡潔にまとめること。
特にシニア層の受験者は、自身の実務経験を反映させすぎず、「与件文の世界観」に合わせる姿勢が必要です。
評価基準を意識すれば、書く内容が自ずと絞られ、採点者にとって“採点しやすい答案”になります。
事例Ⅱ(マーケティング)の評価基準
事例Ⅱは「マーケティング・流通戦略」を扱い、評価基準の中心はターゲットの明確化と施策の一貫性です。
特に採点者は、誰に・何を・どのようにというマーケティングの基本3要素が、答案内で矛盾なくつながっているかを厳しく見ています。
まず、与件文にある顧客層や市場特性を正確に読み取ることが前提です。
ここでターゲット像を誤ると、その後の施策提案が全て的外れとなり、大幅な減点につながります。
また、施策の提案は「ターゲットの課題 → 解決策 → 期待効果」という因果構造を明確にすることが必須。
単なるアイデアの羅列や、与件にない情報の盛り込みは減点対象となります。
合格答案の条件は、制約条件を守りつつ、具体的かつ実現可能な施策を提案すること。
例えば、「地域密着型の小規模店舗」という条件があれば、大規模広告や全国展開よりも、地域イベントや既存顧客への販促強化など、スケール感の合った施策が高評価を得やすくなります。
シニア層の受験者にありがちな失敗は、過去のビジネス経験から「理想論」を展開してしまうことです。
評価基準を意識し、与件に書かれた事実を根拠にした論理展開を心がければ、採点者の評価に直結する答案になります。
事例Ⅲ(生産・技術)の評価基準
事例Ⅲは「生産管理・技術戦略」に関する課題解決がテーマで、評価基準の中心は現状分析の網羅性と改善策の実現可能性です。
採点者は、与件文に記載された生産現場の課題をどれだけ正確かつ漏れなく抽出しているかを重視します。
例えば、「工程間の仕掛品滞留」「設備稼働率の低下」など、複数の課題を網羅的に拾い、それぞれに対応策を結びつけることが必要です。
また、改善策は現場の制約条件に適合していることが必須。
中小企業の現場にとって、最新鋭の設備導入や大規模な生産ライン改修は非現実的なケースが多いため、既存設備の有効活用や作業手順の改善、レイアウト変更など、低コストで効果的な施策が評価されます。
合格答案の条件は、課題と施策が一対一で対応していること。
例えば、「生産計画の精度が低い」という課題に対し、「需要予測精度の向上」「工程間の情報共有ルール整備」という具合に、改善策を明確にリンクさせる必要があります。
特に注意すべきは、シニア層受験者がやりがちな「過去の成功事例の押し付け」。
評価基準は与件文内の事実を前提に採点されるため、経験則だけで語ると減点の原因になります。与件に忠実な現場改善提案こそが、高評価につながる鍵です。
事例Ⅳ(財務・会計)の評価基準
事例Ⅳは「財務・会計」の事例で、評価基準の核心は計算精度と説明の整合性です。
採点者は、数値が正しいかどうかだけでなく、その数値を導き出す過程や、背景にある経営判断の根拠まで確認します。
つまり、計算問題と記述問題の両方で高水準を維持する必要があります。
計算問題では、途中式や計算根拠の明示が重要です。
採点者は部分点を与える際に、受験者がどのような思考プロセスを踏んだかを見ています。
正解にたどり着けなくても、与件に沿った数値や適切な計算式が書かれていれば加点の可能性があります。
記述問題では、数値結果と与件文の情報を結びつけた説明が求められます。
「売上高営業利益率の低下」を分析する場合、単なる数値の比較ではなく、「販管費増加による利益率低下」など、因果関係を明確に示すことが高評価のポイントです。
合格答案の条件は、精度の高い計算 + 一貫性のある根拠説明をセットで提示すること。
シニア層受験者は計算速度に不安を抱くケースもありますが、計算ミスを減らすためには、問題ごとの解法手順を型として定着させることが有効です。
評価基準を意識し、計算と文章の両輪をバランスよく磨くことで、得点源に変えることができます。
まとめ|事例別評価基準を理解すれば答案は変わる
中小企業診断士2次試験は、単なる知識再現ではなく、「与件文に沿った論理的な解決策」を評価する試験です。
そして、その評価基準は事例Ⅰ〜Ⅳで大きく異なります。
• 事例Ⅰ:一貫性と現実性
• 事例Ⅱ:ターゲット明確化と施策の因果
• 事例Ⅲ:現状分析の網羅性と実現可能性
• 事例Ⅳ:計算精度と根拠説明の整合性
この違いを理解して答案を組み立てれば、採点者が「読みやすく、評価しやすい答案」に変わります。
逆に、この視点が欠けていると、知識や経験があっても点数に結びつきにくくなります。
特に学び直し世代やシニア層の受験者は、豊富な経験を持ちながらも、与件文とのズレによって減点されやすい傾向があります。
評価基準を踏まえ、与件の世界観に忠実な答案作成を意識することが合格への近道です。
本記事を読んで「自分の答案が評価基準に沿っているか不安…」と感じた方は、過去問演習や模試だけでなく、事例別に解法手順を学べる参考書やオンライン講座を活用してみてください。
理解と実践の両輪がそろえば、答案は確実に変わります。
以下は、事例別の解法手順を体系的に学べる参考書とオンライン講座のご提案です。シニア層の学び直しニーズにも配慮した信頼性ある教材を選びました。
おすすめの書籍(参考書)
- 『2次試験 解き方の黄金手順〈2024‑2025年受験用〉』
事例Ⅰ〜Ⅳまでの与件読解から解答作成までを「黄金手順」として分解・体系化。どの事例にも応用できる安定した解法フレームが身につきます。
- 中小企業診断士 第2次試験 外さない答案への攻略ロードマップ(TAC)
事例ごとの解法プロセスを重視した参考書で、初見問題への感覚を磨ける構成。実戦力を高める練習にも役立ちます。
「まとめシート」流!ゼロから始める2次対策(野網美帆子 著)
設問タイプごとに文章構成を変えるノウハウや、事例別の切り口テンプレートが特徴。解法の型を自分のものにしたい方におすすめです。
おすすめの通信講座・オンライン講座
- アガルート アカデミー
添削付きの2次試験対策パックがあり、記述スキルを合格レベルまで引き上げることに定評あり。段階的に学習を進めたい方に向いています。
- AAS(アウトプット強化型講座)
事例Ⅰ〜Ⅳのアウトプット演習を集中的に強化するコース。過去問および新作問題に取り組みながら、答案作成のリズムをつかめます。
- クレアール(WEB通信)
解法メソッド「ロジカル・チャート」により、事例Ⅰ~Ⅳすべてに共通した構造的・論理的な解法手順を身につけられます。インプットとアウトプットのバランスが良く、過去問演習50回・過去問24年分の練習量が魅力。

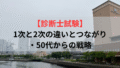

コメント