私は診断士受験生時代、政策分野を「とにかく用語暗記で乗り切ろう」としていました。
ところが本試験では、「施策の背景」「制度の評価」など、一筋縄ではいかない設問に大苦戦。
そのとき初めて気づいたのです——“出題者の意図”を理解していなければ、表面的な知識は通用しないと。
この記事では、私自身の学びをもとに、出題意図を読むための視点とトレーニング法をお届けします。
出題者が問いたい「本当のテーマ」とは?
中小企業診断士試験の政策分野では、単なる施策名の記憶や制度の列挙だけでは通用しない設問が増えています。
これは私自身、受験時に身をもって体験したことです。
たとえば、ある年度の問題で「中小企業の事業承継を支援する施策」として出題された設問がありました。
私は事業承継税制や補助金名をいくつか思い出し、選択肢を処理しました。
しかし、実はその設問の本質的な問いは「高齢化社会における円滑な世代交代」という政策的課題に対し、国がどうアプローチしているか、という背景と狙いを理解していなければ、正答にたどり着けない構造だったのです。
こうした問題を読み解くうえで、出題者が本当に問いたいテーマは、主に以下の3点に集約できます。
● ① 社会的背景や課題への理解
政策は「時代の課題」に応じて設計されています。
たとえば、地方創生、デジタル化対応、カーボンニュートラル支援といったトピックは、国全体の構造的問題(人口減少、DXの遅れ、気候変動など)と結びついています。
出題者は、こうした背景を理解しているかを選択肢の文脈やニュアンスを通して探ってきます。
単なる「制度の名前」ではなく、「何のために、誰のために導入された施策なのか」という読み解きが必要です。
● ② 政策目的と手段の関係性
たとえば、「中小企業のデジタル化支援」と言っても、目的は単にITツールを配ることではありません。
「生産性の向上」「競争力強化」「業務効率化による人手不足対策」など、目的 → 手段のロジックが設問の背後に隠れていることが多いのです。
出題者は、こうした因果関係を受験生がつかめているかを、あえて似たような施策を並べたり、誤った因果関係を示した選択肢を用意することで試しています。
● ③ 政策効果の評価や今後の展望
近年では、「この施策は一定の成果を上げた」といった文脈で、制度の“その後”にまで言及する設問も増えています。
これは、診断士として“政策を理解して終わり”ではなく、“評価し活用する立場”であることを前提とした問われ方です。
つまり出題者は、制度そのものよりも制度の意味や実効性、今後の動向といった、より広く深い理解を求めているのです。
このように、試験問題は表面上の知識を問うているようでいて、実際は「社会の動き」「政策の本質」「未来への洞察」といった、思考力や政策感覚を試しています。
次のパートでは、実際の過去問を取り上げながら、出題意図をどう読み解くかのトレーニング方法を紹介します。
過去問から学ぶ“意図のパターン”分析
出題者の意図を見抜く力は、過去問分析から身につけるのが最も効果的です。
ここでは令和以降に出題された中小企業政策分野の問題をもとに、出題の背景や意図が見えやすい特徴的な設問をいくつか取り上げ、そのパターンを分析してみましょう。
● 事例①:令和4年度 第18問(中小企業白書・事業再構築)
設問概要:
「中小企業白書に基づく記述文の正誤を問う設問。ポストコロナの企業支援施策に関する出題。」
この問題は、事業再構築補助金などの個別制度を問うように見えて、実際は「国が中小企業の構造転換をどのように促そうとしているか」という施策全体の方針が問われていました。
• 単なる制度名の暗記ではなく、
• なぜそのような支援が必要になったか、
• どんな企業を対象にしているのか、
といった文脈を理解していないと、細かな選択肢のひっかけに対応できません。
▶ パターン分類:
「個別制度の背景にある政策意図」を読む必要があるタイプ。
● 事例②:令和3年度 第19問(中小企業憲章と中小企業基本法)
設問概要:
「中小企業政策の基本理念に関する理解を問う問題。」
この問題では、中小企業基本法の目的や中小企業憲章の理念が問われましたが、表面的な条文の暗記では対応が難しい設問でした。
キーワードとしては「多様で活力ある中小企業像」や「地域社会への貢献」などが登場し、それらが国の政策立案にどう結びついているかを問う文脈が設定されていました。
▶ パターン分類:
「理念・方針→施策」の因果を問う抽象度の高いタイプ。
● 事例③:令和2年度 第17問(働き方改革と中小企業)
設問概要:
「中小企業における働き方改革推進施策に関する内容を問う設問。」
この年の問題では、働き方改革に関連する制度の羅列ではなく、中小企業の現場における実態と政策の効果・限界について触れた内容が含まれていました。
「制度の導入=すぐに解決」という単純な構図ではなく、「制度はあるが定着に課題がある」ことを前提とした選択肢も存在し、“現実を見据えた政策評価”の視点が求められました。
▶ パターン分類:
「制度の運用上の課題・実効性」を意識させる現実重視タイプ。
● 共通する出題傾向と“読み取りのコツ”
上記のような設問に共通する出題者の意図は、以下の3点に整理できます:
1. 制度を生み出す背景や問題意識を理解しているか?
2. 政策目的と施策内容の整合性を読み取れているか?
3. 制度の意義・課題・今後の展望まで考えられているか?
このような問いに対応するには、「制度そのもの」ではなく、「制度が投げかける問い」や「制度の裏側」に注目して過去問を読み直すことが効果的です。
次のパートでは、こうした出題意図を意識した実践的なアウトプットトレーニング法をご紹介します。
答える力を養うアウトプットトレーニング
出題者の意図を読み取る「インプット」だけでは、本試験で安定した得点は望めません。
なぜなら、本番で求められるのは「問いの背景を正確に読み取り、最適な選択肢を選ぶ」アウトプットの実践力だからです。
このパートでは、政策問題に対して「ただ知っている」から「正しく答えられる」へとステップアップするための、具体的なトレーニング法をご紹介します。
● 要点を“自分の言葉で”5行にまとめる訓練
政策関連の文章を読んだり、施策を調べたりしたあと、ぜひ行ってほしいのが「5行要約法」です。
• ① その施策の目的は何か
• ② 対象はどのような中小企業か
• ③ どんな支援内容があるか
• ④ どのような課題に対応しているか
• ⑤ 成果や今後の課題は何か
この5つの観点を「自分の言葉」で要約しておくことで、記憶にも残りやすく、設問文を読んだときに背景を想起する力がつきます。
● 選択肢を“逆から読む”思考トレーニング
過去問や予想問題を解く際、正解を選ぶだけで終わっていませんか?
ここで一歩踏み込んで、「出題者はなぜこの選択肢を作ったのか?」という視点で逆解析を行ってみましょう。
たとえば、不正解の選択肢に
「〜という支援は現在は終了している」
という文言があれば、次のように考えられます。
• 「施策の“継続性”に注目させたい意図か?」
• 「受験生が古い知識のまま覚えているかどうか試している?」
• 「制度の背景を知らず表面的に記憶しているとミスする構成だな」
こうした“逆読み”を日々の演習で意識することで、選択肢の罠にかかりにくくなり、問題文全体の構造や狙いが見えるようになります。
● 政策に“自分の意見”をもつ習慣を
実務でも試験でも、「なぜこの制度が導入されたのか?」「どのような中小企業にとって有効か?」という仮説思考が求められます。
そのため、日頃から政策ニュースや白書の内容に対して、「私はこう思う」という視点を持つ習慣が非常に有効です。
診断士の学習者であっても、たとえば以下のような一文を書き出してみることをおすすめします:
• 「この施策は地方企業の人材確保という課題に対して有効だと思う」
• 「一方で、制度利用のハードルが高く、資源の乏しい小規模事業者には恩恵が届きにくいのではないか」
このように、制度に対して批判的かつ建設的な視点を持つことが、実務的思考力にも直結し、二次試験以降にも活かされていきます。
以上のようなトレーニングを積むことで、政策問題に対する“答える力”は確実に向上します。
暗記頼みの学習から一歩抜け出し、「なぜ問われているのか?」に答えられる診断士らしい思考を手に入れましょう。
まとめ|“政策問題=暗記”という思い込みを超えて
中小企業診断士試験の政策分野は、つい「制度名を覚える科目」と捉えがちです。
しかし近年の出題傾向を見れば明らかなように、本当に問われているのは“制度の意味”や“背景にある政策的課題”への理解力です。
この記事では、以下の3つの視点から出題者の意図を読み解く訓練法をご紹介しました:
• 政策の背景や社会的文脈に注目する
• 過去問を“構造”で読み直し、出題のパターンを見抜く
• アウトプット重視の要約・逆読みトレーニングを習慣化する
これらは、単に試験対策にとどまらず、診断士としての実務力を養う訓練にもなります。
制度を「覚える対象」から「考える材料」へと変えることで、学びはより深まり、実務でも通用する“政策リテラシー”が身についていくでしょう。
「出題者の視点」で問題を見ることは、合格への近道であると同時に、資格取得後に求められる姿勢そのものでもあります。
今日からぜひ、政策を“読む目”を育てる学習を始めてみてください。
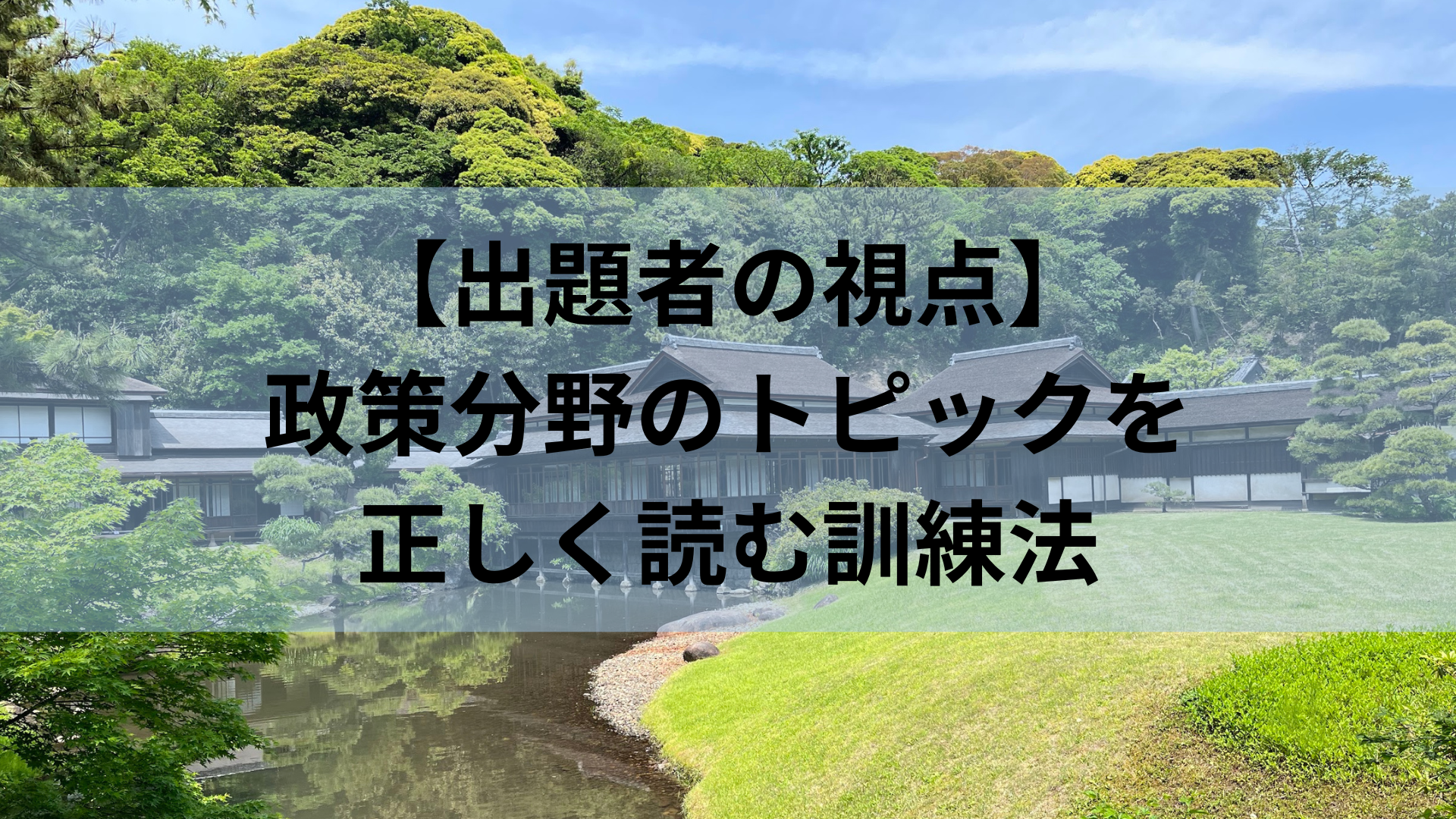

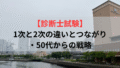
コメント