「読む時間がない」「どこが重要かわからない」。
そんなあなたに向けて、中小企業白書を“30分で要点把握”する方法をまとめました。
特に1次試験の企業経営理論や、2次試験の事例分析に効く「白書の使い方」にフォーカスし、効率的な学習法をご紹介します。
忙しい50代学び直し世代にもおすすめの内容です。
中小企業白書は1次試験でこう出る!過去問分析
中小企業白書は、実は中小企業診断士1次試験の「企業経営理論」や「経営政策」において、頻出テーマの情報源として利用されています。
毎年出題されるとは限りませんが、「出る年はピンポイントで数字や用語が問われる」ため、白書の扱い方ひとつで得点に差がつく部分でもあります。
■ 出題例①|企業経営理論における「中小企業の定義」や支援施策
たとえば令和元年度の企業経営理論では、「中小企業基本法における中小企業の定義」に関する設問が出題されました。
これは中小企業白書の「冒頭部分」や「付録データ」に毎年掲載されている内容で、年度ごとに更新される基準値(資本金・従業員数など)が正確に問われます。
また、経営支援・政策支援に関する用語や分類(例:小規模事業者持続化補助金や事業再構築補助金)が問われることもあり、これは白書の政策パートを見ておけばしっかり対応できます。
■ 出題例②|経営政策分野におけるトレンド用語・重点施策
経営政策の設問では、政府が重視する中小企業支援策や地域活性化の方向性について出題されるケースがあります。
令和4年度には、「事業承継・M&Aに対する支援策」が選択肢として登場しました。
これは、中小企業白書で近年特集的に取り上げられているテーマであり、読んでいればスムーズに選択できる内容です。
■ 出題の“傾向”をつかむコツ
過去問を分析すると、白書からの出題には次のような特徴があります。
• 「数字」や「定義」を正確に覚えているかが問われる
→ 試験直前に付録データだけ見直しておくだけでも得点に直結。
• 「トレンド用語」や「施策名」の知識が問われる
→ 最新の白書で使われている表現や用語を見ておくことで選択肢を正しく判断。
• 毎年出るわけではないが、出たときは配点が高め
→ 出題リスク管理の観点から“捨てない方が良いパート”として対策するのが賢明。
■ 結論:白書を「全部読まなくても」対策は可能
1次試験対策としては、「中小企業の定義」「支援策」「最新トレンドのキーワード」に絞って、白書の該当箇所だけピックアップして読むだけで十分です。
特に試験直前期には、過去問で出題された箇所を白書上で確認しながら読み返すと、記憶の定着にも役立ちます。
次のセクションでは、2次試験や実務補習の現場で、白書がどのように活用されるのかを解説します。

2次試験・実務補習における白書の活用事例
中小企業白書は、1次試験だけでなく、2次試験や実務補習においても“実務的背景知識”として非常に有用です。
特に、記述式で中小企業の課題や施策を論じる場面では、白書の内容が“思考の軸”として活きてきます。
■ 2次試験:与件文の“背景理解”と「助言の引き出し」に
2次試験では、与件文の中に明確な課題やヒントが散りばめられている一方で、解答では「どのような施策を提案するか」という実務的な視点が求められます。
ここで中小企業白書を読んでおくと、
• 「現在の中小企業が直面している構造的課題(人材不足・事業承継・デジタル化対応など)」
• 「国や自治体が推進している支援策」
を踏まえて、より現実的かつ説得力のある助言文を書くことが可能になります。
例として、令和5年度の事例Ⅱでは「地域密着型の小売業」に関する設問がありましたが、白書の「地域商業の再構築」「デジタル販促支援」などの知見がそのまま助言の根拠になり得ます。
■ 実務補習:報告書・発表資料の論拠として引用可能
実務補習においても、中小企業白書は現場での“診断の裏付け資料”として頻繁に活用されます。
報告書や発表スライドで、
「全国的な傾向として●●業界では××が課題となっている(中小企業白書○年版より)」
と記述することで、診断や助言の信頼性が大きく向上します。
特に次のような場面で引用価値が高まります:
・業種別の生産性や従業員数などの統計データを示す場面
・施策提案の際に、国の方針と整合性をもたせる場面
・地域経済や業界全体のトレンドを客観的に提示する場面
■ ポイント:最新年度の白書を使うことが重要
白書は毎年発行されるため、できるだけ最新の年度版を参照することが大前提です。
古いデータや政策を用いると、実務補習指導員や試験官に「情報感度が低い」と判断される可能性もあります。
特に実務補習では、「中小企業庁の見解を踏まえたうえでの提言」が重視されるため、白書を日頃から読み慣れておくことは、診断士としての信頼を高める武器になります。
■ 結論:2次・実務では「白書を知っているだけで」差がつく
2次試験や実務補習は、単なる知識の暗記ではなく、「中小企業支援のリアリティ」が問われる場です。
白書にはそのリアリティが詰まっており、読むだけで“中小企業の現場感”が身につく教材とも言えます。
次章では、こうした出題や実務で問われやすい「定番テーマ」や「今年の注目ポイント」について、具体的に見ていきます。
出題されやすい「定番テーマ」と今年の注目ポイント
中小企業白書は、試験でも実務でも活用される「政策と現場をつなぐ資料」です。
とはいえ、すべてのページを読むのは現実的ではありません。
診断士として押さえておきたいのは、“出題されやすい定番テーマ”と“その年ごとの注目分野”です。
ここでは、過去10年の白書の傾向と、2025年版で特に注目すべきポイントを解説します。
■ よく出る!中小企業白書の「定番テーマ」3つ
過去の1次・2次試験や実務補習を分析すると、毎年のように扱われる“鉄板ネタ”があります。
1. 人手不足と人材確保
特に小規模事業者にとっての人手不足問題は、慢性的かつ深刻な経営課題として長年取り上げられています。
→ 働き方改革、デジタル人材の育成、シニア・女性人材の活用などがセットで登場。
2. 事業承継とM&A
経営者の高齢化に伴う承継問題は、今や全業種共通の経営リスクです。
→ 家族内承継、第三者承継、後継者教育など多角的な視点が求められます。
3. 地域経済と商店街・観光・地場産業支援
地域創生の文脈で、商店街の再生や観光資源活用による地域活性化も頻出。
→ 地域密着型ビジネスの戦略立案や、官民連携の視点が出題されることも。
■ 2025年版の注目キーワードとトピック
2025年版白書では、以下のようなテーマが特に力を入れて取り上げられています。
◉ 「GX(グリーントランスフォーメーション)」の推進
→ 中小企業にとっても、脱炭素対応や省エネ投資が不可避のテーマに。
→ 具体的な補助制度や先進事例も掲載されており、実務にも直結。
◉ 地域の“稼ぐ力”強化(ローカル経済圏)
→ 地元資源×デジタル×観光×外貨獲得をキーワードに、地域戦略型支援の事例が豊富。
→ 特に地域活性・6次産業化を扱う問題に活かしやすい内容。
◉ 生成AIや業務効率化の最新動向
→ ChatGPTをはじめとする生成AIの中小企業活用が特集され、業務改善やマーケティング活用事例が紹介。
→ IT導入支援策やDX戦略と絡めた出題も想定される。
■ 対策のポイント:テーマごとに「事例」と「数字」を押さえる
白書に出てくるキーワードは、「なんとなく見たことある」では得点に結びつきません。
テーマごとに次の2つを意識して学習・活用するのが効果的です。
1. 代表的な実例(モデル企業)や支援策名を把握する
→ 具体名を助言や報告書に盛り込めば説得力アップ。
2. 関連する統計データ・数字もセットで覚える
→ 出題の多くは“数値の正誤判定”や“実態の理解度”を見ています。
次のパートでは、こうした定番テーマや注目ポイントを効率的に押さえるための「白書の読み方」や「時短術」について解説します。

おすすめの読み方と資料活用法
試験対策や実務補習で中小企業白書を有効活用するには、「効率的な読み方」と「関連資料の活用」が鍵となります。
ここでは、学習効果を最大化しつつ、診断士視点で読解を広げる方法をご紹介します。
■ 白書を効率的に読むためのステップ
➊ 目的別に読む章を絞る
1次試験対策なら「定義・統計・支援策」、2次試験・実務なら「具体事例・トレンド論点」に注目。
最新版である2025年版白書(2025年4月発表)は最優先で確認すべきです 。
➋ 図表や巻頭要約から先行して読む
多くの読み手は本文に時間を使いがちですが、巻頭要約と主要図表だけでも、試験頻出テーマや政策背景がざっと把握できます。
➌ “出題例→白書確認”で逆引き学習
過去問に登場した用語や数字を白書で確認すると効率的。例えば、事業承継やGX、生成AI関連は出題されやすいトピックです 。
➍ メモとマーカーで自分用索引を作る
章ごとにキーワードや数字をまとめた索引ノートを作成し、後から資料検索しやすくするのがポイント。
■ 診断士学習におすすめのAmazon書籍
試験対策として白書を効率的に学ぶなら、以下の書籍が有効です。
• 中小企業白書・小規模企業白書2025年版(上巻) 中小企業庁発行、2025年版の〈上巻〉。
A4判全460ページで「経営力」「スケールアップ」など最新の経営トレンドと政策動向を網羅。信頼性が高く、実務や2次試験の背景知識としても活用可能です。
• TBC 特訓問題集〈1〉 中小企業白書(最新版)
2025最新版対応の特訓問題集。白書の要点を択一・穴埋めで確認でき、動画講義や過去問解説も付いているため、独学でも効率よく学べます 。
■ 書籍と白書PDFの併用が効果的
- 書籍で「概要と頻出テーマ」を素早くインプット
- 白書PDF(中小企業庁公式サイト)で必要なページの参照・図表確認
- 過去問で出題された数字・キーワードを書籍 → 白書で検証する流れを習慣化
この組み合わせにより、「必要な情報だけ効率よく拾う力」が自然と養われます。
■ 実務補習や助言文に活かす応用法
- 白書の事例引用に関しては、支援策名や統計データを報告書・助言文に明記することで信頼性が高まります。例えば、「GX補助制度」「地域創生M&A支援」などの言及が有効です。
- 報告用スライドやレジュメに図表を転写することで、説得力のある資料に仕上がります。
このように、白書の「読む→理解→活用」の流れを明確化し、書籍を適切に取り入れながら学習を進めることで、シニア層の受験・実務力強化につながります。
まとめ:白書は「読める」と強みになる、診断士の必携ツール
中小企業白書は、そのボリュームから敬遠されがちですが、実際にはポイントを絞れば30分でも要点を把握できる強力な資料です。
診断士試験においては、1次試験の「定義・支援策」、2次試験の「助言の引き出し」、そして実務補習の「根拠資料」として活用されるなど、学習・実務の両面で差がつくツールといえるでしょう。
特に2025年版では、「GX(グリーントランスフォーメーション)」や「生成AI」など、これからの中小企業支援で不可欠となるテーマが多数盛り込まれています。
これを活かせば、診断士としての提案力・現場対応力にも厚みが出てきます。
忙しい方や独学の方でも、まずは「巻頭要約」「図表」「定番テーマ」だけでもOK。
紹介した書籍や過去問と組み合わせて、自分なりの「読み方ルール」を確立することが、白書を得点源・実務力源に変える第一歩になります。
「全部読む」ではなく、「使いこなす」。
それが、中小企業白書を味方につける診断士の姿勢です。
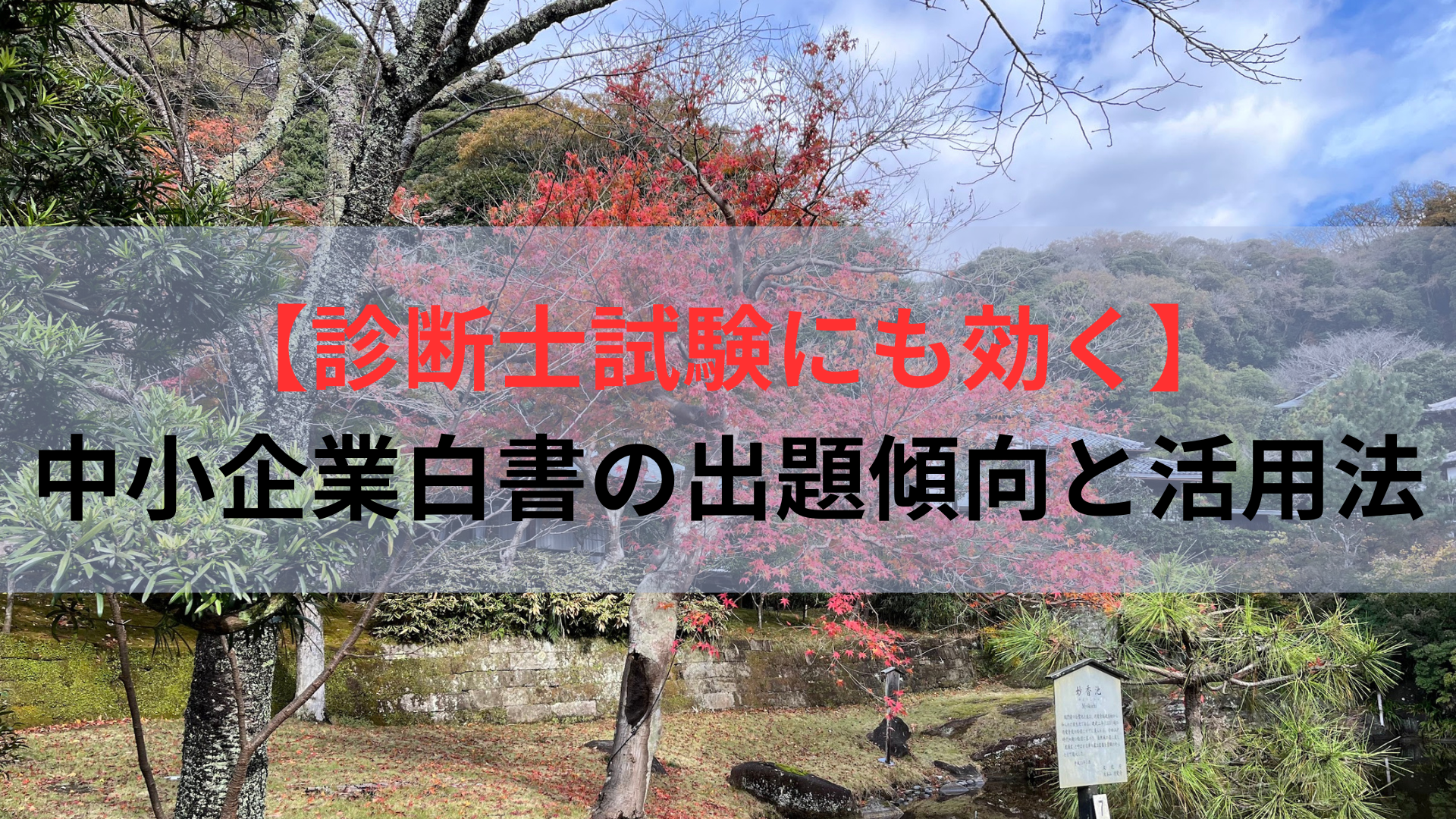
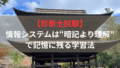
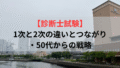
コメント