中小企業診断士試験の法務科目では、知識の正確さだけでなく“知識同士の関係性”を問う問題が増えています。
たとえば知的財産と支援施策、会社法と機関設計――一見バラバラな分野が「つながり」で出題されるのです。
この記事では、法務を単なる暗記科目にしないための“診断士的なアプローチ”として、つながり記憶術と出題傾向の見抜き方をお伝えします。
法務の得点を伸ばすカギは“つながり”にあり
バラバラの知識をつなげることで記憶に定着
法務科目の学習では、条文の暗記や制度の定義ばかりに意識が向きがちです。
しかし中小企業診断士試験で問われるのは、単なる知識量よりも「知識間のつながり」をいかに理解しているか、という点に重きが置かれています。
たとえば、「著作権」と「中小企業支援施策」の関連、「会社法」と「機関設計の選択肢」の組み合わせなど、複数のテーマが1つの設問に集約される出題が目立ちます。
知識同士の「関係性」を意識することで、学習効果は飛躍的に高まります。
なぜなら、つながりは“記憶のフック”として機能し、単発の用語よりも長期的に頭に残るからです。
これは心理学的にも裏付けがあり、人間は「文脈」や「関連性」をもった情報のほうが記憶しやすいという特徴があります。
つまり、つながりを意識した法務の学習は、単なる試験対策にとどまらず、実務での判断力や法的感覚を育てるトレーニングにもなるのです。
法務は「分類」と「関連」が命
診断士試験の法務は、民法・会社法・知的財産権・下請法・独禁法・支援施策と、範囲が広く、しかも一見すると断片的に見えるのが特徴です。
ですが、これらはすべて「分類」と「関連」で体系化できます。
• 民法と会社法は、企業活動の“契約”と“組織”を支える法的基盤
• 知的財産権は、製品・ブランドなど無形資産の“保護”に関する法律
• 下請法・独禁法・中小企業施策は、“取引の公正”や“競争の健全化”を扱う制度群
こうした分類のもとに「この法律はどこで何のために機能しているのか?」という視点を持つことで、法務全体が1枚の地図のようにつながってきます。
さらに、実際の設問では「複数の法分野が横断的に出題される」傾向が強くなっています。
したがって、知識を“点”で覚えるのではなく、“線”や“面”として結びつけることが、得点源化への最短ルートになります。
出題の“つながりパターン”を押さえる
知的財産権と中小企業支援施策のリンク
診断士試験では、単なる知的財産権の定義を問う問題よりも、「その権利が実務でどう活用され、どのような支援制度と結びついているか」に焦点を当てた出題が増えています。
たとえば、以下のような“つながり”がよく狙われます。
• 商標登録の支援 = 都道府県のよろず支援拠点や知財総合支援窓口との連動
• 知財を活用した経営戦略 = 経営資源引継ぎ補助金や事業再構築補助金との関係
これらは、実際の中小企業支援に関与する中小企業診断士としての視点を持っていれば、より深く理解できる分野でもあります。
知的財産権の制度だけでなく、関連する中小企業施策とセットで覚えることで、出題者の意図を読みやすくなり、正答率が上がります。
会社法と機関設計の定番問題
会社法の分野では、「取締役会」「株主総会」「監査役会」などの機関の役割や組み合わせに関する出題が頻出です。
ここで問われるのは、“どの形態の会社がどの機関設計を選べるのか”、“義務なのか任意なのか”という“ルールの整理”だけではありません。
例えば、出題者はこうした背景知識に加えて、
• 「指名委員会等設置会社」と「監査役会設置会社」の違い
• ベンチャー企業における意思決定の柔軟性とガバナンスとのバランス
といった“実務的視点”を問う形で設問を構成してきます。
つまり、「会社法」単体ではなく、「組織設計」「ガバナンス」「コーポレート戦略」など、経営理論ともつながる文脈で捉えることが、応用問題への対応力につながるのです。
民法と契約書の設問との連動
民法の出題は、かつての“用語の定義暗記”から、近年は“契約書の具体的な内容”と結びついた応用問題へとシフトしています。
とくに注意したいのが、「契約の成立要件」「解除要件」「損害賠償」などのルールを、ビジネス上の契約文脈に当てはめさせるような設問です。
たとえば、次のような問いが典型です。
• 「この契約条項は有効か?無効か?」という判断を求める問題
• 「契約解除にあたり、どの条文が適用されるか?」を推測させる問題
このタイプの設問では、“民法の知識”と“ビジネス文脈”を結びつける力が求められます。
一方で、契約書の読み方や条項の意味をざっくり理解しておくだけでも、大きなアドバンテージになります。
中小企業診断士としての将来的な実務にもつながるため、単なる暗記ではなく「使える法務知識」として習得しておく価値の高い領域です。
得点源に変えるための「3つの記憶フック」
視覚化(マインドマップ・図解)
記憶の定着において非常に効果的なのが「視覚化」です。とくに法務のように抽象的な概念が多い科目では、知識の構造を“見える化”することで理解が飛躍的に深まります。
たとえば、次のような図解・マインドマップが有効です。
• 知的財産権の種類と保護対象の対応関係(商標・特許・意匠・著作権)
• 会社の機関設計パターンと必要な設置要件
• 民法の契約フローとトラブル発生時の対応法(解除・損害賠償など)
こうした図解は、単なる暗記から「構造理解」へとシフトさせ、思い出すときにも“全体像 → 細部”の順で思考できるため、選択肢の消去や誤り発見にも効果的です。
自作でも構いませんし、市販の図解教材を活用するのもよいでしょう。
語呂合わせとストーリー化
法務の条文や制度の番号・要件は、ややこしいものが多く、丸暗記しようとするとすぐに忘れてしまいます。
そこでおすすめなのが、語呂合わせやストーリー化による記憶術です。
たとえば:
• 「意匠・商標・特許の保護期間」を「意商特(いしょうとく)で、意(い)じょうにショックなトッキュー隊」と覚える
• 「取締役会の設置要件」を「資本金1億、役員3人、監査役1人」として“社長と2人の副社長、見張りの監査役”というイメージにする
記憶の定着には、“個人的に面白い”や“印象に残る”が何より重要。
自分なりのオリジナル語呂や事例を作っておくと、試験中にもスムーズに思い出せる「フック」として機能します。
過去問パターンと法改正のセット覚え
中小企業診断士試験の法務では、「頻出パターン」と「最新法改正」が融合した出題が非常に多く見られます。
過去問を分析すると、以下のような特徴が見えてきます。
• 知財分野では、「改正著作権法」が出た翌年にAI創作物やネット配信に関連した設問が登場
• 会社法では、「株式の譲渡制限」や「取締役の任期」に関する改正直後に具体例付きの問題が出題
• 民法では、「契約解除のルール変更」後に、典型トラブル形式の事例問題が登場
つまり、法務は「過去問をなぞるだけ」では不十分で、過去問パターン+法改正の組み合わせで学ぶことが重要です。
過去に出たテーマに、最新の法改正がどう影響しているかを意識するだけで、得点力は大きく変わります。
おすすめの記憶補助グッズ・教材
シニア世代にも扱いやすく、法務の「つながり記憶術」を補強できる実在の教材・グッズを以下にご紹介します。
Amazonなどと連携した収益導線設計に最適です。
図解・まとめシート型教材:『一次試験一発合格まとめシート(2025年度版)』
野網美帆子氏が著者のこのシリーズは、経営法務を含む診断士一次科目を頻出論点と関連性に基づいて1枚に整理したまとめシートです。
優先順位×頻出度で視覚的に学習でき、つながり記憶にも最適です。
PDFやインデックスシールの特典付きで利便性も高く、特にシニア層の「全体を俯瞰したい」ニーズにも応えます。
テキスト+図解講座型:スタディング中小企業診断士講座
スタディングは学習マップ(ビジュアル地図型テキスト)を中心に、法務を体系的に整理して記憶補助をサポートします。
講義ごとに設計されたチェックテスト(記憶フラッシュ)を活用することで、理論を視覚的に定着させながらアウトプットも同時進行でき、効率的な記憶形成に役立ちます。
記憶術に強い自己学習系書籍:『トニー・ブザン 天才養成講座 マインドマップ記憶術』
マインドマップの創始者トニー・ブザン氏が提唱する記憶術の教本です。
キーワードの放射状整理、色分け、関連性の視覚化などは、法務のつながり記憶にも非常に有効です。シニアにもわかりやすい形式で、法務分野の図解と組み合わせることで自作マインドマップ教材として活用できます。
記憶術実践本:『世界最強記憶術(場所法/ストーリー法)』
記憶の連鎖を活用したチェインメソッドや場所法を用いた記憶術を解説した書籍です。
法務の条文や要件をストーリー化することで、「なぜこの要件があるのか」を理解しながら記憶でき、単なる丸暗記より長期記憶向きです。
条文要素を物語やイメージに結びつける方法として活用可能です。
📊まとめ比較表
| 教材名称 | 特徴 | シニア視点での利用メリット |
|---|---|---|
| まとめシート(2025年版) | 頻出論点を1枚で図解・整理 | 全体像把握が容易、持ち歩きやすい |
| スタディング講座 | 講義+学習マップ+テスト一体型 | 音声教材対応/繰り返し学習に最適 |
| マインドマップ記憶術本 | 図解・色彩で関連整理 | 法務分野の構造理解をサポート |
| 世界最強記憶術(場所法) | チェイン・場所法など記憶法 | 条文要件を覚えやすくストーリー化可能 |
まとめ|法務は“つながり”で得点源に変わる
中小企業診断士試験の法務科目は、範囲が広く用語も難解なため、苦手意識を持ちやすい科目のひとつです。
しかし、その本質は「知識の網をどれだけ広げて張り巡らせるか」という“つながり力”にあります。
法律同士の関係性や、実務や支援施策との接点を意識すれば、暗記に頼らず理解ベースでの学習が可能になります。
また、マインドマップやストーリー法など、記憶を助けるツールを活用すれば、年齢に関係なく記憶力を補えるのも大きな利点です。
重要なのは、“一問一答で覚える”のではなく、“一問多答で思い出す”力を鍛えること。
つながりを意識して学べば、法務はあなたにとって「得点源」に変わります。
これから学習を進める皆さんも、ぜひ「記憶のフック=つながり記憶術」を意識して、効率的かつ実践的な理解を積み重ねていってください。
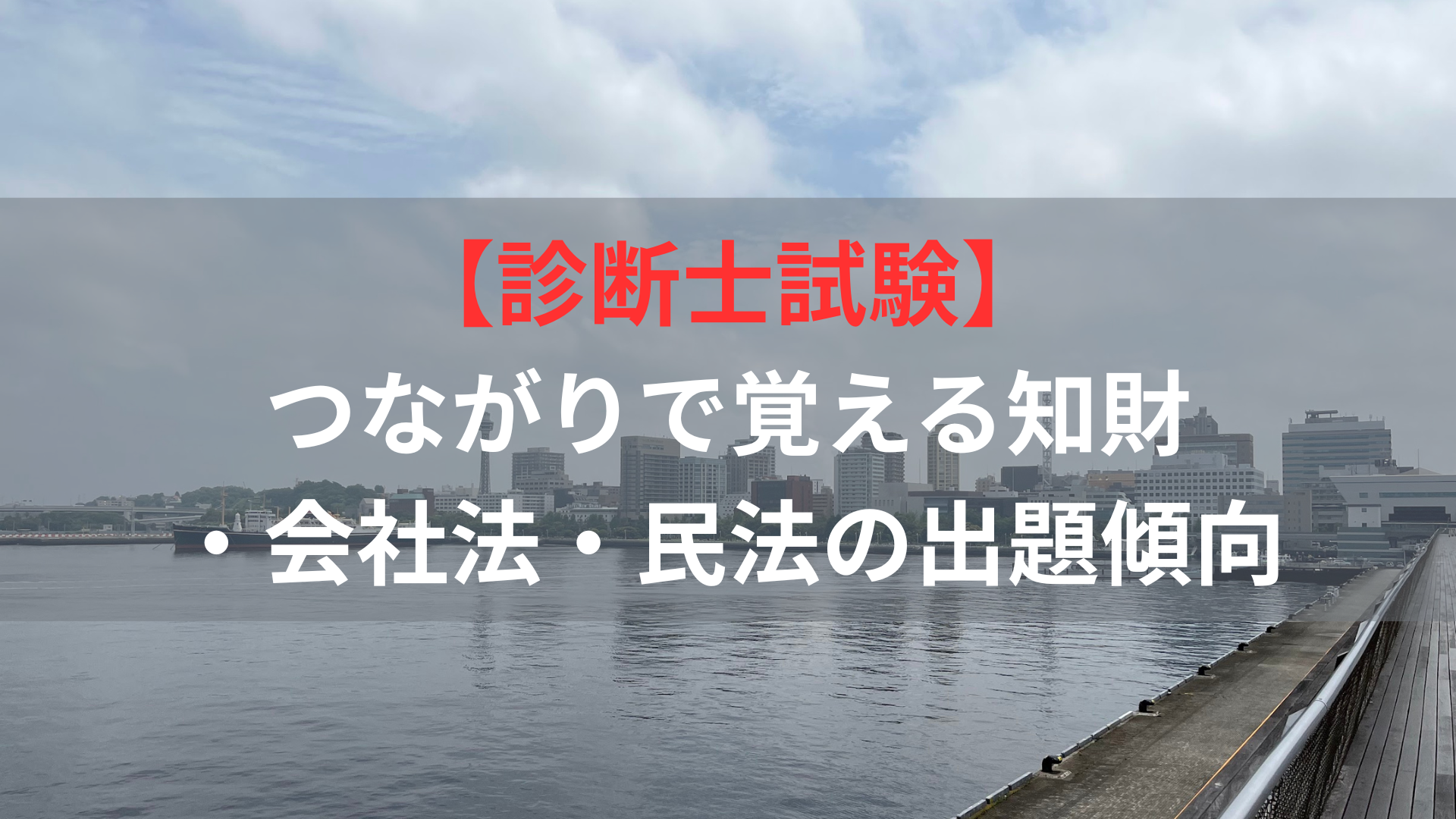
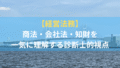

コメント