「STPや4Pは分かるけど、試験ではどう書けばいいのか分からない」──そんな悩みを抱えていませんか?
中小企業診断士試験の1次企業経営理論、そして2次事例Ⅱでは、このマーケティングの基本フレームワークが頻出します。
特に事例Ⅱでは、使いこなせるかどうかで得点が大きく変わると言っても過言ではありません。
この記事では、試験で差がつくSTP・4Pの本質と、過去問事例を活用した攻略法を診断士の視点で解説します。
STP・4Pが診断士試験で重要な理由
中小企業診断士試験では、マーケティングの基礎理論であるSTP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)と4P(製品・価格・流通・プロモーション)が毎年のように問われています。
特に1次試験の「企業経営理論」では単純な知識問題として出題され、正確に暗記していれば確実に得点できる分野です。
しかし、それ以上に差がつくのが2次試験の事例Ⅱです。
事例Ⅱは「ある企業の売上拡大策」をテーマにした問題が中心で、与えられた情報から市場を分析し、ターゲットやポジショニングを定め、適切なマーケティング施策(4P)を提案する力が求められます。実際、過去問の模範解答には必ずと言っていいほどSTPや4Pに基づいた記述が盛り込まれています。
つまり、STP・4Pは単なる知識ではなく、「フレームワークとして答案構成の軸になるもの」です。しっかり理解しておけば、与件の情報を整理する際にも、答案に説得力を持たせる際にも役立つのです。
逆に、ここが曖昧だと、どれだけ与件を読んでも筋の通った答案が書けず、大きな減点につながりかねません。
診断士試験において、STP・4Pは「知っているかどうか」ではなく、「使いこなせるかどうか」で差がつくのです。
ここからは、それぞれのフレームワークのポイントと、試験での活用法を具体的に見ていきましょう。

STP分析のポイントと試験頻出パターン
STPは、マーケティング戦略の方向性を決めるための基礎となる考え方です。
診断士試験では、1次の選択肢問題として定義や順序を問われるだけでなく、2次の事例Ⅱでは「市場のどこに焦点を当てるか」を論理的に示すためのフレームワークとして活用されます。
ここでは、それぞれの要素の試験でのポイントを押さえておきましょう。
セグメンテーション:市場をどう切るか?
セグメンテーション(市場細分化)は、まず市場を「特性の似た顧客のグループ」に分ける作業です。
試験では、地理的(エリア)、人口統計的(年齢・性別)、心理的(ライフスタイル・価値観)、行動的(利用頻度・購買動機)といった代表的な切り口が与件に散りばめられています。
ポイントは、与件の中からこれらに該当する記述を見つけ出し、グループ化して書くことです。
例えば「地元の高齢者が多く来店する商店街」という記述があれば、「高齢者層」というセグメントを設定できます。
ターゲティング:狙う市場の決め方
ターゲティングは、細分化した市場のうち、どのセグメントを狙うかを決める段階です。
試験では、単に「すべての顧客を対象とする」のではなく、「限られた経営資源の中で最も成果が見込める層を狙う」視点が重要です。
例えば、「近隣の主婦層が定期的に来店する」とあれば、そこに経営資源を集中する提案が好まれます。
ポジショニング:選ばれる立ち位置をつくる
ポジショニングは、ターゲット顧客にとっての「他社との違い」を明確にする段階です。
試験では、ポジショニングマップを頭の中で描き、与件の企業が空いているポジション(差別化できる点)に立てる提案を意識すると書きやすくなります。
例えば、「低価格なチェーン店と高級路線の専門店の間にある“こだわりの品質を手頃な価格で”」というように、与件の強みを活かせるポジションを示すのがポイントです。
過去問事例での出題例
過去の事例Ⅱでは、例えば平成29年度の設問で「地域の高齢者をターゲットにしたサービスの提案」が求められたり、平成30年度の事例で「競合が強い中での差別化戦略」が問われるなど、STPの視点が問われる問題が多数見られます。
過去問に取り組む際は、与件の中からセグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングに関わる記述を探し出し、答案に反映する練習をしておくと効果的です。
4Pの攻略法と過去問分析
STPで「誰に」「どんな立ち位置で」提供するかを決めたら、次に具体的な施策として考えるのが4Pです。
4P(Product, Price, Place, Promotion)は、診断士試験の2次事例Ⅱで頻出のテーマであり、答案の骨格をつくる上で非常に重要です。
ここでは、各要素ごとの攻略ポイントと過去問での出題パターンを確認していきましょう。
Product(製品)で問われる改善策のヒント
事例Ⅱでは、与件に現行の商品やサービスの課題が書かれているケースが多く見られます。
例えば「メニューが多すぎて管理が煩雑」「季節限定商品しか売れない」といった記述です。
ここから「ターゲット顧客のニーズに沿った商品開発」「商品ラインナップの絞り込み」など、的確な提案をするのが基本です。
重要なのは、与件の強みを活かしつつ改善する視点です。
Price(価格)で出る典型パターン
価格戦略は、特に小規模事業者の事例で問われやすいポイントです。
過去問では「競合より安くする」のではなく、「価値に見合った適正価格の設定」「高付加価値に見合う価格戦略」といった提案が好まれます。
値引き一辺倒ではなく、ターゲットが価格に対してどう感じるかに着目することが大切です。
Place(流通)で差がつく解答例
流通チャネルの見直しも頻出です。
例えば「既存顧客しか来店しない」という課題には、「オンライン販売の導入」「地域外の取引先開拓」など、新しいチャネルを追加する提案が有効です。
与件の強みとターゲット顧客の利便性を考慮して提案するのがコツです。
Promotion(販促)の書き方・キーワード
事例Ⅱで最も書きやすいのが販促提案です。
過去問では、「SNSの活用」「地元メディアとのタイアップ」「イベント開催」など、費用対効果の高い施策が好まれます。
ターゲットに届くメディアや手法を意識することで、具体性のある提案になります。
与件に記載の「顧客層の情報収集手段」や「口コミが強い」といったヒントも見逃さないようにしましょう。
過去問事例での出題例
例えば令和元年度の事例Ⅱでは、4Pそれぞれの施策を答案に盛り込むことで満点に近い評価が得られる模範解答がありました。
過去問に取り組む際は、与件から課題や強みを見つけ、それを4Pに沿って施策に落とし込む練習が効果的です。

高得点に繋げるSTP・4Pの学習法
STPと4Pは、診断士試験の合格に向けて必須のフレームワークです。
しかし、単に理論を暗記するだけでは試験本番で得点源にはなりません。
ここでは、高得点に繋げるための効率的な学習法をご紹介します。
抽象理論だけでなく事例で覚える
多くの受験生が陥りがちなのは、「STPはセグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング、4Pは製品・価格・流通・プロモーション」と定義だけを覚えて満足してしまうことです。
2次試験では、与件から読み取った情報をこれらのフレームに当てはめ、具体的な提案につなげる力が求められます。
過去問や模試で実際に答案を書き、フィードバックを受けることで実践力を養いましょう。
フレームワークシート活用のすすめ
学習中は、過去問の設問ごとに「STPの観点でターゲット層は誰か」「4Pの観点で改善すべきポイントは何か」を簡単に書き出す練習が効果的です。
自作のフレームワークシートや、市販の問題集に付属しているワークシートを活用することで、短時間でも効率よく繰り返し練習できます。
実務にも役立つおすすめ参考書・講座
診断士試験の学習は、単なる合格だけでなく、実務にも応用できる知識を身につけるチャンスです。
マーケティングの基礎を深めるために、以下の参考書・講座も併用すると理解が進みます。
📘 おすすめ参考書
• 『中小企業診断士 1次試験 過去問題集 企業経営理論』(同友館)
• 1次対策としてSTP・4Pの出題パターンがわかります。巻末の解説が充実しており、理論の復習にも最適です。
• 『コトラーのマーケティング・マネジメント 基本編』日経BP
• マーケティングの基本概念が網羅されており、診断士の知識の補強に最適です。
• 『グロービスMBAマーケティング 改訂4版』ダイヤモンド社
• フレームワークや実務的な考え方が豊富で、STPや4Pを実践的に理解するのに役立ちます。
🎓 おすすめ講座
• TAC中小企業診断士講座(1次・2次対策)
• TACの企業経営理論対策講座は、過去問を使いながらフレームワークを答案に活かす練習ができます。教室通学・Web通信どちらも対応しています。
• LEC中小企業診断士講座(2次集中答練)
• 2次試験特化の答練講座で、事例Ⅱの答案作成を通じてSTP・4Pの使い方を身につけられます。
どちらも診断士受験生向けに実務的な視点を意識したカリキュラムが組まれており、短期間で実践力が身につきます。
まとめ:STP・4Pは実務でも役立つ武器に
STPと4Pは、中小企業診断士試験において確実に得点源となる重要なフレームワークです。
1次試験では知識問題として、2次試験の事例Ⅱでは答案の柱として、ほぼ毎年のように出題されるテーマです。
しかし、単に理論を暗記するだけでは、本番で与件文から適切に情報を拾い、筋道の通った提案を書くことはできません。
今回ご紹介したように、過去問事例を活用し、フレームワークに沿って答案を構成する練習を積むことで、STP・4Pは強力な武器になります。
また、この学びは試験合格後の実務でも必ず役立ちます。
顧客視点で市場を捉え、経営改善策を立案する力は、診断士としての価値を高めてくれるでしょう。
ぜひ、STPと4Pを「知っている」だけで終わらせず、「使いこなせる」レベルまで引き上げ、試験突破とその先の活躍に活かしてください。
あなたの学びが実を結ぶことを願っています。

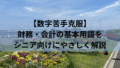

コメント