50代で資格試験や学び直しに挑戦する人の約6割が、半年以内にやめてしまう──ある調査でそんなデータが出ています。
原因の多くは、モチベーションの維持に失敗するからです。
中小企業診断士として、私は日々、企業の仕組み改善を支援していますが、その考え方は個人の学びにも応用可能です。
本記事では、診断士流「仕組み化」で学びが続く仕組みを解説します。
50代の学び直しが「3日坊主」で終わる理由
50代から学び直しや資格取得に挑戦する人の約6割が、半年以内に学習をやめてしまう──これは大手通信教育会社が行ったアンケート調査の結果です。
学び直しに意欲を持つ人が多い一方で、なぜこれほどの人が挫折してしまうのでしょうか。
原因のひとつは、「意志の力に頼りすぎている」ことです。
多くの人は「やる気があれば続けられる」と考えますが、意志の力は思いのほか脆いものです。
仕事や家庭の用事が立て込むと、つい学習が後回しになり、次第に習慣が途切れてしまうのです。
もうひとつの原因は、「環境や仕組みが学びを邪魔している」ことです。
例えば、学習スペースが片付いていなかったり、時間の管理が曖昧だったりすると、学びに取り組むまでの心理的ハードルが高くなります。
結果として、「今日は疲れたからいいや」「明日まとめてやろう」といった先延ばしが積み重なり、いつの間にかフェードアウトしてしまうのです。
学び直しを続けるためには、こうした意志任せのやり方から脱却し、意志に頼らずとも自然に行動できる「仕組み」を作ることが重要です。
次の章では、中小企業診断士の業務改善の知見をもとに、仕組み化の力について解説していきます。
診断士的視点で考える「仕組み化」の力
中小企業診断士の仕事の多くは、企業の「仕組み」を整えることです。
売上が伸び悩んでいる、ミスが多い、離職率が高い──こうした問題の多くは、社員の意識や努力不足ではなく、業務の仕組みや環境に原因があります。
そのため診断士は、現場の実態を分析し、仕組みを見直して改善することで成果を出していきます。
この「仕組み化」の考え方は、個人の学び直しにもそのまま当てはまります。
人は意志や気合いに頼るより、環境やルールの力に従う方がずっと行動しやすいのです。
たとえば、決まった時間に必ず学習できるスケジュールを組んだり、勉強道具を出しやすい場所に置いておいたりするだけでも、心理的な負担は大きく減ります。
また、業務改善の現場では「数値化」「見える化」という考え方も重視します。
進捗や成果を数値で記録し見える形にすることで、モチベーションを維持しやすくなります。
学び直しも同じで、学習時間や達成度を記録するだけで、継続の力になります。
このように、仕組み化は「やる気を必要としない状態」を作るための強力な武器です。
次の章では、具体的にどのような仕組みを作れば学び直しが続けやすくなるのか、診断士流の実践ステップをご紹介します。
学習継続のための仕組み化ステップ
ここからは、診断士が現場改善で用いるノウハウを応用し、学び直しを継続するための具体的な「仕組み化ステップ」をご紹介します。
ポイントは、環境整備・目標設定・進捗管理の3つです。
ステップ1|環境整備編(物理的・心理的)
まずは学習に取り組みやすい環境づくりから始めましょう。
診断士の現場でも「5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)」の徹底は基本です。
学習スペースを整え、必要な教材や文具をすぐに手に取れる状態にしておくことで、勉強の心理的ハードルを下げられます。
さらに、家族に学習時間をあらかじめ伝えておくのも効果的です。
「この時間は学習に集中する」というルールを周囲と共有しておくことで、邪魔されるリスクを減らせます。
ステップ2|目標設定編(OKR・KPIの考え方)
次に、目標を「数値化」して見える形にするのが大切です。
企業の業務改善でも用いられる OKR(Objectives and Key Results) の考え方は個人にも有効です。
例えば、「半年後に資格試験に合格する」というObjectiveに対して、「毎週10時間学習する」「模試で70点以上を取る」といったKey Resultsを設定します。
これにより、自分がどこまで進んでいるかがわかりやすくなり、やるべき行動が明確になります。
ステップ3|進捗管理編(ツール活用と見える化)
進捗管理は、モチベーションを維持する上で欠かせません。
診断士の現場でも、グラフやダッシュボードを使って改善状況を「見える化」します。
同様に、学習時間や達成度を記録する習慣を持ちましょう。
おすすめは、学習管理アプリや手帳を活用することです。
1週間単位で計画と実績を書き出し、進捗が確認できると達成感が得られます。
習慣化アプリを併用するのもよいでしょう。
さらに、小さな達成ごとに自分にご褒美を用意すると、前向きな気持ちが持続します。
仕組み化は、一度作ってしまえば意志に頼らずとも自然と行動を促してくれます。
次の章では、この仕組み化がもたらす成果と、学び直しの未来についてお伝えします。
仕組み化で得られる成果と未来
学び直しの仕組みを整えると、目に見える成果が現れ始めます。
まず実感できるのは、「続けることがラクになる」という変化です。
意志の力に頼っていた頃は、毎日「やろうか、やめようか」と悩むだけで消耗していましたが、仕組み化によって学習が習慣に組み込まれると、迷う時間がなくなり、自然と机に向かえるようになります。
次に、進捗の可視化による達成感も大きなモチベーションになります。
記録を振り返ったときに、積み上がった学習時間や過去の成果が一目でわかると、自分の成長が実感でき、さらに学びを続けたい気持ちが湧いてきます。
これは診断士が企業支援の現場で何度も見てきた「成果が成果を呼ぶ好循環」と同じです。
さらに、仕組み化は「学び続けられる人」という自信をもたらしてくれます。
50代以降の人生で「自分はまだ成長できる」という感覚は、大きな財産になりますし、仕事や家庭での姿勢にも良い影響を与えます。
あなたもぜひ、学びを仕組みに変えることで、これからの人生をもっと前向きに、もっと充実したものにしていきましょう。
まとめ|学び直しを続けるために「仕組み化」という選択を
50代からの学び直しは、決して遅くありません。
しかし、意志の力だけに頼っていては、忙しい日々の中で続けるのは難しいものです。
そこで重要になるのが、今回ご紹介した「仕組み化」の発想です。
中小企業診断士として現場改善を支えてきた私は、人や組織が変わるためには、無理のない仕組みを整えることが何よりも大切だと痛感しています。
その知見を個人の学びに活かせば、やる気や根性に頼らず、自然に行動が継続できる環境を作れます。
あなたもぜひ、今日から環境を整え、目標を見える化し、進捗を管理する仕組みを作ってみてください。
それが、これからの学びの習慣を支え、人生をもっと豊かにしてくれるはずです。

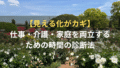
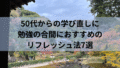
コメント