中小企業診断士試験は「難関国家資格」と呼ばれ、合格率も低く、ハードルが高い印象があります。
とくに50代からの挑戦となると、「記憶力が落ちている」「仕事や家庭と両立できるのか」といった不安がつきものです。
しかし実際には、50代の合格者も少なくないのが事実。
年齢別データ、受験回数、合格率の推移をもとに、「本当に可能かどうか」を冷静に分析していきます。
「受かるかどうか」ではなく、「どう戦略を立てるか」がカギです。
中小企業診断士とは?50代からでも挑戦する価値はある
中小企業診断士は、「経営コンサルタントの国家資格」として、幅広いビジネス知識と分析力を証明する専門資格です。
経済産業省の認定資格であり、企業内での昇進や転職、副業・独立にも活かせる実務性の高さが特徴です。
特に近年では、定年延長や再雇用を見据えたキャリアの再設計として、50代・60代から診断士を目指す人が増えています。
実際、令和5年度の中小企業診断士試験では、50代の合格者が全体の約2割以上を占めるなど、「年齢の壁」は決して高くないことが分かります。
また、50代だからこそ強みとなるのが「これまでの経験」。
診断士試験では、単なる暗記ではなく、事例に基づいた論理的思考力やビジネス視点が求められます。
長年の実務経験やマネジメント経験は、二次試験の事例問題において大きなアドバンテージとなり得ます。
さらに、資格取得後の選択肢も豊富です。
企業内診断士としてのポジション確保、副業としての経営支援、さらには定年後の独立開業まで、「知識資本」を活かした柔軟な働き方が可能になります。
✅ポイントまとめ:
• 中小企業診断士はビジネス系唯一の国家資格
• 50代以上の合格者も多数。年齢はハンデにならない
• 社会人経験が二次試験で強みに
• 資格取得後は「収入・自由・やりがい」の再設計が可能
診断士試験の難易度とは|偏差値・学習時間・合格までの年数
中小企業診断士試験は「ビジネス系資格の最高峰」と称されるほど、難易度が高いことで知られています。
一次試験・二次試験ともに出題範囲が広く、合格までには計画的な学習と相応の覚悟が必要です。
◆ 一次試験の難易度と合格率
一次試験は7科目(例:経済学、財務会計、企業経営理論など)にわたるマークシート方式で、合格率は毎年20〜30%前後。
ただし、全科目同時合格だけでなく、科目合格制度(3年間有効)があるため、50代の学習者でもペース配分をしながら挑戦しやすい設計となっています。
◆ 二次試験の難易度と合格率
一方、筆記と口述で構成される二次試験は、合格率が例年18%前後。
特に筆記試験(4つの事例問題)は記述式で、論理的な思考力と文章力が問われます。
「正解が1つに決まらない」という特性からも、一次よりもハードルが高いと感じる受験生が多いです。
なお、二次試験の受験資格は、一次試験合格年度を含む2年間有効です。
◆ 学習時間の目安と偏差値感覚
一般的に、合格に必要な総学習時間は1,000〜1,200時間程度といわれています。
これは、平日2時間・週末4〜5時間で1年半〜2年かけて合格するペース。
学力偏差値でいえば、日東駒専〜MARCH以上レベルの学力が必要という見方もあります。
◆ 合格までにかかる年数
実際には、一発合格する人はごく少数。
TACなどの大手予備校によるアンケートでも、1次・2次ともに通して合格するまでに平均2〜3年かかるケースが多数派です。
特に働きながら勉強する50代にとっては、長期戦を前提にした学習戦略が重要になります。
✅ポイントまとめ:
• 一次は科目数が多く、科目合格制がカギ
• 二次は記述式で“正解がない”試験。難関で差が出る
• 合格までの総学習時間は1,000時間超
• 一発合格は稀。2〜3年かけて戦略的に挑むのが現実的年齢別の合格者データ|50代・60代でも受かるのか?
「診断士試験は若い人向けの資格では?」
そんな先入観を持っている方も多いかもしれません。
しかし、実際の年齢別の合格者データを見ると、そのイメージは大きく覆されます。
◆ 50代の合格者割合は年々増加傾向
たとえば、令和5年度の中小企業診断士試験結果を見ると、50代以上の合格者が全体の20%超を占めています。
さらに、合格者の平均年齢はおよそ38〜40歳前後とされており、社会人経験者や中高年層が中心となっている資格試験であることがわかります。
過去5年の統計を見ても、40代・50代の合格者数は安定して多く、「中高年でも戦える試験」ということがデータで裏付けられています。
◆ 実務経験が評価されやすい試験構造
特に二次試験では、企業経営や事業戦略に関する事例を読み解き、課題解決の提案を記述する形式です。
これにより、現場で培った経験やビジネス感覚が武器になる傾向が強く、50代の受験者が高得点を出すことも少なくありません。
また、論点の整理や文章構成に必要な力は、社会人としての報告書作成や会議での提案経験などが自然と生きてきます。
単なる“若さ”よりも、「経験知」と「戦略的な学習」が結果に直結する点も、50代にとって追い風です。
◆ 60代合格者も存在する現実
さらに注目すべきは、60代の合格者も一定数存在していること。
「もう遅い」という思い込みこそが最大の壁であり、年齢よりも“準備力”と“継続力”が合否を左右するのが診断士試験の本質です。
✅ポイントまとめ:
• 合格者の2割以上が50代以上
• 二次試験ではビジネス経験が強みになる
• 年齢よりも「実務知+論理的訓練」の有無が合否を決める
• 60代合格者も珍しくなく、“いつからでも挑戦できる”資格
合格までの受験回数と成功パターン|一発合格は本当に可能?
中小企業診断士試験は、1次・2次あわせての“総合力”が問われる長期戦です。
「一発合格できるかどうか」が気になる方も多いかもしれませんが、現実はそれほど甘くはありません。
◆ 一発合格は“稀”。受験回数の平均は2〜3回
TACやLECといった大手予備校が実施する合格者アンケートでは、一次試験・二次試験ともに一発合格した人は2〜3割程度。
多くの合格者は、一次試験を複数年に分けてクリアし、その後に二次試験に進むというルートをたどっています。
とくに50代の場合、仕事や家庭との両立を図る必要があり、フルコミットできない状況が当たり前です。
そのため、「1回で受かる」よりも「何回かけても受かる」戦略のほうが現実的で、確実に成果を積み上げていく姿勢が重要です。
◆ 一次試験は“科目合格制”が味方
一次試験には、「60点以上の科目は翌々年まで持ち越せる」科目合格制度があります。
これを上手に使えば、1、2年目に3〜5科目、3年目に残りを合格というペース配分が可能で、働きながらでも着実に前進できます。
この制度は特に50代の受験者にとって非常に有効で、心理的な負担を軽減しながらゴールを目指せるのがメリットです。
◆ 二次試験は“反復学習”がカギ
一方、二次試験(記述式)は、初見では高得点を狙うのが難しい試験です。
与件文の読み取り、課題の特定、設問に沿った答案作成には、一定の訓練と“慣れ”が不可欠。
そのため、1回目で不合格になっても落ち込まず、2回目で合格する人が多数派です。
◆ 合格者に共通する成功パターンとは
実は、一発合格者よりも「失敗を踏まえて戦略を修正しながら合格した人」のほうが、その後の活動で活躍している傾向があります。
途中で諦めない、計画を柔軟に見直せる、継続して勉強できる。
こうした姿勢が、合格だけでなく診断士としての実務力にもつながるのです。
✅ポイントまとめ:
• 一発合格は全体の2〜3割。複数年計画が主流
• 科目合格制を活用すれば計画的に突破できる
• 二次試験は“練習量”が勝負の鍵
• 諦めずに戦略を練り直す人が、合格後も活躍している50代から診断士を目指す人がやるべき“準備”とは?
診断士試験は長期戦です。
そのため、学習を始める前に「どの教材がいいか」よりも前に、“合格まで走り切れる土台”を整えておくことが極めて重要です。
ここでは、50代から挑戦する方が、まず優先してやるべき準備を3つご紹介します。
◆ ① 時間管理の見直し:1日1時間でも「学習枠」を固定化
仕事・家庭・健康管理…50代は何かと忙しい世代です。
まずは「学習に使える時間」を無理なく確保する習慣づくりから始めましょう。
たとえば、平日は朝30分+夜30分、週末は90分など、“ルーティン化”するだけでも継続率は格段に上がります。
また、移動時間のスキマを活かせるように、スマホ学習に対応した環境を整えるのも有効です。
◆ ② 家族・職場の理解を得る:孤独な戦いにしない
診断士の学習は短くて1年、長ければ2〜3年に及びます。
その期間、周囲の協力や理解があるかどうかは、継続の成否を大きく左右します。
特に家庭では、「この時間は勉強に集中したい」「この日は模試がある」など、事前に目的と期間を共有しておくことが大切です。
同様に、職場に対しても「資格取得のために学んでいる」という姿勢を伝えておけば、意外と応援してくれるものです。
◆ ③ 学習方針を“診断士的に”考える:戦略なき努力は続かない
診断士試験そのものが「戦略を立てて課題解決する力」を問う試験です。
学習もまた、「自分はどこが弱いのか」「何に時間をかけるべきか」を診断士的に自己分析し、PDCAを回すことが必要です。
最初に「一次試験は2年かける」「得意科目は初年度に固める」といった戦略的な全体像を描いておくことが、途中の迷いや焦りを防ぎます。
◆ 学習法や教材の選び方が知りたい方へ
50代に適した独学法やおすすめ教材については、以下の記事で詳しく紹介しています。

✅ポイントまとめ:
• 学習時間を“固定枠”として生活に組み込む
• 周囲の理解を得ることで継続率が上がる
• 自己分析→戦略→実行のPDCAを「診断士的に」実践する
• 教材選びは後回しでもOK。まずは“続けられる自分の土台”づくりから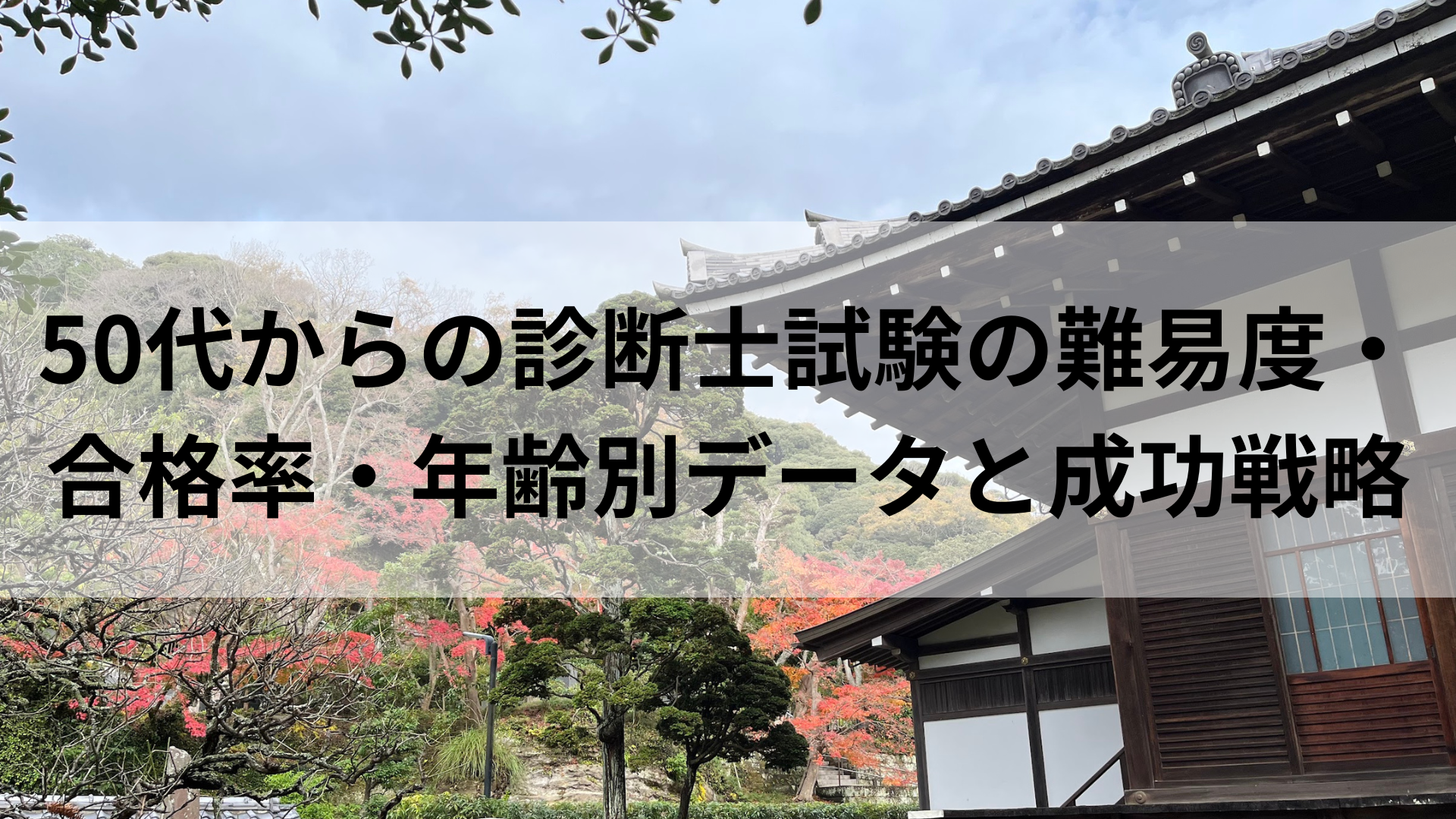


コメント